2年前にフィンランドの写真家ペンティ・サマラッティの写真展を京都の何必館で見た。
友達が褒めてたので雨の中、急遽京都まで遠征して見てきたけど、見てよかった。
久しぶりにプリントを買いたくなりましたが、図録買って帰り道のバーでうっとりと眺めてる。

友達のレビューを踏まえて見たので2倍楽しめたけど、こういう写真は好きだなぁ。
構図や内容はついあざとくなってもいいくらいだと思う決まりすぎ写真もあるのに
実際に見るとあざとくないのよね。

それは彼の言葉にも表れていて「写真は撮るものではない、受け取るもの」
「理想的な写真家とは、誰にも気づかれず、何にも影響を与えず、ただ観察している人のことだろう」
日本画をする時に最初に叩き込まれた、描くよりもまずよく見ることがほとんどだ、というのを
描かなくなってからも信じているので、これはストンと腑に落ちました。
また、この1年ずっと読んでるハンナ・アレントの「人間の条件」の中の「観照」のことも
思い浮かべ、サマラッティのいう「観察」と似たところについて考えました。
ソクラテスは、突然、ある想念に打たれて、周りのことに気が付かず、忘我の状態に放り込まれ、何時間も完全に身動きしないことがあった。この衝撃的な驚きが本質的に言語を欠くものであって、(略)少なくとも、「驚き」を哲学の始まりと考えていたプラトンとアリストテレスが、多くの点でこれほど決定的に意見を異にしながら、言論を欠くある状態、観照という本質的に言論を欠く状態が哲学の目的であることに同意した理由を説明するだろう。実際、「観照」というのは「驚き」の別の表現にすぎない。哲学者が最終的に到達する真理の観照は、彼が最初に抱いた、哲学的に洗練された言葉のない驚きだからである。
ハンナは、「観照者」は製作をしない、ただ「あるがままにものを残して、滅びることのない永遠なるものと隣り合わせになっている」と言います。
ただこれらは「観照」が「工作人」の製作の活動力とのヒエラルキーの順序に
転倒があったという文脈で書かれているのでここだけ抜き出してもよくわからないかもしれませんが。
製作者(工作人)ではなくまず観照者であれ、作るのではなくただ受け取ればいいのだ、
個人のささいな個性や工夫より世界の方が遥かに多彩で驚きに満ちて素晴らしいと
写真家としてサマラッティは言っているのだろうし、わたしもそう思っています。

友達が褒めてたので雨の中、急遽京都まで遠征して見てきたけど、見てよかった。
久しぶりにプリントを買いたくなりましたが、図録買って帰り道のバーでうっとりと眺めてる。

友達のレビューを踏まえて見たので2倍楽しめたけど、こういう写真は好きだなぁ。
構図や内容はついあざとくなってもいいくらいだと思う決まりすぎ写真もあるのに
実際に見るとあざとくないのよね。

それは彼の言葉にも表れていて「写真は撮るものではない、受け取るもの」
「理想的な写真家とは、誰にも気づかれず、何にも影響を与えず、ただ観察している人のことだろう」
日本画をする時に最初に叩き込まれた、描くよりもまずよく見ることがほとんどだ、というのを
描かなくなってからも信じているので、これはストンと腑に落ちました。
また、この1年ずっと読んでるハンナ・アレントの「人間の条件」の中の「観照」のことも
思い浮かべ、サマラッティのいう「観察」と似たところについて考えました。
ソクラテスは、突然、ある想念に打たれて、周りのことに気が付かず、忘我の状態に放り込まれ、何時間も完全に身動きしないことがあった。この衝撃的な驚きが本質的に言語を欠くものであって、(略)少なくとも、「驚き」を哲学の始まりと考えていたプラトンとアリストテレスが、多くの点でこれほど決定的に意見を異にしながら、言論を欠くある状態、観照という本質的に言論を欠く状態が哲学の目的であることに同意した理由を説明するだろう。実際、「観照」というのは「驚き」の別の表現にすぎない。哲学者が最終的に到達する真理の観照は、彼が最初に抱いた、哲学的に洗練された言葉のない驚きだからである。
ハンナは、「観照者」は製作をしない、ただ「あるがままにものを残して、滅びることのない永遠なるものと隣り合わせになっている」と言います。
ただこれらは「観照」が「工作人」の製作の活動力とのヒエラルキーの順序に
転倒があったという文脈で書かれているのでここだけ抜き出してもよくわからないかもしれませんが。
製作者(工作人)ではなくまず観照者であれ、作るのではなくただ受け取ればいいのだ、
個人のささいな個性や工夫より世界の方が遥かに多彩で驚きに満ちて素晴らしいと
写真家としてサマラッティは言っているのだろうし、わたしもそう思っています。















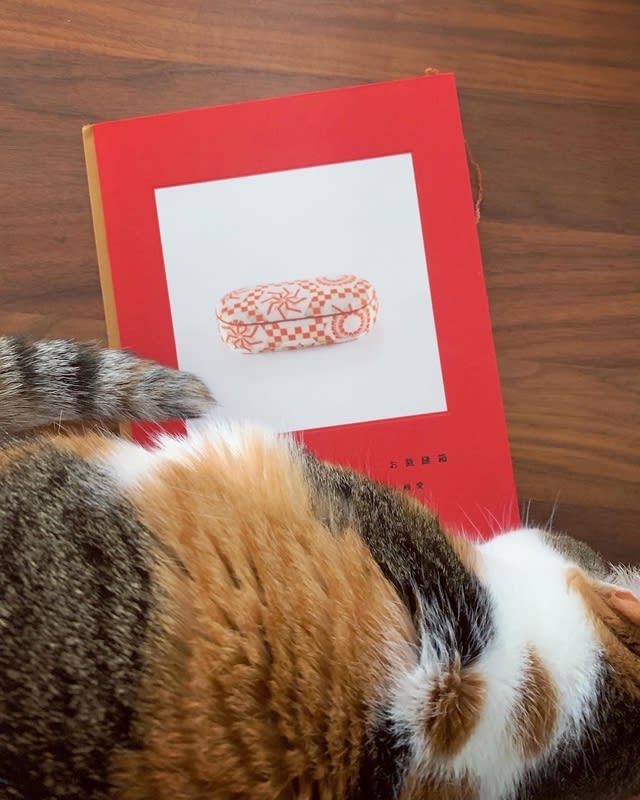
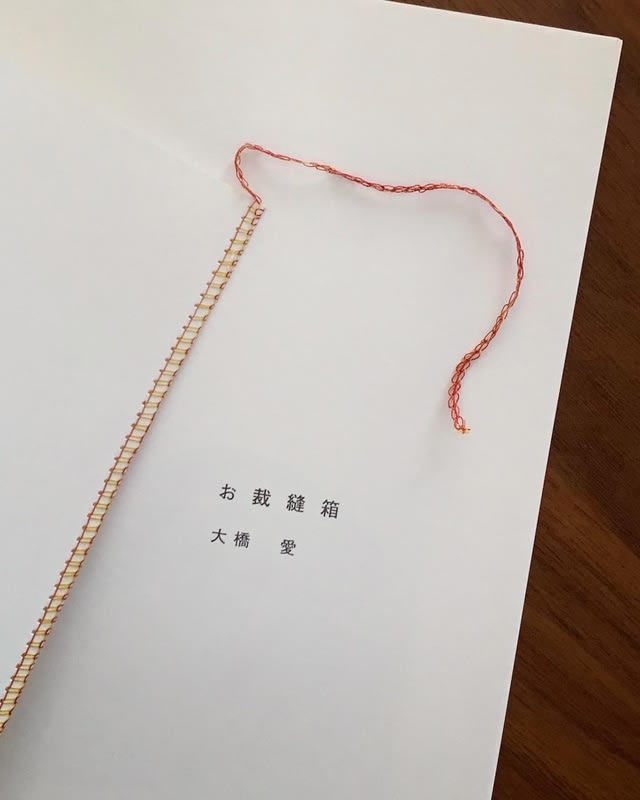
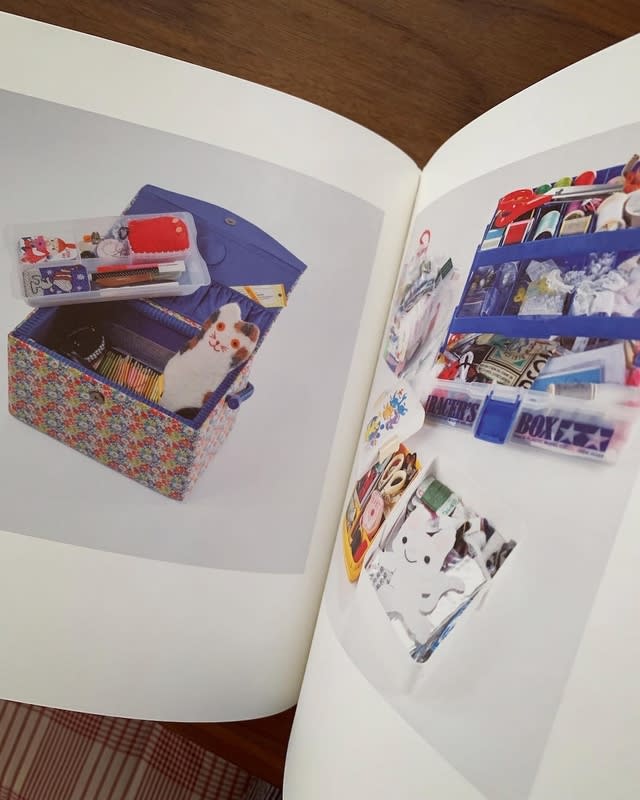















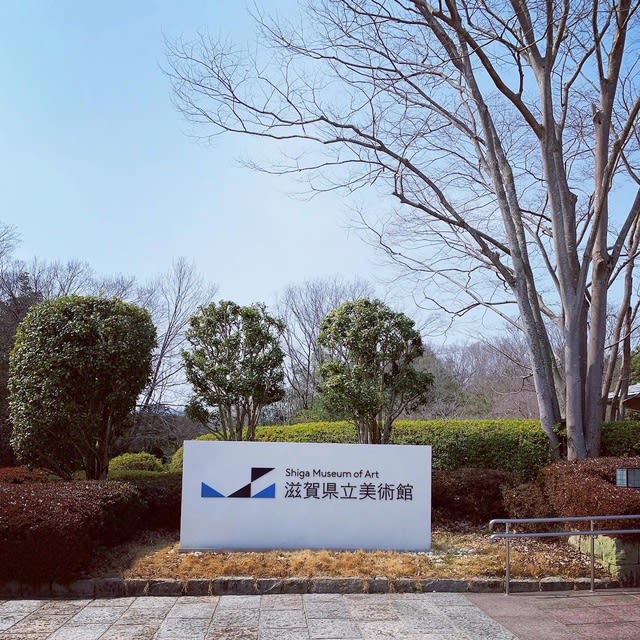




















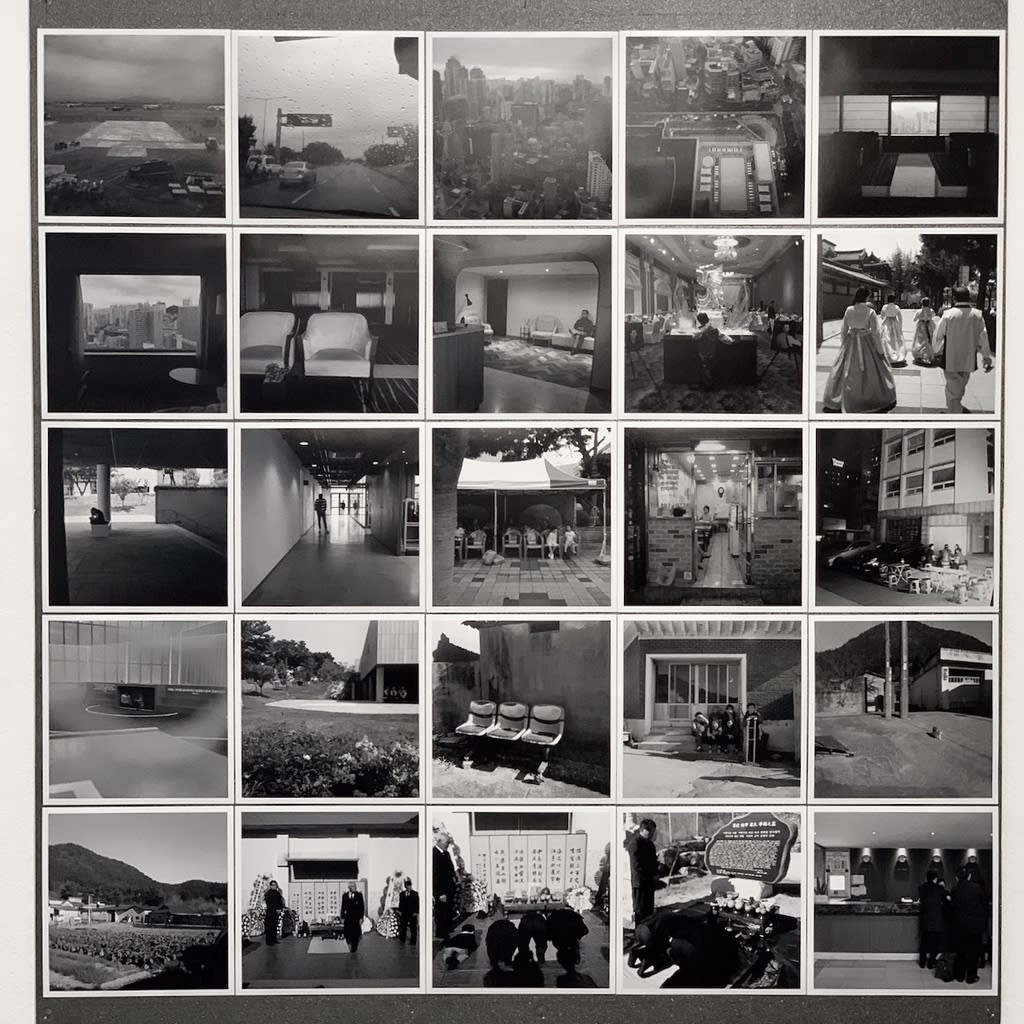





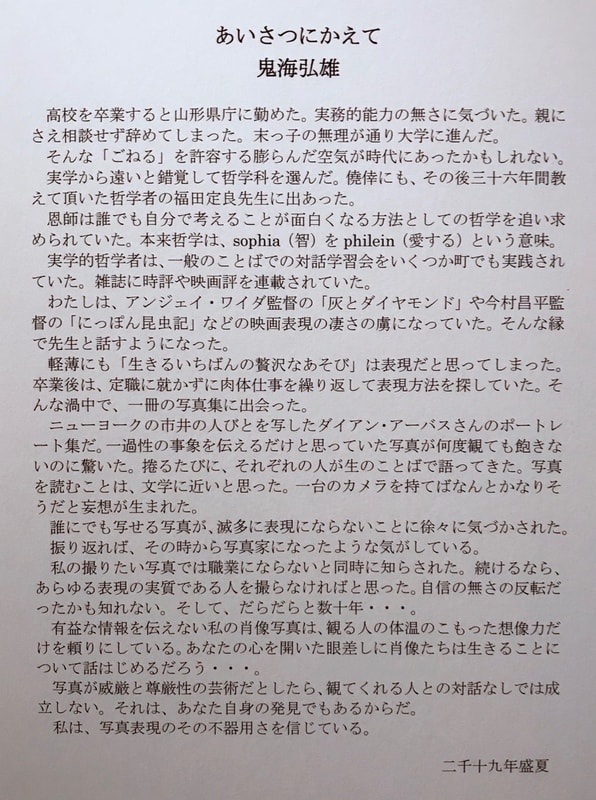

 」
」















 今回の春画のやつは、自分が日本画卒業生で、
今回の春画のやつは、自分が日本画卒業生で、