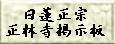正林寺御住職指導(R2.3月 第194号)
仏縁とは、仏との間に結ばれる縁のことをいいます。一般世間的に考えられている仏とは、仏壇に安置された本尊となる仏像や御先祖(位牌・お墓)、死者を呼ぶ場合が通例とされています。そのような仏との縁を結ぶ多い時代が末法の仏縁といえるでしょう。
しかし、その仏縁は、残念ながら現時の末法において正しい仏縁とはいえません。本来の釈尊が説かれた仏という意味からは適切でないからです。
末法のあるべき仏とは、値いがたき法華経の行者であるからです。仏である釈尊が説かれた法華経から離れては、末法時代において幸せとなる仏縁を結ぶことにはなりません。
正しい仏縁とは、値いがたき法華経の行者が説かれた、三大秘法の南無妙法蓮華経と仏縁を結ぶことであります。ここで南無妙法蓮華経でも、三大秘法が重要であります。三大秘法とは「本門の本尊」「本門の戒壇」「本門の題目」のことです。
値いがたき法華経の行者である宗祖日蓮大聖人は『法華取要抄』に、
「本門の本尊と戒壇と題目の五字となり」(御書736)
と、三大秘法について御指南であります。
さらに大聖人は『報恩抄』にも、
「一つには日本乃至一閻浮提(えんぶだい)一同に本門の教主釈尊を本尊とすべし。所謂(いわゆる)宝塔の内の釈迦・多宝、外(そのほか)の諸仏並びに上行等の四菩薩脇士(きょうじ)となるべし。二つには本門の戒壇。三つには日本乃至漢土月氏一閻浮提に人ごとに有智無智をきらはず一同に他事をすてヽ南無妙法蓮華経と唱ふべし。」(御書1036)
と、はじめて身延期に三大秘法の名目を明かされました。ここで種脱相対の上から「本門の教主釈尊」とは第六の文底の教主釈尊である日蓮大聖人であり、「宝塔の内の釈迦」とはインド応誕の脱益仏法である釈尊のことであります。
多くの人が他事を捨てて三大秘法の南無妙法蓮華経と仏縁を結び、大切にする信行に取り組むことで、三災七難をも止めて法界・世界を動かす本当の幸福が到来します。つまり、大聖人は『上野殿御返事』に、
「今、末法に入りぬれば余経も法華経もせん(詮)なし。但南無妙法蓮華経なるべし。」(御書1219)
と仰せであります。さらに『聖愚問答抄』には、
「南無妙法蓮華経とだにも唱へ奉らば滅せぬ罪や有るべき、来たらぬ福(さいわい)や有るべき。真実なり甚深なり、是を信受すべし。」(御書406)
と仰せであります。
しかし、この度の新型コロナ(COVID-19)による災難は、大聖人が『治病大小権実違目』に、
「三災七難疫病起こり」(御書1238)
と仰せである疫病に当たり、世間的には不謹慎かも知れませんが、仏教の観点からは世界の多くの人が他事(邪宗邪義)を捨てて、南無妙法蓮華経の仏縁を大切にしない正法誹謗の因果応報であります。
三災七難とは、三災が穀貴・兵革・疫病であります。
①穀貴とは、五穀の価が異常に高騰する物価騰貴のこと。
②兵革は戦争。
③疫病は伝染病や流行病など、まさに新型コロナウイルス感染症のこと。
大聖人は『守護国家論』に、
「世間の安穏を祈らんに而も国に三災起こらば悪法流布する故なりと知るべし。」(御書143)
と御指南であります。
七難は薬師経などに説かれています。大聖人は『立正安国論』に、
「薬師経に云はく『若(も)し刹帝利(せっていり)・潅頂王(かんじょうおう)等の災難起こらん時、所謂人衆疾疫(にんじゅしつえき)の難・他国侵逼(しんぴつ)の難・自界叛逆(ほんぎゃく)の難・星宿変化(せいしゅくへんげ)の難・日月薄蝕(にちがつはくしょく)の難・非時風雨の難・過時不雨の難あらん』已上。」(御書236)
と御指南であります。七難の意味について、
①人衆疾疫難(伝染病が流行り、多くの人が死ぬ)
②他国侵逼難(外国から侵略され、脅かされる)
③自界叛逆難(内部分裂や同士討ち)
④星宿変怪難(天体の運行に異変が起こる)
⑤日月薄蝕難(日食や月食)
⑥非時風雨難(季節はずれの暴風や強雨)
⑦過時不雨難(雨期に雨が降らない天候不順)
以上、正法を誹謗することによって起こる七種の難で、経典によってその内容に多少の差異があります。
まさに末法のあるべき仏、南無妙法蓮華経を唱える法華経の行者ではない、一般世間的な仏や仏教以外の神では、法界・世界まで動かし三災七難をも止める力はありません。それは現実の権教謗法のみ多い神仏の力を眼前にすれば、新型コロナウイルスの他に、昨年(2019)十月の台風十九号(ハギビス)などの天変地異まで抑える力のないことは明白です。いまだに権教謗法のみ多い現実を見た時に、今年も⑥非時風雨難である台風やゲリラ豪雨の影響は払拭できません。
ところが、他宗から信仰の寸心を改めて本門の本尊を信じ本門の題目である南無妙法蓮華経を唱える人が多くなり、異体同心し様々な分野で力を合わせて生きていけば必ず変わります。世の中の多くの人は、爾前権教や他宗教では法界を動かす力が限界であることを即刻さとるべきです。
もし、疫病である新型コロナウイルス感染症が終息せずに、このまま進んだ場合、①人衆疾疫難へと拡大する危険性があります。まさにパンデミックです。
そして、最前線で命がけの治療に関わる貴重な医療従事の皆さんには、三大秘法の南無妙法蓮華経と仏縁を結ばれ信心の上から解決策を生み出す時が来ているのではないでしょうか。
他宗派の寺社へ、今年も一月の元旦には初詣にて大勢の方がお参りされたことでしょう。また二月には節分会もありました。その時の祈りは、はたして新型コロナをも寄せ付けずに回避し、日本の経済に影響しない絶大な力がある祈り願いとして叶えられているでしょうか。他宗派で祈念された方は、是非、過去からのルーティーン(習慣)に終始している姿を、冷静に自問自答されるべきです。また今月は春季彼岸会の月でもあります。御先祖の彼岸供養において、この機会に見直されるべき時ではないでしょうか。御先祖の末法にあるべき供養は、法華経に依らなければいけません。法華経でも三大秘法の南無妙法蓮華経でなければならないのです。
そのルーティーンから卒業して、総じての法華経の行者に加わり日蓮正宗総本山に在す本門戒壇の大御本尊を信じ、南無妙法蓮華経の仏縁を大切にする人が多くなれば、仏天の加護のもとに生活を送ることができます。それが宗祖日蓮大聖人の仏法であります。
南無妙法蓮華経の仏縁の出発は、西暦1052年から始まった末法時代に、日蓮大聖人は『南条兵衛七郎殿御書』に、
「当世は正像二千年すぎて末法に入りて二百余年なり。」(御書323)
と仰せのように、南無妙法蓮華経と唱えられた一番はじめ、末法に入り約200年後の建長五年(1253)三月二十八日であります。三時(正法・像法・末法)弘教の次第から大聖人は末法万年尽未来際を見据えられて、宗旨建立の内証を宣示あそばされました。
大聖人は『清澄寺大衆中』に、
「建長五年三月二十八日、安房国東条郷清澄寺道善の房持仏堂の南面にして、浄円房と申す者並びに少々の大衆にこれを申しはじめて」(御書946)
と仰せであります。
内証宣示あそばされた題目には、すでに「文底秘沈」の深義から三大秘法が秘められた宣示と拝します。
私達自身の修行となる自行では、南無妙法蓮華経の仏縁を大切にすることは当たり前です。さらに、化他行である折伏において、この度の三災七難である疫病の新型コロナには世界の宗教や一般世間的な仏では、法界まで動かす力がないことを教えて、現実の権教謗法のみ多い仏の力を眼前にすれば、天変地異まで抑える力のない現証を認識して、信仰の寸心を改めるように仏縁を結ぶ下種折伏が大切になります。
そのような現実からも御法主日如上人猊下の御命題である法華講員八十万人体勢構築は急務であり、必ず達成させて頂くことが重要であります。
三月中は疫病の影響により信心活動に支障はありますが、三災七難が降りそそぐ環境の中でも自行化他に邁進できる広布の戦士として、信力行力のスキルアップが求められているでしょう。
まさに御法主日如上人猊下が常々御指南である、
「万難を排し」(大日蓮 第887号)
との実践的な修行として絶好の環境であります。三災七難が降りそそぐ環境の中でも、御本尊への唱題を中心に御仏智をいただきながら創意工夫して、折伏活動することが必要です。まさしく大聖人は『御義口伝』に、
「難来たるを以て安楽と意得べきなり」(御書1763)
と仰せであります。
そして、他宗派での滝行等の荒行と称する難行苦行は、当宗で行わなくとも邪宗邪義の害毒が起因する三災七難に直面して自行化他に精進するところに、総ての難行苦行の要素が人生の四苦八苦や三障四魔の姿として網羅されています。そのために敢えて荒行と称する難行苦行を進んで行う必要は一切ありません。必然的に末法五濁悪世は、生きていくこと自体が難行苦行を強いられていることを理解しましょう。
大聖人は『椎地四郎殿御書』に、
「大難なくば法華経の行者にはあらじ。」(御書1555)
と仰せであります。
最後に御法主日如上人猊下は、
「三大秘法の大御本尊への絶対的確信」(大日蓮 第743号)
と御指南であります。南無妙法蓮華経の仏縁を大切にする一番重要なことであります。世界と日本の人口比率において、大御本尊への絶対的確信を堅持する人口が多くなれば、必然的に依正不二の原理により三災七難を抑制した法界・世界へと変わることを確信すべきであります。
その原点を大聖人は『異体同心事』に、
「日蓮が一類は異体同心なれば、人々すくなく候へども大事を成じて、一定(いちじょう)法華経ひろまりなんと覚へ候。悪は多けれども一善にかつ事なし。」(御書1389)
と仰せであります。まさに、この極限の最中「人々すくなく候へども大事を成じて(中略)悪は多けれども一善にかつ事なし」との御書を心肝に染めて、法華講の皆さんは仏道修行の灯が消えないように精進致しましょう。
宗祖日蓮大聖人『新池御書』に曰く、
「雪山の寒苦鳥は寒苦にせ(責)められて、夜明けなば栖(す)つくらんと鳴くといへども、日出でぬれば朝日のあたゝかなるに眠り忘れて、又栖をつくらずして一生虚(むな)しく鳴くことをう(得)。一切衆生も亦復(またまた)是くの如し。地獄に堕ちて炎にむせぶ時は、願はくは今度人間に生まれて諸事を閣(さしお)いて三宝を供養し、後世菩提をたす(助)からんと願へども、たまたま人間に来たる時は、名聞名利の風はげしく、仏道修行の灯(ともしび)は消えやすし。」(御書1457)