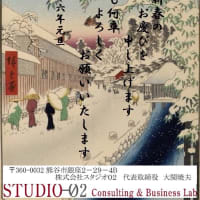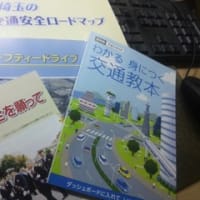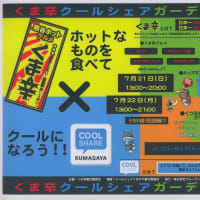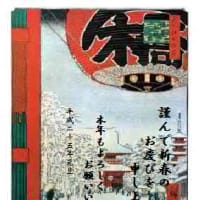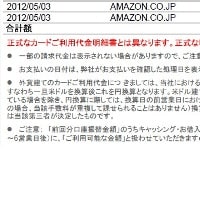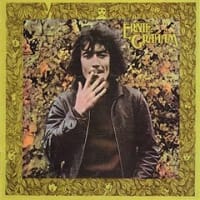「村田クンシリーズ」にコメントをいただいた「87」さん、ありがとうございます(彼の同級生=先輩ですね?)。
先週末は所用がありまして久しぶりにお茶の水に行ってきました。お茶の水と言えば村田クンとよく学校帰りにブラブラした懐かしい街です。その後も予備校時代に毎日通った街でもあり、用事を済ませた後に“あの頃”を訪ねてひとりぶらついてみました。まず、驚いたのは、「駿河台の坂道ってこんなに楽器屋さんが多かったっけ?」と言う点。たしかにイシバシとか下倉とか楽器屋がいくつかあったのは記憶にあるのですが、道の両側をこんなにも軒を連ねていたとは思えないのです。高校時代はバンドをやっていましたたから、けっこう楽器を冷やかしにイシバシあたりには行った記憶があるのですが、これは驚きだなと。ある意味秋葉原の電器街以上のものがあるように思いました。
何が驚きかと言うと、こんなに楽器屋さんが軒を連ねていて皆商売になっていると言う事が驚きな訳です。秋葉原だって今やヤマダやコジマに押されて、家電販売を生業とする店舗はむしろジリ貧状態。近年はPCに端を発した“おタク向けビジネス”が、すっかり街の事業ドメインになっており、古くからの事業ドメインである家電販売業は同業店舗の集積がむしろ減少するパイの食い合いを産み、もはやつぶし合いの様相を呈しているのです。お茶の水の林立楽器店はそうはならないのでしょうか?当然、お茶ノ水の楽器屋さん間にも激しい価格競争はあるでしょうから、よほど需要が伸びていない限りはやはりつぶし合いのジリ貧が待っているように思うのです。でもさにあらず・・・。
理由を考えてみると、商品サイクルが長く在庫回転率が悪くとも不良在庫は発生しにくいこと、楽器の原価率が低いであろうこと、は想像できるところですが、それ以上に彼らを力強く支える理由がマーケットに存在するように思います。我々時代に比べて少子化の影響で確かに若年層の楽器演奏人口は減少の一途にあると思います。しかしながら、それ以外の層の楽器需要が意外に伸びているのではないでしょうか。そうですいわゆる“ギター小僧”“バンド小僧”OBの連中です。我々の高校時代に40代以上のオヤジ層で楽器をいじったりバンド活動をしたりなんていうのは、ごくごく稀なケースだったじゃないですか。ところが今はどうでしょう?子供も大きくなって生活も安定して、“昔取った杵柄”とかなんとかで「オヤジバンド」をはじめる連中の何と多いことか。オヤジバンド・コンテストなんてものもあこちで催されるようになり、やりがいも手伝って中年バンド・ブームが定着してきていると言ってもいいと思うのです。
しかもオヤジは、高校生に比べて金持ってますから。昔はなかなか手が出なかったギター・エフェクターの“大人買い”とか、ギブソンやフェンダー等憧れの海外ブランド・ギターの衝動買いとかもバンバンある訳で、この業界は実は20~30年前に比べるとかなりマーケットが大きくなっていると言えるのではないでしょうか。それと、秋葉原の主流ビジネスが家電からPC関連に移った最大の要因は、おタクの存在です。要するにPCやゲームのマーケットには相当数のオタクが存在しており、彼らの「好きなモノには金に糸目をつけない」という行動特性が安定的な需要を支えている訳なのです。楽器もPCほどではないにしても、マーケット比率的にそれなりの規模のオタクは存在する訳で、これが資金力のある中年層中心と考えるならかなり肥沃なマーケットであると言えるのかもしれません。
お茶ノ水を歩いていて、そんなことをちょっと考えさせられました。
お茶の水古今物語はもうひとネタありましたので、それは次回に。
先週末は所用がありまして久しぶりにお茶の水に行ってきました。お茶の水と言えば村田クンとよく学校帰りにブラブラした懐かしい街です。その後も予備校時代に毎日通った街でもあり、用事を済ませた後に“あの頃”を訪ねてひとりぶらついてみました。まず、驚いたのは、「駿河台の坂道ってこんなに楽器屋さんが多かったっけ?」と言う点。たしかにイシバシとか下倉とか楽器屋がいくつかあったのは記憶にあるのですが、道の両側をこんなにも軒を連ねていたとは思えないのです。高校時代はバンドをやっていましたたから、けっこう楽器を冷やかしにイシバシあたりには行った記憶があるのですが、これは驚きだなと。ある意味秋葉原の電器街以上のものがあるように思いました。
何が驚きかと言うと、こんなに楽器屋さんが軒を連ねていて皆商売になっていると言う事が驚きな訳です。秋葉原だって今やヤマダやコジマに押されて、家電販売を生業とする店舗はむしろジリ貧状態。近年はPCに端を発した“おタク向けビジネス”が、すっかり街の事業ドメインになっており、古くからの事業ドメインである家電販売業は同業店舗の集積がむしろ減少するパイの食い合いを産み、もはやつぶし合いの様相を呈しているのです。お茶の水の林立楽器店はそうはならないのでしょうか?当然、お茶ノ水の楽器屋さん間にも激しい価格競争はあるでしょうから、よほど需要が伸びていない限りはやはりつぶし合いのジリ貧が待っているように思うのです。でもさにあらず・・・。
理由を考えてみると、商品サイクルが長く在庫回転率が悪くとも不良在庫は発生しにくいこと、楽器の原価率が低いであろうこと、は想像できるところですが、それ以上に彼らを力強く支える理由がマーケットに存在するように思います。我々時代に比べて少子化の影響で確かに若年層の楽器演奏人口は減少の一途にあると思います。しかしながら、それ以外の層の楽器需要が意外に伸びているのではないでしょうか。そうですいわゆる“ギター小僧”“バンド小僧”OBの連中です。我々の高校時代に40代以上のオヤジ層で楽器をいじったりバンド活動をしたりなんていうのは、ごくごく稀なケースだったじゃないですか。ところが今はどうでしょう?子供も大きくなって生活も安定して、“昔取った杵柄”とかなんとかで「オヤジバンド」をはじめる連中の何と多いことか。オヤジバンド・コンテストなんてものもあこちで催されるようになり、やりがいも手伝って中年バンド・ブームが定着してきていると言ってもいいと思うのです。
しかもオヤジは、高校生に比べて金持ってますから。昔はなかなか手が出なかったギター・エフェクターの“大人買い”とか、ギブソンやフェンダー等憧れの海外ブランド・ギターの衝動買いとかもバンバンある訳で、この業界は実は20~30年前に比べるとかなりマーケットが大きくなっていると言えるのではないでしょうか。それと、秋葉原の主流ビジネスが家電からPC関連に移った最大の要因は、おタクの存在です。要するにPCやゲームのマーケットには相当数のオタクが存在しており、彼らの「好きなモノには金に糸目をつけない」という行動特性が安定的な需要を支えている訳なのです。楽器もPCほどではないにしても、マーケット比率的にそれなりの規模のオタクは存在する訳で、これが資金力のある中年層中心と考えるならかなり肥沃なマーケットであると言えるのかもしれません。
お茶ノ水を歩いていて、そんなことをちょっと考えさせられました。
お茶の水古今物語はもうひとネタありましたので、それは次回に。