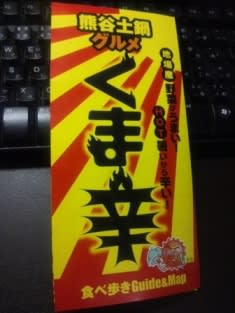熊谷「食」の街おこし「くま辛」の「食べ歩きガイド&マップ(写真)」が市内各所で配布され始めています。
本冊子には、「くま辛」の説明、市長へのQ&Aと参加店の基本情報と地図が掲載されています。「メニューは出ていないの?」というご質問をよく受けるのですが、「くま辛」はメニューが参加店の都合で頻繁に変更になる可能性があるため、常に最新の情報を掲載続けることが難しいのでやむを得ずこの形をとらせていただきました。ですので、メニューが気になる皆さま、恐れ入りますがパンフレット記載の電話番号で直接お店にお問い合わせください。準備が整いましたら、WEBで最新メニュー一覧を掲載できるよう頑張ります!その辺につきましてはどうかご理解のほどよろしくお願いいたします。
現在の配布スポットですが、参加店に加えて市役所および熊谷駅前観光案内所はじめ熊谷市の関係施設で絶賛配布中です。お分かりにならない場合は、写真のパンフと同じデザインののぼりが立っているお店が目印です。「くま辛パンフください!」とお気軽にお声かけください。熊谷駅周辺を歩いていますと、かなりのぼり旗が目立ってきました。私も続々参加店のメニューをいただいてみておりますが、どれもこれも実に個性的に仕上がっておりまして、素晴らしきことこの上なしです。ぜひこのパンフレットを入手して「くま辛」食べ歩きを実践してみてください。
(青山カレー工房のHPトップページ中ほど右手の「くま辛」ポスターバナーから、パンフレットのPDF画面に入れます。URLは下をご参照ください)
メディアでの「くま辛」取り上げも続々です。NHKさんはすでにラジオ第一とFM放送でお取り上げいただき、来週はいよいよテレビ取材が予定されています。放映は12日(木)午前11台の「こんにちは、いっと6けん」の予定です。本日はFM局NACK5さんがご来店され、パーソナリティの三遊亭鬼丸さんが直接取材してくれました。放送予定は14日午後2時台とか。詳しく分り次第お知らせいたします。今後もテレビ、ラジオでいろいろな「くま辛」参加のお店が紹介されると思いますので、お楽しみに。
さて青山カレー工房ですが、「くま辛」メニュー「熊谷大和芋カレー(720円)」大好評です。「クセになる味と触感!」と皆さん大変気に入っていただき嬉しいかぎりです。しかし本日は夕方時点で売切れ。その後来店された方、ごめんなさい。たくさんご用意しているのですが、お持ち帰りニーズも多く、日によっては早めに売り切れてしまうこともありますので、お早めにご来店いただければ幸いです。来週からは食べ歩き用のミニサイズ(450円)もご用意いたします。皆さまのご来店お待ち申し上げます。
◆メディア取材のお申し込みは、熊谷倶楽部くま辛実行委員会広報窓口 �048-580-7440(スタジオ02)または048-598-8091(青山カレー工房)へお願いいたします。
◆くま辛については、
http://blog.goo.ne.jp/ozoz0930/e/18cef0712baa171ac98e9ae382ba8be0
ご参照願います。
◆青山カレー工房HPは、(「くま辛」パンフレットはこちらからどうぞ)
http://www.studio-02.net/aoyamacurry/
です。
◆今週取材に来てくれたNHKのレポーター山崎さんが支局のブログで「くま辛」を紹介してくれました。
http://www.nhk.or.jp/saitama/ana-blog/120628_02.html
本冊子には、「くま辛」の説明、市長へのQ&Aと参加店の基本情報と地図が掲載されています。「メニューは出ていないの?」というご質問をよく受けるのですが、「くま辛」はメニューが参加店の都合で頻繁に変更になる可能性があるため、常に最新の情報を掲載続けることが難しいのでやむを得ずこの形をとらせていただきました。ですので、メニューが気になる皆さま、恐れ入りますがパンフレット記載の電話番号で直接お店にお問い合わせください。準備が整いましたら、WEBで最新メニュー一覧を掲載できるよう頑張ります!その辺につきましてはどうかご理解のほどよろしくお願いいたします。
現在の配布スポットですが、参加店に加えて市役所および熊谷駅前観光案内所はじめ熊谷市の関係施設で絶賛配布中です。お分かりにならない場合は、写真のパンフと同じデザインののぼりが立っているお店が目印です。「くま辛パンフください!」とお気軽にお声かけください。熊谷駅周辺を歩いていますと、かなりのぼり旗が目立ってきました。私も続々参加店のメニューをいただいてみておりますが、どれもこれも実に個性的に仕上がっておりまして、素晴らしきことこの上なしです。ぜひこのパンフレットを入手して「くま辛」食べ歩きを実践してみてください。
(青山カレー工房のHPトップページ中ほど右手の「くま辛」ポスターバナーから、パンフレットのPDF画面に入れます。URLは下をご参照ください)
メディアでの「くま辛」取り上げも続々です。NHKさんはすでにラジオ第一とFM放送でお取り上げいただき、来週はいよいよテレビ取材が予定されています。放映は12日(木)午前11台の「こんにちは、いっと6けん」の予定です。本日はFM局NACK5さんがご来店され、パーソナリティの三遊亭鬼丸さんが直接取材してくれました。放送予定は14日午後2時台とか。詳しく分り次第お知らせいたします。今後もテレビ、ラジオでいろいろな「くま辛」参加のお店が紹介されると思いますので、お楽しみに。
さて青山カレー工房ですが、「くま辛」メニュー「熊谷大和芋カレー(720円)」大好評です。「クセになる味と触感!」と皆さん大変気に入っていただき嬉しいかぎりです。しかし本日は夕方時点で売切れ。その後来店された方、ごめんなさい。たくさんご用意しているのですが、お持ち帰りニーズも多く、日によっては早めに売り切れてしまうこともありますので、お早めにご来店いただければ幸いです。来週からは食べ歩き用のミニサイズ(450円)もご用意いたします。皆さまのご来店お待ち申し上げます。
◆メディア取材のお申し込みは、熊谷倶楽部くま辛実行委員会広報窓口 �048-580-7440(スタジオ02)または048-598-8091(青山カレー工房)へお願いいたします。
◆くま辛については、
http://blog.goo.ne.jp/ozoz0930/e/18cef0712baa171ac98e9ae382ba8be0
ご参照願います。
◆青山カレー工房HPは、(「くま辛」パンフレットはこちらからどうぞ)
http://www.studio-02.net/aoyamacurry/
です。
◆今週取材に来てくれたNHKのレポーター山崎さんが支局のブログで「くま辛」を紹介してくれました。
http://www.nhk.or.jp/saitama/ana-blog/120628_02.html