
ミスター・ノーバディ
ジャコ・ヴァン・ドルマル監督
仏・独・加・ベルギー共同制作(2009年)
あらすじ 人々が不死となった2092年、記憶をなくした老人ニモ・ノーバディは、死を迎える最後の人類として脚光を浴びる。彼は死を目前にして、様々な人生をたどってきたという信じられない過去を語り出す。
1. 本作に登場する軌道エレベーター
ほんのちょこっとしか登場しませんが、実写映画で軌道エレベーターが描かれるのは極めて珍しく、また映像が非常に綺麗なので取り上げました。本作では火星に人類が進出しており、ここに3本のピラーから成る軌道エレベーターらしきものが建造されています。主人公のニモが火星を訪れ、末端に宇宙船が接舷して、彼は地上との間をエレベーターで行き来します。ちなみにニモは「火星に遺灰を撒く」という恋人との約束を果たすためにやって来ました。
ここで火星の軌道エレベーターの説明を。火星の静止軌道は対地高度約1万3600kmの位置になります。二大衛星の一つ「フォボス」の平均高度は約6000kmと静止軌道より低く、そのままだと軌道が交差して衝突します。ですがこれはSFの常識と言ってよく、火星の軌道エレベーターは大抵フォボスを「避ける」んですね。『楽園の泉』では、地球で建造するためのトライアルとして、まず火星にエレベーターを造るのですが、フォボスが衝突コースに重なる時はピラーを曲げて回避し、さらにこのアクションを観光客向けのショーにしようなんて話が出てきます。本作も静止軌道エレベーターであれば、フォボスを同じように回避していると思われ、さぞかし見ものでしょう。
エレベーター本体が軌道運動をしているか疑問の描写もあるのですが、いずれにしても登場場面は短く、詳細は不明です。単なる作中の小道具に過ぎないので、科学的な検証や図割は愛します。とはいえ本作の映像技術はそれはもう見事で、軌道エレベーターの外観はなかなか美しいです。
2. ストーリーについて
ニモは117歳の余命わずかな老人で、人類が不死(テロメアの減損を食い止める医療技術が確立してるみたい)を手に入れ、生殖不要で恋愛もしなくなった時代の「死んじゃう最後の1人」なんだそうです。実はこのニモ、複数の世界線?で様々な人生をたどってきた記憶をすべて有しているという、魔眼リーディング・シュタイナーの持ち主です。ダース・モールみたいな医師や記者に回想を語る形で、子供のころに「離婚した母親についていったら」「父親についていったら」「恋人と再会できたら」「できなかったら」などと、電話レンジ(仮)もなしに全部体験したと称し、色んなルートの人生を振り返ります。
とにかく場面があっちへ飛ぶわこっちへ移るわ、はたまた『木更津キャッツアイ』みたいにシーンが巻き戻されて別のルートに入るわ、複雑な世界線をたどりながら物語が進みます。話を聞いてる医師や記者も、ニモ自身も何が真相なのか分からず混乱状態で、その混乱を見る側に押し付けてきます。
彼の記憶や体験が多重化しているのには少々カラクリ(ネタバレは避けます)もあるのですが、それも含め本当なのか、単なる妄想か、ボケてるのか、あえて不可解につくってあるので、結局は観客一人ひとりの解釈に委ねられるところです。個人的には「単なる中二病的妄想だろう」という印象です。「どの人生も最高だった」とか言って何でも美化するあたり、「体験したくてもできなかった劣等感の裏返しじゃね?」と見てしまうのは、ひねくれ過ぎでしょうか。
しかし結局は、アトラクタフィールドの収束によって118歳の誕生日に死を迎えることになり、いまわの際に沢山の矛盾した体験談を語って聞かせるという状況にたどりつくようです。中には若くして事故死したり何者かに殺されたりしちゃう(SERNのラウンダーか?)末路もあるんですが、それは彼がダイバージェンス1%の壁を超えてβ世界線に移動できたということなのでしょう。
本作には、成功や失敗、後悔や反省などの思いをかみしめながら、多岐にわたる人生を重ねることで、「自分の意志で人生を選択することがいかに大事か」というテーマ性や「人はなぜ異性を愛するのか」といった問いかけも盛り込んであって、感動的なシーンもあります。ただ最終的にはよくわからないままです。まー、自分をだまし、世界をだまし通した狂気のマッドサイエンティスト・鳳凰院凶真の中二病レベルにはとうてい及ばないな、ということにしておきます。前から思ってたけど「狂気」と「マッド」がかぶってるのはネタなんだろうな。
3. 科学的な作品にあらず
シュタゲネタはこのへんにしておきます。本作をSF扱いする声を散見しましたが、科学的な用語をちりばめているだけで全然SFじゃないです。それが別に悪くはないですけど、科学的な物語やSFとして期待すると、ギアナ高地で会得したという秘奥義スルーショルダー(肩透かし)くらいます。例えば、現在の宇宙論の中には、宇宙が膨張の限界に達すると反転して収縮を始め、「ビッグクランチ」に収束するというものがあり、収縮に転ずると時間の矢が反転するとも言われます。本作では2092年2月9日(!?)に膨張が終わり、そこまで生き延びた人間は時間の反転に伴い若返るんだそうです。
実際にある理論では、宇宙の膨張が止まり時間が反転するのは、エントロピーが極大になり、そこから減少する方向に物理法則が逆転するからで、エントロピーの極大とは、すなわち人間を含めたあらゆる物質が、形状も位相もすべての秩序を失って全部混じり合った存在になる状態です。収縮の瞬間まで人間が生きることはない。このほかにもバタフライ効果(カオス理論)や量子力学、スーパーストリング理論など色々出てきますが、観客を煙に巻く道具に使われるに過ぎません。
4. 全体の感想
最後に、本作には心打たれる部分もメッセージ性もあるし、映像も見ごたえがある。それでも、全体としていい印象を抱けなかった一作でした。観ていて、デヴィット・フィンチャー監督の『セブン』と同じ匂いを感じました。どこが共通するのかというと、観客を掌の上で転がして遊んでいるように思えるんです。このコーナーでは制作者批判は極力避けているのですが、本作は見る側を小馬鹿にしているように感じます。
冒頭に登場する「ハトの迷信行動」も、特に意味はないのに勝手に脳内補完して自己満足し、「自分にはわかる!」と喝采を贈る観客を揶揄しているのではないか。これも私の勝手な脳内補完ですが、こういう手法はすでに出尽くしている感があり、昨今の難解なアニメに慣れた日本の観客などには食傷気味に感じるのではないでしょうか。
今回は少々批判的な結びで筆を置きますが、こう感じるのは私だけなのか? 内容が複雑な上に2時間以上ある非常に長い映画で、ほとんどレンタルもされてませんが、ご覧になった方がいらしたら、意見を聞いてみたいものです。長くなりましたが、ここまで読んでくださり、ありがとうございました。














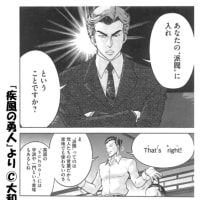






 iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。
iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。


