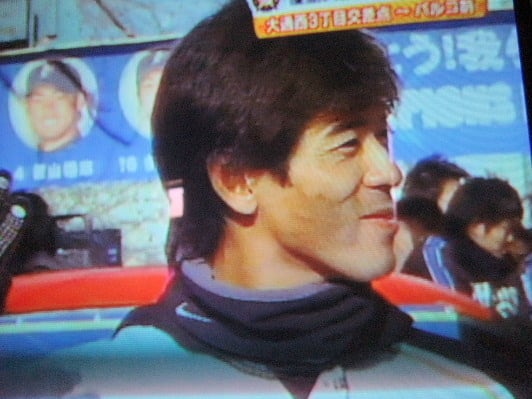家族、お一人、友人同士で函館に来られた方。
そんな方々のために、観光ボランティアガイド「愛」、「一會の会」がご案内しています。
ガイド料は無料で予約不要。ただし、有料施設は参加者の負担です。
コースは期間により次の二つ。
1.元町散策コース(これからの日程は下記のとおり)
約1.2km 所要時間1時間30分から2時間程度
8月21日~10月25日 (金・土・日・祝のみ)10:00~
12月4日~25日(金・土・日・祝日のみ)15:00~
2.開港150周年記念散策コース 約2km
元町散策コース+緑の島入り口まで
8月8日~16日(毎日) 10:00~所要時間2時間程度
※ 問合せ先
(社団)函館国際観光コンベンション協会
http://www.hakodate-kankou.com/
0138-27-3535
土日祝日は元町観光案内所へ
0138ー27-3333
私は歴史などの勉強のために、10日「2コース」に参加しました。
9時50分に元町公園内にある元町観光案内所前に集合。
参加者は11名。こじんまりとして説明がよく聞こえる人数。
先ず、ガイドさんのご挨拶とコース説明があって、いよいよ出発。

最初は、旧北海道庁渡島(おしま)支庁庁舎。
明治42年の木造建築で広さは約964㎡。
巨大なエンタシス柱がダイナミックで美しい。
現在は1階が観光案内所、2階が写真歴史館で、ペリー来航時に撮影された日本一古い松前藩士の写真(レプリカ)などが展示。
建物が老朽化し危険となったとき、札幌郊外の北海道開拓の村への移転話もあったが、市民運動で現在地保存となったのは嬉しかった。

旧渡島支庁庁舎向かいにあるこの建物は「旧開拓使函館支庁レンガ造書庫」。
明治10年代の建築で瓦葺き2階建。
使われたレンガは、郊外の茂辺地(もへじ)で作られ、明治7年、8年、
9年函館製の刻印が一枚一枚に見える。
、

元町公園から市街地を眺望。
函館の歴史説明があった。
幕末の箱館奉行所はここにあったが、開港にともない防御上の理由から五稜郭へ移転した。

旧函館区公会堂へ移動。
明治40年の大火で函館区の三分の一が焼失し、区民が集まる施設も焼け、再建を図った。
そして、明治洋風建築を代表する建物(コロニアル・スタイル)が完成したのは明治43年。
明治天皇のご宿泊所としても使われた。

教会通りの八幡坂へ。
障害物がなく真っ直ぐ下に港を望め、また旧青函連絡船・摩周丸も見えることから、テレビCMでお馴染みの坂。
代表的なCMは「チャーミーグリーン」。
赤いチョッキを着た老夫婦がダンスをしながらの場面は美しかった。
坂の名の由来は、幕末にこの坂の上に八幡様が祭られていたからである。
坂を上り切ったところに、北島三郎さんの出身校・函館西高校がある。
次は、函館の顔と呼ばれている「ハリストス正教会」へ。

ハリストスとは、ロシア語でキリストを意味する。
教会は、この地に安政6(1859)年に建てられたロシア領事館の付属聖堂として同時に建設されたが、明治40年の大火で焼失。
大正5年にレンガで再建したのが現教会。
ロシア風ビザンチン様式の本堂丸天井に特徴があり、美しい姿を誇っている。。

そして隣に位置するのが、日本聖公会函館聖ヨハネ教会。
イギリスの聖公会の牧師が来函して伝道したのに始まる。
大火で二度焼失。
現教会は昭和54年の完成で、教会通りでは一番新しい存在だ。
教育や福祉活動に大きな功績を残した。

風見鶏のある元町カトリック教会は、明治8年に初代教会を建設。
明治40年に木造であった聖堂が焼けたため、ゴシック式のレンガ造りの聖堂に変わった。
ところが、大正10年の大火でこの聖堂も焼失。
同年レンガ部分を修復。増築した鐘楼部分だけは鉄筋コンクリートで造った。
完成後、ローマ法王・ベネディクト15世から豪華な祭壇が寄進された。

幅20間(約36m)の二十間坂を見て寺院へ。
東本願寺函館別院の境内へ入った。
1710年に近郊の現木古内町 から基坂付近に移ってきた。
1747年、現弥生小学校付近に移り、明治12(1879)年の大火で焼失。
現在地に移転新築したが、これも明治40年の大火で焼失。
再建は、国内最初の鉄筋コンクリート造とし、明治45年に着工、大正4年に完成した。
本堂は間口約33m、奥行約35mと大きなもの。
工事期間中は、「大屋根が、この構造で支えられるのか?」の疑問に応えるるため、梁に芸者を上げ手踊りさせたという。
瓦の美しさは見事である。

このように狭い地域に世界の宗教が集まる元町。
この存在は国内はもとより、世界でも珍しい町並みと評価されている。
元町コースの最後の見学施設は、旧イギリス領事館(現・開港記念館)。
安政6(1859)年、初代領事・ホジソンは、現弥生小学校にあった称名寺の一部屋を借りて執務を開始。
元治元(1864)年、ハリストス正教会隣に移ったが、慶応2(1866)年、ロシア病院からの出火で焼失。
旧函館病院敷地へ移ったが、明治12年の大火でまたもや焼失。
現在地へ移ったものの、明治40年の大火でまたまた焼失。
現在の建物は明治42年に完成したもの。
昭和9年、領事館は閉鎖、市が買い取り、市立病院の看護婦寮やカルテ保管庫として利用された経緯がある。

元町散策コースを終え、函館開港150周年記念散策コースがスタート。会場の緑の島へと足を運んだ。
最初はアメリカ合衆国・ペリー提督像。
この領事館向かい、基坂を挟んだ旧市立函館病院の敷地に北を向いて立っている。
制作者は、函館出身でローマ在住の彫刻家・小寺真知子さん。
五稜郭タワーにある土方歳三像も手がけた。
繊細な技法が見る者を唸らせる。

中華会館(華僑会館)
基坂を下り、バス通りから左に目をやると見える。
華僑の集会所は、最初同徳堂といったが、明治40年の大火で焼失。
二代目のこの総煉瓦造の建物は、明治43年に完成した。
釘を一本も使わない純中国(清朝)様式としては、日本に現存する唯一の貴重な建物である。
函館から中国への海産物貿易の盛んな頃に、在函華僑が信仰する三国時代(220年~280年)の武将・関帝(商売と学問の神様)を祀る聖所として建設した。
中国から大工・彫刻師・漆工らを招き、煉瓦等の資材も中国から取り寄せ、約3年の工期と巨費を投じた。
内部は朱色の漆塗り、金色の関帝壇を中心として周囲に小部屋を配し、装飾、調度品は壮麗である。
会館は華僑の公儀場所、祭事と交際の場所として使われてきた。
中国領事館が置かれた時もあった。
戦後、日常的にはほとんど使われていないが、例外的に国慶節(10月1日)、関帝祭(5月13日)の祝宴、結婚披露宴、中国からの賓客の歓迎の場として使われている。

コースの最終地・緑の島へ到着したのは丁度正午。
予定どおりであった。
ガイドさんからお別れの挨拶。
{楽しかったですよ。有難うございました。」と、参加者の声。
「またのお越しをお待ちしております」。
参加者は緑の島へと消えて行った。

感じたこと。
① 何と多い函館の大火。
それでも、くじけず復興へ立ち上がった人々。
強い意志があったればこそだと思いました。
②函館検定を受検するにあたり、歴史テキスト本を多数読破しましたが、ガイドさんの説明に、新たな知識がたくさん吸収されました。
また、機会を見て参加し、郷土函館の歴史・文化を身につけたいと思いました。
気配り、目配りして下さったガイドさん、ご苦労様でした。 
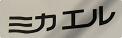


![]()