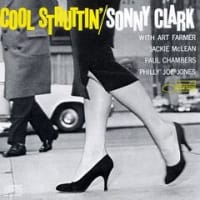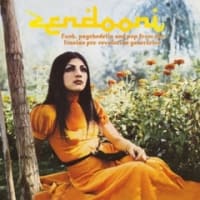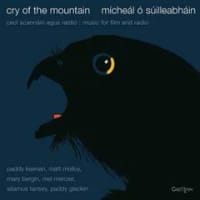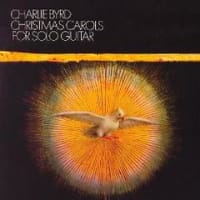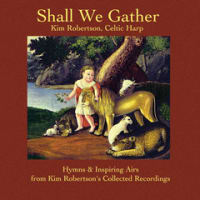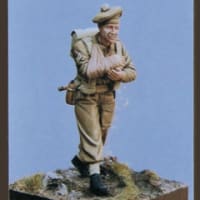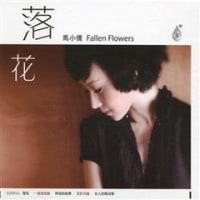”ちょんちょんキジムナー”by 照屋政雄
沖縄方面のミュージシャンで私が一番興味あるのが、実は照屋政雄氏なのであって。あれは普天間かおりのヴァージョンだっけか、政雄氏の代表作である”チョンチョン・キジムナー”を聴いて、何だこりゃ、こんなひょうきんな歌を作ったのはなにものだ?と慌てて氏の経歴を調べたりCDを買い込んだりしたものだ。
キジムナーとはもちろん、あの沖縄の愛すべき精霊なのであるが、氏は彼ならではの愛嬌たっぷりの手管で、現実と非現実のあわいに住む伝説の生き物を、実に生き生きと親愛の情を込めて描き出していた。
それにしても照屋林山、登川誠仁両氏をはじめとして、錚々たる師匠連に沖縄の伝承音楽を学び、言ってみればかの世界の”王道”を歩いてきたかに見える正雄氏、にもかかわらずさっぱり偉そうではない、むしろ素っ頓狂なキャラを貫いているのが嬉しいではないか。
中ジャケでも複数の人が政雄氏の日常のトボケた失敗談など紹介しているが、その楽しさ、暖かさがそのまま、氏の音楽の魅力と直結している。
ここに挙げたアルバムは沖縄のローカル・レーベル、”んなるふぉん”から2002年に発売になった、おそらくは氏の初のソロアルバムなのだが、ここには政雄氏の音楽の、気のおけない楽しさが頭から尻尾までギッシリと詰まっている。
沖縄と言う土地の日常の、なにげない生活の喜怒哀楽や伝承を歌う、その狭間々々に、聴く者の脇の下にもぐりこんでコチョコチョくすぐり倒すような飄々とした風刺と諧謔のタマシイが潜んでいる。その標的となるのはオカミの作ったなんの役に立つやら分からない道路から、”分かっちゃいるけどやめられない”と自堕落な生活を続ける名もない庶民の日常まで、分け隔てはない。
沖縄の伝統音楽の素養はもとより身についている政雄氏だが、一方、沖縄漫才等の方にも手を染めていて、そのあたりから身に付けたのだろう、”寄席芸の肌触り”が、彼の歌声、節回しから良い具合でこぼれ落ち、氏の音楽に更なる奥行きを与えている。彼の歌の向こうに、裏表から見た沖縄の庶民史が透けて見えてくるような気がしてくるのだ。
ギターやベース等の軽い伴奏が付いている曲もあるが、多くは政雄氏の三線の弾き語りで、このパフォーマンスにおいても、鋭さよりはどこかコロコロした鈍角の愛嬌(?)を滲ませる政雄氏である。
コミカルでファンキーな自作曲の間に伝統曲を挟みつつ進行したアルバムは、かっての紅楼の巷におけるドタバタ騒ぎを活写した愉快な”吉原漫歩”で幕を閉じる。こいつがまた、楽しい曲である。
で、聞き終えると同時にこちらは、照屋政雄氏の世界にますます惹かれ始めていて、「早く次のアルバム、出ないかなあ」などと呟いてしまっている次第だ。