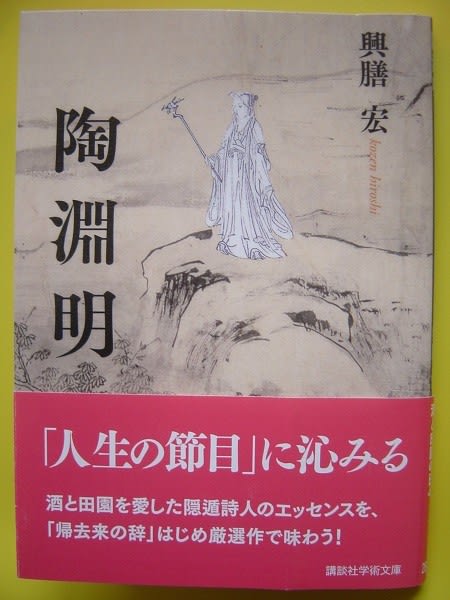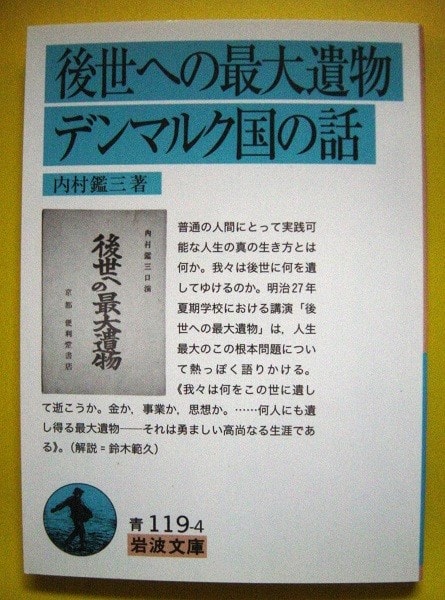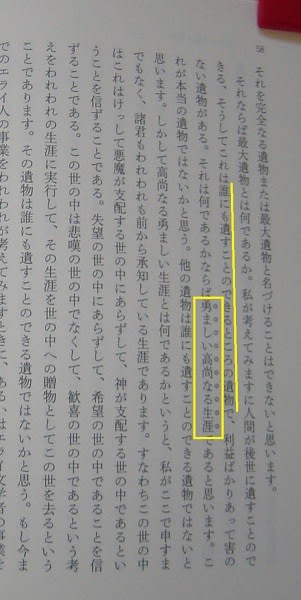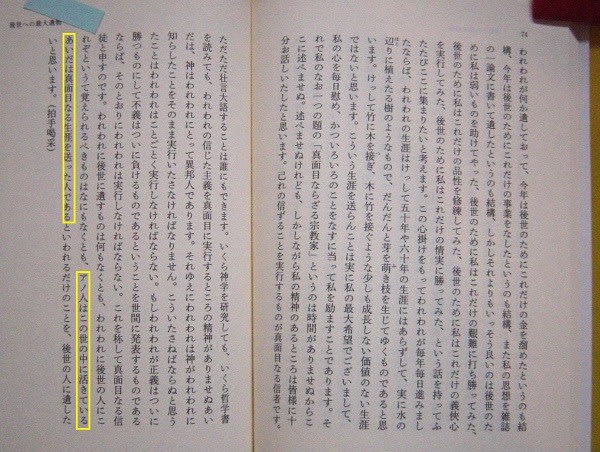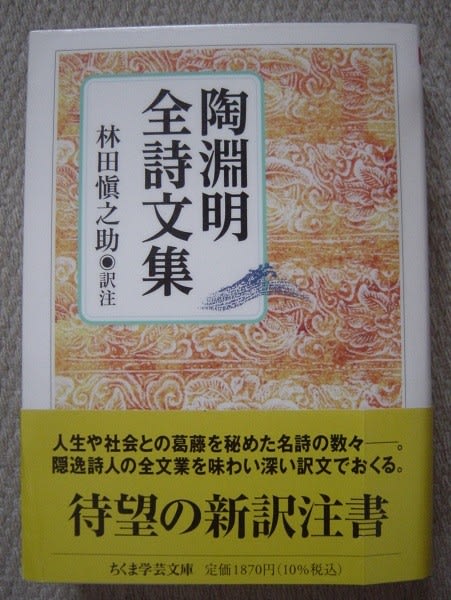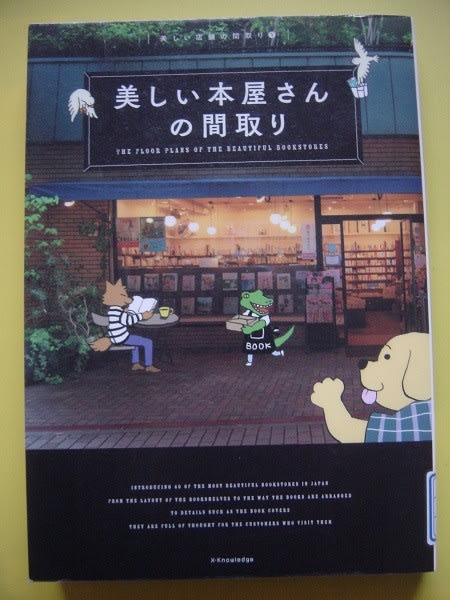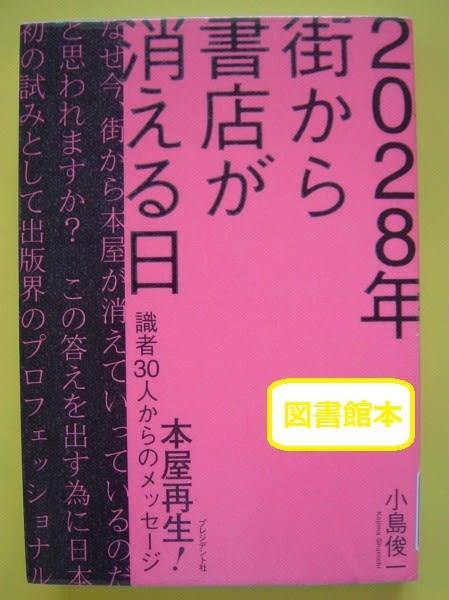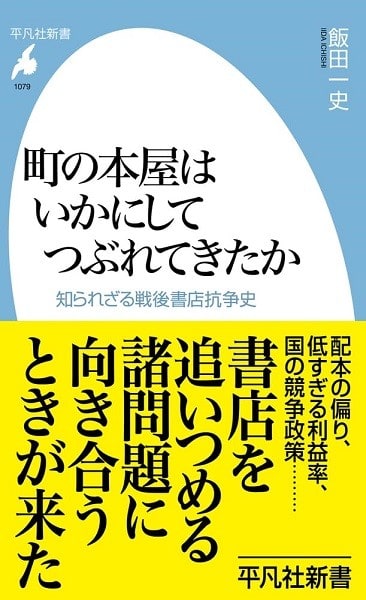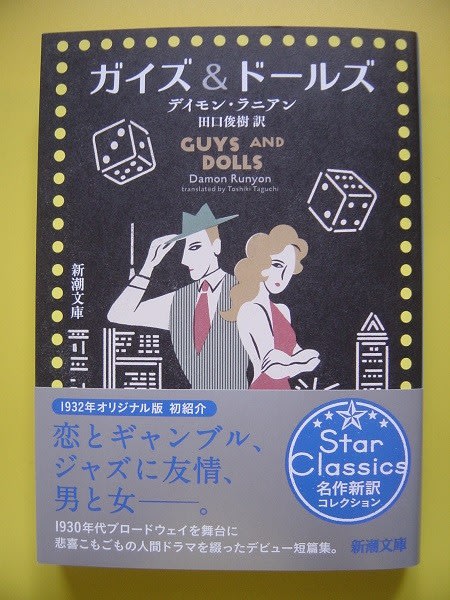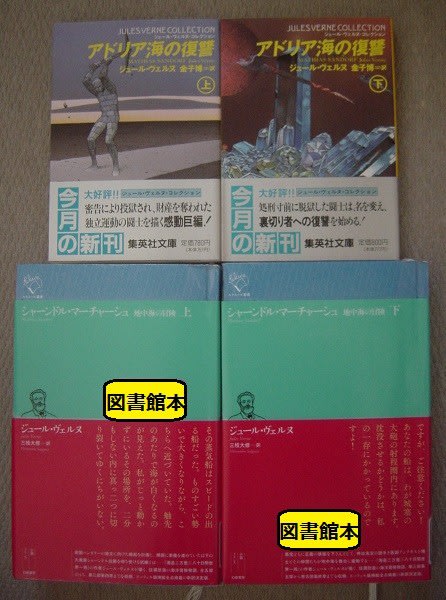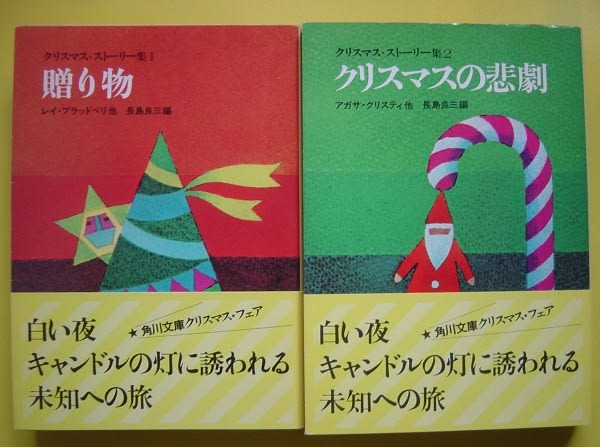古典から始める レフティやすおの楽しい読書(まぐまぐ!)
【最新号・告知】【別冊 編集後記】
2025(令和7)年7月31日号(vol.18 no.13/No.393)
「新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2025から(2)集英社文庫・
『存在の耐えられない軽さ』ミラン・クンデラ~一回限りの人生~」

------------------------------------------------------------------
◇◆◇◆ 古典から始める レフティやすおの楽しい読書 ◆◇◆◇
------------------------------------------------------------------
2025(令和7)年7月31日号(vol.18 no.13/No.393)
「新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2025から(2)集英社文庫・
『存在の耐えられない軽さ』ミラン・クンデラ~一回限りの人生~」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年も毎夏恒例の新潮・角川・集英社の
<夏の文庫>フェア2025から――。
今年も、一号ごと三回続けて、一社に一冊を選んで紹介します。
今年のテーマは、大阪関西万博の年ということで、
「大阪」もしくは、万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」
ということで、大阪ものの小説や「いのち」に絡んだ作品に
取り組んでみましょう。
二本目は、集英社文庫から、一回限りの人生についての物語、
ミラン・クンデラさんの作品『存在の耐えられない軽さ』を。
角川文庫夏フェア2025 | カドブン
https://kadobun.jp/special/natsu-fair/
ナツイチ2025 広くて深い、言葉の海へ| web 集英社文庫
https://bunko.shueisha.co.jp/natsuichi/
よまにゃチャンネル - ナツイチ2025 | 集英社文庫
https://bunko.shueisha.co.jp/natsuichi/yomanyachannel/
新潮文庫の100冊 2025
https://100satsu.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆ 2025年テーマ:<大阪関西万博2025> ◆
新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2025から(2)
~一回限りの人生~
集英社文庫―『存在の耐えられない軽さ』ミラン・クンデラ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●集英社文庫ナツイチ2025 広くて深い、言葉の海へ
ナツイチ2025
https://bunko.shueisha.co.jp/natsuichi/
2025年テーマ
言葉は海にそっくりだ。
水平線のようにつづく世界。
深海より底のしれない一行。
ビーチみたいにしずかな時間。
とおくまで泳ぐのも、じっくり潜るのもいい。
さあ、よまにゃ。

(対象書目 86点)
すべてを書き写すスペースはもったいないので、
気になる作品、既読作品をピックアップしてみましょう。
・映像化する本 よまにゃ (5)
水滸伝 一 曙光の章 北方 謙三
・心ふるえる本 よまにゃ (21)
塞王の楯 〈上〉〈下〉今村 翔吾
チンギス紀 一 火眼 北方 謙三
幻夜 東野 圭吾
N 道尾 秀介
・手に汗にぎる本 よまにゃ (26)
帰去来 大沢 在昌
真夜中のマリオネット 知念 実希人
布武の果て 上田 秀人
ハヤブサ消防団 池井戸 潤
・心ときめく本 よまにゃ (11)
午前0時の忘れもの 赤川 次郎
愛じゃないならこれは何 斜線堂 有紀
・じっくり浸る本 よまにゃ (23)
地獄変 芥川 龍之介
存在の耐えられない軽さ ミラン・クンデラ
星の王子さま サンテグジュペリ
人間失格 太宰 治
こころ 夏目 漱石
うまれることば、しぬことば 酒井 順子
――以上、やっぱり古典といいますか名作と呼ばれるもの以外は、
ほとんど読んでいません。
●<じっくり浸る本 よまにゃ> から『存在の耐えられない軽さ』
『存在の耐えられない軽さ』ミラン・クンデラ/ 千野 栄一/訳
集英社文庫 1998/11/20


《女たらしの外科医トマーシュと純朴なテレザは愛し合うが、
「プラハの春」へのソ連軍事介入に運命を翻弄される。
チェコの悲劇を背景にした純愛大河小説》
とあります。
今年のテーマから「いのち」をの本としてこれを取り上げてみました。
以前私は、文学の王道は恋愛小説ではないか、というお話をしたか、
と思います。
この本を選んだ理由の一つでもあります。
Amazonには、
《苦悩する恋人たち。不思議な三角関係。
男は、ひとりの男に特別な感情を抱いた。鮮烈でエロチック…。
プラハの悲劇的政治状況下での男と女のかぎりない愛と転落を、
美しく描きだす哲学的恋愛小説。
フィリップ・カウフマン監督、主人公トマシュに
ダニエル・デイ=ルイス、テレーザにジュリエット・ビノシュを迎え、
1988年に映画公開された原作小説。》
とありました。
で、まずは全巻読み終えての感想です。
読み終えての結論的なものとも言えます。
●感動的なラスト
いきなり、結末までバラしてしまうのはどうかという気もしますが、
推理小説のようなエンタメ作品ではないので、
感動した部分を素直に書いてしまってもいいのではないか、と思います。
冒頭、ニーチェの永劫回帰という言葉が出てきます。
これは結構キツいぞ、と思いながら読み続けますと、
著者と思われる“私”が登場してあれこれとものをいいます。
これが哲学的な文章です。
最初は少し戸惑いましたが、とにかく最後まで読み切ってしまおう。
評価はそれから、ということで。
で、色々と難しい文章もありますが、最終的な着地点というのが、
主人公たち二人のカップルが、女性の飼い犬と二人と一匹で、
牧歌的な田舎で暮らし、土地の人ともお付き合いをします。
しかし、二人の愛犬カレーニンが癌におかされ、
日々衰えながらもけなげに生きていき、最後には安楽死――。
この二人と一匹の悲しいけれど、美しいラストが、感動的です。
それまでの難しい政治的な論理や人の心の愛情の問題や、
何やかやの展開もすべて流し去って、
美しい思い出だけが残るラストになっています。
●登場人物とストーリー
では、簡単にストーリーを紹介しましょう。
登場人物は、登場人物表にもありますように、主な登場人物は、
外科医のトマーシュ、その恋人のテレザ、
トマーシュの愛人のサビナ、サビナの愛人のフランツ、
フランツの前妻との息子シモン、そしてテレザの愛犬カレーニン。
次に、目次 です。
第I部 軽さと重さ
第II部 心と体
第III部 理解されなかったことば
第IV部 心と体
第V部 軽さと重さ
第VI部 大行進
第VII部 カレーニンの微笑
「第I部 軽さと重さ」は、プラハでのトマーシュとテレザの関係。
トマーシュは優秀な外科医で、女たらしで、
愛人を次々ととっかえひっかえしています。
一方で、テレザがいないと生きていけないというのです。
《 トマーシュは、女と愛し合うのと、いっしょに眠るのとは、
まったく違う二つの情熱であるばかりか、対立するとさえいえるもの
だといっていた。愛というものは愛し合うことを望むのではなく
(この望みは数えきれないほどの多数の女と関係する)、いっしょに
眠ることを望むである(この望みはただ一人の女と関係する)。》p.22
ソ連がチェコに侵攻したのち、二人と一匹はチューリッヒへ移ります。
《(略)かたつむりが自分の家を運ぶように、自分の生き方を運んで
いると彼は幸福そうにつぶやいた。テレザとサビナは彼の生活の
二つの極、遠く離れた極、和解しがたく、しかもともに美しい極を
代表していた。》pp.39-40
しかし、この生活は長くは続きません。
テレザは、ソ連の侵攻に抵抗する人々の姿を写真に撮ったものを、
西側の新聞や雑誌に売り込みに行きますが、相手にされません。
テレザは、祖国への思いからプラハに帰ってしまいます。
当座、独り身の「軽さ」を覚えたトマーシュでした。
サビナと会うときも嘘の出張話を持ち出す必要もないのですから。
ところが、半年もするとテレザのいない生活には耐えられず、
彼もプラハに帰って行きます。
「第II部 心と体」は、テレザとトマーシュとの出会いと、
テレザのそれまでのお話。
トマーシュは二人の出会いには六つのありえない偶然があった、と。
テレザは、トマーシュの《一夫多妻生活の第二の自己になる》ことを
意識して、トマーシュの愛人であるサビナに接近し、カメラに撮ります。
「第III部 理解されなかったことば」は、サビナと愛人のフランツとの
関係です。
サビナにとって女であることは自分が選んだ運命ではなかったのです。
フランツにとっては妻マリー=クロードのなかの女を大事にしなければ
ならないと考えていました。
《 人生のドラマというものはいつも重さというメタファーで表現
できる。われわれはある人間が重荷を負わされたという。その人間は
その重荷に耐えられずにその下敷きになるか、それと争い、
敗(ま)けるか勝つかする。しかしいったい何がサビナに起こったので
あろうか? 何も。(略)彼女のドラマは重さのドラマではなく、
軽さのであった。サビナに落ちてきたのは重荷ではなく、存在の
耐えられない軽さであった。》p.156
「第IV部 心と体」は、テレザとトマーシュの生活です。
テレザは、トマーシュの髪に女のデルタの臭いを嗅ぎとります。
バーで働くテレザはある時、男の誘いに乗り、浮気をします。
男の部屋でソフォクレースの『オイディプース』の翻訳本を見つけます。
テレザはトマーシュに復讐しようというわけではなかったのです。
「第V部 軽さと重さ」で、トマーシュは『オイディプース』にヒントを
得て書いた文章を週刊新聞に送ると、編集部から呼ばれ掲載されます。
ロシア人の軍隊による占領を招いた共産主義者たちは、公然と自分たちの
目を刺すべきだ、というトマーシュの意見に対して圧力をかけてきます。
しかし「あれ以上大事なものはありません」と拒否したトマーシュは、
外科医の職を奪われ、地位の低い地方病院の医者に、さらに窓掃除人に。
そこでも彼の名は知られていて、反体制派の人物が接触してきます。
そこにトマーシュの息子も。前妻は共産主義だが、息子は違いました。
サビナはプラハは嫌な町になったといい、トマーシュに田舎へ引っ越そう
と話します。彼にとってサビナは『饗宴』でいう片割れなのでしょうか?
《 トマーシュはプラトンの有名なシンポジオンという神話を思い出し
た。人びとは最初、男女両性具有者であったが、神がそれを二等分
したので、その半身はそれ以来世の中をさまよい、お互いを探し求め
ている。愛とは我々自身の失われた半身への憧れである。》p.304
この後、アメリカへ移民したサビナの話や、政治的な話が出てきます。
●『存在の耐えられない軽さ』とは?
ストーリーを追うのはこのへんにして、私なりの感想を書いていこうか
と思います。
男女の愛と性をめぐるお話と、チェコの民主化を阻むソ連軍や
それに迎合する共産主義者によって、祖国を守ろうとする人々や
政治犯とされる人々が追い込まれていく政治的なお話が展開されます。
人間にとって大事なことは、男女の愛(と性)の生活なのか、政治的に
自由な生活なのか、<存在の耐えられない軽さ>とは何なのか。
正直なところ、よくわかりません。
「第VI部 大行進」で、
《(略)テレザとトマーシュは重さの印の下で死んだ。彼女(引用者注
・サビナ)は軽さの印の下で死にたいのである。彼女は空気よりも
軽くなる。これはパルメニデースによれば、否定的なものから
肯定的なものへの変化である。》p.344
とあります。
確かに、トマーシュは発言を撤回させず、社会から抹殺されていきます。
トマーシュは銃殺され、最後にはテレザも死んでしまったようです。
それは思想的な理由で殺される重い死だったようですし、
それに比べれば、アメリカに逃れた? サビナの最期はまた違ったものに
できるのでしょう。
●「第VII部 カレーニンの微笑」
しかし、先にも書きましたように、
そのラストは非常に感動的なものでした。
その場面での存在のなかには、男女以外に愛犬がいました。
《(略)カレーニンとテレザの愛は、彼女とトマーシュとの間のそれ
よりもよいという考えである。よりよいのであって、より大きいと
いうのではない。(略)》p.372
《 犬への愛は無欲のものである。テレザはカレーニンに、何も要求
しない。愛すらも求めない。私を愛している? 誰か私より好き
だった? 私が彼を愛しているより、彼は私のことを好きかしら?
というような二人の人間を苦しめる問いを発することはなかった。
愛を測り、調べ、明らかにし、救うために発する問いはすべて、愛を
急に終わらせるかもしれない。(略)》p.373
《(略)テレザはカレーニンをあるがままに受け入れ、自分の思う
ように変えることを望まず、あらかじめ、カレーニンの犬の世界に
同意し、それを奪おうとはせず、カレーニンの秘め事にも
嫉妬しなかった。犬を(男が自分の妻を作り直そう、女が自分の
亭主を作り直そうとするように)作り直そうとはしないで、ただ
理解し合っていっしょに暮せるような基本的な言語を学べるように
と育てた。/ さらにいえば、犬への愛はだれかがテレザに強いた
のではなく、自由意志に基づくものである。(略)》p.373
《(略)人間の時間は輪となってめぐることはなく、直線に沿って
前へと走るのである。これが人間が幸福になれない理由である。
幸福は繰り返しへの憧れなのだからである。/ そう、幸福とは
繰り返しへの憧れであると、テレザは独りごとをいう。》p.374
カレーニンとの暮らしは、基本的に毎朝、同じことの繰り返しでした。
そして、時が来てカレーニンにお迎えが来て、安楽死させた二人は
決めていたリンゴの木の間に埋葬します。
考えてみれば、私たちの暮らしというものも、基本、同じことを繰り返し
続けられるうちが花で、しあわせな日々といえるのかも知れません。
トマーシュは、外科医を辞めさせられ、愛人との生活も失われ、
テレザとカレーニンとの田舎での暮らしとなりました。
時には、トマーシュのために着飾ったテレザを見た若い男と農場長たちと
ホテルのバーのダンスホールに出かけ、楽しい時間をすごしました。
テレザが真に彼の失われた片割れであったかどうかはわかりません。
しかし、最終的に彼らが選んだのは、二人(と一匹)の生活でした。
《(略)人生はたった一度かぎりだ。それゆえわれわれのどの決断が
正しかったか、どの決断が誤っていたかを確認することはけっして
できない。所与の状況でたったの一度しか決断できない。いろいろ
な決断を比較するための、第二、第三、第四の人生は与えられて
いないのである。/ 歴史も、個人の人生と似たようなものである。
チェコ人の歴史はたった一度しかない。トマーシュの人生と同じよう
にある日終わりを告げ、二度繰り返すことはできないであろう。》
p.284(「第V部 軽さと重さ」)
・・・
色々と考えさせられる小説でした。
難しいといえば難しいですし、こういう展開の仕方はストーリーとして
どうなんだ? と問われたら、こういうのもありなんでしょうね、
としかいえません。
とにかく、一度は読んでおきたい小説です。
みなさまもどうぞ、機会があれば!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本誌では、「新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2025から(2)集英社文庫・『存在の耐えられない軽さ』ミラン・クンデラ~一回限りの人生~」と題して、今回も全文転載紹介です。
本文中にも書きましたように、人生というのは一回ポッキリのもので、やり直しはできません。
セカンド・チャンスはありません。
それだけにその時その時の決断というものが重要になって来ます。
しかし、考えすぎては、チャンスを逃がすことにもなりかねません。
難しいものです、何十年生きてきても。
でも、それだからこそ「人生はおもしろい」とも言えるのかも知れません。
・・・
*本誌のお申し込み等は、下↓から
(まぐまぐ!)『(古典から始める)レフティやすおの楽しい読書』
『レフティやすおのお茶でっせ』
〈メルマガ「楽しい読書」〉カテゴリ
--
『レフティやすおのお茶でっせ』より転載
" target="_blank"><夏の文庫>フェア2025から(2)集英社文庫『存在の耐えられない軽さ』ミラン・クンデラ-楽しい読書393号
--
【最新号・告知】【別冊 編集後記】
2025(令和7)年7月31日号(vol.18 no.13/No.393)
「新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2025から(2)集英社文庫・
『存在の耐えられない軽さ』ミラン・クンデラ~一回限りの人生~」

------------------------------------------------------------------
◇◆◇◆ 古典から始める レフティやすおの楽しい読書 ◆◇◆◇
------------------------------------------------------------------
2025(令和7)年7月31日号(vol.18 no.13/No.393)
「新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2025から(2)集英社文庫・
『存在の耐えられない軽さ』ミラン・クンデラ~一回限りの人生~」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年も毎夏恒例の新潮・角川・集英社の
<夏の文庫>フェア2025から――。
今年も、一号ごと三回続けて、一社に一冊を選んで紹介します。
今年のテーマは、大阪関西万博の年ということで、
「大阪」もしくは、万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」
ということで、大阪ものの小説や「いのち」に絡んだ作品に
取り組んでみましょう。
二本目は、集英社文庫から、一回限りの人生についての物語、
ミラン・クンデラさんの作品『存在の耐えられない軽さ』を。
角川文庫夏フェア2025 | カドブン
https://kadobun.jp/special/natsu-fair/
ナツイチ2025 広くて深い、言葉の海へ| web 集英社文庫
https://bunko.shueisha.co.jp/natsuichi/
よまにゃチャンネル - ナツイチ2025 | 集英社文庫
https://bunko.shueisha.co.jp/natsuichi/yomanyachannel/
新潮文庫の100冊 2025
https://100satsu.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆ 2025年テーマ:<大阪関西万博2025> ◆
新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2025から(2)
~一回限りの人生~
集英社文庫―『存在の耐えられない軽さ』ミラン・クンデラ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●集英社文庫ナツイチ2025 広くて深い、言葉の海へ
ナツイチ2025
https://bunko.shueisha.co.jp/natsuichi/
2025年テーマ
言葉は海にそっくりだ。
水平線のようにつづく世界。
深海より底のしれない一行。
ビーチみたいにしずかな時間。
とおくまで泳ぐのも、じっくり潜るのもいい。
さあ、よまにゃ。

(対象書目 86点)
すべてを書き写すスペースはもったいないので、
気になる作品、既読作品をピックアップしてみましょう。
・映像化する本 よまにゃ (5)
水滸伝 一 曙光の章 北方 謙三
・心ふるえる本 よまにゃ (21)
塞王の楯 〈上〉〈下〉今村 翔吾
チンギス紀 一 火眼 北方 謙三
幻夜 東野 圭吾
N 道尾 秀介
・手に汗にぎる本 よまにゃ (26)
帰去来 大沢 在昌
真夜中のマリオネット 知念 実希人
布武の果て 上田 秀人
ハヤブサ消防団 池井戸 潤
・心ときめく本 よまにゃ (11)
午前0時の忘れもの 赤川 次郎
愛じゃないならこれは何 斜線堂 有紀
・じっくり浸る本 よまにゃ (23)
地獄変 芥川 龍之介
存在の耐えられない軽さ ミラン・クンデラ
星の王子さま サンテグジュペリ
人間失格 太宰 治
こころ 夏目 漱石
うまれることば、しぬことば 酒井 順子
――以上、やっぱり古典といいますか名作と呼ばれるもの以外は、
ほとんど読んでいません。
●<じっくり浸る本 よまにゃ> から『存在の耐えられない軽さ』
『存在の耐えられない軽さ』ミラン・クンデラ/ 千野 栄一/訳
集英社文庫 1998/11/20


《女たらしの外科医トマーシュと純朴なテレザは愛し合うが、
「プラハの春」へのソ連軍事介入に運命を翻弄される。
チェコの悲劇を背景にした純愛大河小説》
とあります。
今年のテーマから「いのち」をの本としてこれを取り上げてみました。
以前私は、文学の王道は恋愛小説ではないか、というお話をしたか、
と思います。
この本を選んだ理由の一つでもあります。
Amazonには、
《苦悩する恋人たち。不思議な三角関係。
男は、ひとりの男に特別な感情を抱いた。鮮烈でエロチック…。
プラハの悲劇的政治状況下での男と女のかぎりない愛と転落を、
美しく描きだす哲学的恋愛小説。
フィリップ・カウフマン監督、主人公トマシュに
ダニエル・デイ=ルイス、テレーザにジュリエット・ビノシュを迎え、
1988年に映画公開された原作小説。》
とありました。
で、まずは全巻読み終えての感想です。
読み終えての結論的なものとも言えます。
●感動的なラスト
いきなり、結末までバラしてしまうのはどうかという気もしますが、
推理小説のようなエンタメ作品ではないので、
感動した部分を素直に書いてしまってもいいのではないか、と思います。
冒頭、ニーチェの永劫回帰という言葉が出てきます。
これは結構キツいぞ、と思いながら読み続けますと、
著者と思われる“私”が登場してあれこれとものをいいます。
これが哲学的な文章です。
最初は少し戸惑いましたが、とにかく最後まで読み切ってしまおう。
評価はそれから、ということで。
で、色々と難しい文章もありますが、最終的な着地点というのが、
主人公たち二人のカップルが、女性の飼い犬と二人と一匹で、
牧歌的な田舎で暮らし、土地の人ともお付き合いをします。
しかし、二人の愛犬カレーニンが癌におかされ、
日々衰えながらもけなげに生きていき、最後には安楽死――。
この二人と一匹の悲しいけれど、美しいラストが、感動的です。
それまでの難しい政治的な論理や人の心の愛情の問題や、
何やかやの展開もすべて流し去って、
美しい思い出だけが残るラストになっています。
●登場人物とストーリー
では、簡単にストーリーを紹介しましょう。
登場人物は、登場人物表にもありますように、主な登場人物は、
外科医のトマーシュ、その恋人のテレザ、
トマーシュの愛人のサビナ、サビナの愛人のフランツ、
フランツの前妻との息子シモン、そしてテレザの愛犬カレーニン。
次に、目次 です。
第I部 軽さと重さ
第II部 心と体
第III部 理解されなかったことば
第IV部 心と体
第V部 軽さと重さ
第VI部 大行進
第VII部 カレーニンの微笑
「第I部 軽さと重さ」は、プラハでのトマーシュとテレザの関係。
トマーシュは優秀な外科医で、女たらしで、
愛人を次々ととっかえひっかえしています。
一方で、テレザがいないと生きていけないというのです。
《 トマーシュは、女と愛し合うのと、いっしょに眠るのとは、
まったく違う二つの情熱であるばかりか、対立するとさえいえるもの
だといっていた。愛というものは愛し合うことを望むのではなく
(この望みは数えきれないほどの多数の女と関係する)、いっしょに
眠ることを望むである(この望みはただ一人の女と関係する)。》p.22
ソ連がチェコに侵攻したのち、二人と一匹はチューリッヒへ移ります。
《(略)かたつむりが自分の家を運ぶように、自分の生き方を運んで
いると彼は幸福そうにつぶやいた。テレザとサビナは彼の生活の
二つの極、遠く離れた極、和解しがたく、しかもともに美しい極を
代表していた。》pp.39-40
しかし、この生活は長くは続きません。
テレザは、ソ連の侵攻に抵抗する人々の姿を写真に撮ったものを、
西側の新聞や雑誌に売り込みに行きますが、相手にされません。
テレザは、祖国への思いからプラハに帰ってしまいます。
当座、独り身の「軽さ」を覚えたトマーシュでした。
サビナと会うときも嘘の出張話を持ち出す必要もないのですから。
ところが、半年もするとテレザのいない生活には耐えられず、
彼もプラハに帰って行きます。
「第II部 心と体」は、テレザとトマーシュとの出会いと、
テレザのそれまでのお話。
トマーシュは二人の出会いには六つのありえない偶然があった、と。
テレザは、トマーシュの《一夫多妻生活の第二の自己になる》ことを
意識して、トマーシュの愛人であるサビナに接近し、カメラに撮ります。
「第III部 理解されなかったことば」は、サビナと愛人のフランツとの
関係です。
サビナにとって女であることは自分が選んだ運命ではなかったのです。
フランツにとっては妻マリー=クロードのなかの女を大事にしなければ
ならないと考えていました。
《 人生のドラマというものはいつも重さというメタファーで表現
できる。われわれはある人間が重荷を負わされたという。その人間は
その重荷に耐えられずにその下敷きになるか、それと争い、
敗(ま)けるか勝つかする。しかしいったい何がサビナに起こったので
あろうか? 何も。(略)彼女のドラマは重さのドラマではなく、
軽さのであった。サビナに落ちてきたのは重荷ではなく、存在の
耐えられない軽さであった。》p.156
「第IV部 心と体」は、テレザとトマーシュの生活です。
テレザは、トマーシュの髪に女のデルタの臭いを嗅ぎとります。
バーで働くテレザはある時、男の誘いに乗り、浮気をします。
男の部屋でソフォクレースの『オイディプース』の翻訳本を見つけます。
テレザはトマーシュに復讐しようというわけではなかったのです。
「第V部 軽さと重さ」で、トマーシュは『オイディプース』にヒントを
得て書いた文章を週刊新聞に送ると、編集部から呼ばれ掲載されます。
ロシア人の軍隊による占領を招いた共産主義者たちは、公然と自分たちの
目を刺すべきだ、というトマーシュの意見に対して圧力をかけてきます。
しかし「あれ以上大事なものはありません」と拒否したトマーシュは、
外科医の職を奪われ、地位の低い地方病院の医者に、さらに窓掃除人に。
そこでも彼の名は知られていて、反体制派の人物が接触してきます。
そこにトマーシュの息子も。前妻は共産主義だが、息子は違いました。
サビナはプラハは嫌な町になったといい、トマーシュに田舎へ引っ越そう
と話します。彼にとってサビナは『饗宴』でいう片割れなのでしょうか?
《 トマーシュはプラトンの有名なシンポジオンという神話を思い出し
た。人びとは最初、男女両性具有者であったが、神がそれを二等分
したので、その半身はそれ以来世の中をさまよい、お互いを探し求め
ている。愛とは我々自身の失われた半身への憧れである。》p.304
この後、アメリカへ移民したサビナの話や、政治的な話が出てきます。
●『存在の耐えられない軽さ』とは?
ストーリーを追うのはこのへんにして、私なりの感想を書いていこうか
と思います。
男女の愛と性をめぐるお話と、チェコの民主化を阻むソ連軍や
それに迎合する共産主義者によって、祖国を守ろうとする人々や
政治犯とされる人々が追い込まれていく政治的なお話が展開されます。
人間にとって大事なことは、男女の愛(と性)の生活なのか、政治的に
自由な生活なのか、<存在の耐えられない軽さ>とは何なのか。
正直なところ、よくわかりません。
「第VI部 大行進」で、
《(略)テレザとトマーシュは重さの印の下で死んだ。彼女(引用者注
・サビナ)は軽さの印の下で死にたいのである。彼女は空気よりも
軽くなる。これはパルメニデースによれば、否定的なものから
肯定的なものへの変化である。》p.344
とあります。
確かに、トマーシュは発言を撤回させず、社会から抹殺されていきます。
トマーシュは銃殺され、最後にはテレザも死んでしまったようです。
それは思想的な理由で殺される重い死だったようですし、
それに比べれば、アメリカに逃れた? サビナの最期はまた違ったものに
できるのでしょう。
●「第VII部 カレーニンの微笑」
しかし、先にも書きましたように、
そのラストは非常に感動的なものでした。
その場面での存在のなかには、男女以外に愛犬がいました。
《(略)カレーニンとテレザの愛は、彼女とトマーシュとの間のそれ
よりもよいという考えである。よりよいのであって、より大きいと
いうのではない。(略)》p.372
《 犬への愛は無欲のものである。テレザはカレーニンに、何も要求
しない。愛すらも求めない。私を愛している? 誰か私より好き
だった? 私が彼を愛しているより、彼は私のことを好きかしら?
というような二人の人間を苦しめる問いを発することはなかった。
愛を測り、調べ、明らかにし、救うために発する問いはすべて、愛を
急に終わらせるかもしれない。(略)》p.373
《(略)テレザはカレーニンをあるがままに受け入れ、自分の思う
ように変えることを望まず、あらかじめ、カレーニンの犬の世界に
同意し、それを奪おうとはせず、カレーニンの秘め事にも
嫉妬しなかった。犬を(男が自分の妻を作り直そう、女が自分の
亭主を作り直そうとするように)作り直そうとはしないで、ただ
理解し合っていっしょに暮せるような基本的な言語を学べるように
と育てた。/ さらにいえば、犬への愛はだれかがテレザに強いた
のではなく、自由意志に基づくものである。(略)》p.373
《(略)人間の時間は輪となってめぐることはなく、直線に沿って
前へと走るのである。これが人間が幸福になれない理由である。
幸福は繰り返しへの憧れなのだからである。/ そう、幸福とは
繰り返しへの憧れであると、テレザは独りごとをいう。》p.374
カレーニンとの暮らしは、基本的に毎朝、同じことの繰り返しでした。
そして、時が来てカレーニンにお迎えが来て、安楽死させた二人は
決めていたリンゴの木の間に埋葬します。
考えてみれば、私たちの暮らしというものも、基本、同じことを繰り返し
続けられるうちが花で、しあわせな日々といえるのかも知れません。
トマーシュは、外科医を辞めさせられ、愛人との生活も失われ、
テレザとカレーニンとの田舎での暮らしとなりました。
時には、トマーシュのために着飾ったテレザを見た若い男と農場長たちと
ホテルのバーのダンスホールに出かけ、楽しい時間をすごしました。
テレザが真に彼の失われた片割れであったかどうかはわかりません。
しかし、最終的に彼らが選んだのは、二人(と一匹)の生活でした。
《(略)人生はたった一度かぎりだ。それゆえわれわれのどの決断が
正しかったか、どの決断が誤っていたかを確認することはけっして
できない。所与の状況でたったの一度しか決断できない。いろいろ
な決断を比較するための、第二、第三、第四の人生は与えられて
いないのである。/ 歴史も、個人の人生と似たようなものである。
チェコ人の歴史はたった一度しかない。トマーシュの人生と同じよう
にある日終わりを告げ、二度繰り返すことはできないであろう。》
p.284(「第V部 軽さと重さ」)
・・・
色々と考えさせられる小説でした。
難しいといえば難しいですし、こういう展開の仕方はストーリーとして
どうなんだ? と問われたら、こういうのもありなんでしょうね、
としかいえません。
とにかく、一度は読んでおきたい小説です。
みなさまもどうぞ、機会があれば!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本誌では、「新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2025から(2)集英社文庫・『存在の耐えられない軽さ』ミラン・クンデラ~一回限りの人生~」と題して、今回も全文転載紹介です。
本文中にも書きましたように、人生というのは一回ポッキリのもので、やり直しはできません。
セカンド・チャンスはありません。
それだけにその時その時の決断というものが重要になって来ます。
しかし、考えすぎては、チャンスを逃がすことにもなりかねません。
難しいものです、何十年生きてきても。
でも、それだからこそ「人生はおもしろい」とも言えるのかも知れません。
・・・
*本誌のお申し込み等は、下↓から
(まぐまぐ!)『(古典から始める)レフティやすおの楽しい読書』
『レフティやすおのお茶でっせ』
〈メルマガ「楽しい読書」〉カテゴリ
--
『レフティやすおのお茶でっせ』より転載
" target="_blank"><夏の文庫>フェア2025から(2)集英社文庫『存在の耐えられない軽さ』ミラン・クンデラ-楽しい読書393号
--