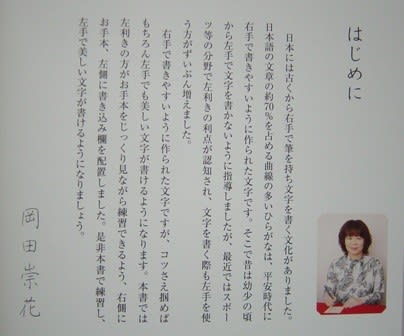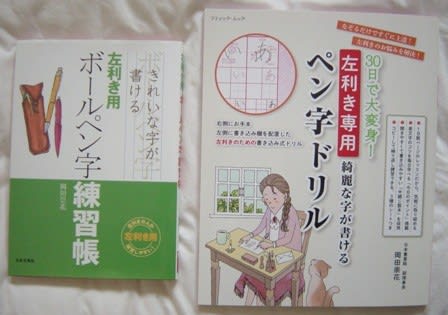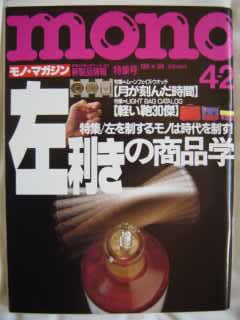―第236号「レフティやすおの楽しい読書」別冊 編集後記
★古典から始める レフティやすおの楽しい読書★
2018(平成30)年11月30日号(No.236)
「クリスマス・ストーリーをあなたに~(8)『昔なつかしいクリスマス』ワシントン・アーヴィング」
------------------------------------------------------------
(目次)
過去の「クリスマス・ストーリーをあなたに」の紹介
~過去の私のおススメの〈クリスマス・ストーリー〉~
●『昔なつかしいクリスマス』の紹介
●イギリスのクリスマスの概略(第1章)
●ステージコートの旅(第2章)
●クリスマス前夜(第3章)
●クリスマス当日(第4章)
●クリスマス・ディナー(第5章)
------------------------------------------------------------
本誌は、例年恒例の私のお気に入りのクリスマス・ストーリーを紹介する「~クリスマス・ストーリーをあなたに~」の8回目、「『昔なつかしいクリスマス』ワシントン・アーヴィング」です。
『クリスマス・キャロル』以前のクリスマス物語といいますか、クリスマス紹介エッセイです。
200年前のイギリスの地方地主のお屋敷に招かれたアメリカ人の見たクリスマス風景の紹介です。
長々と書いた割には、思うように要点をまとめられず、あまりいい紹介はできませんでした。
でも、それなりに何かしらは伝えられたのでは、と心は慰めています。
・・・
では、詳細は本誌で!
*本誌のお申し込み等は、下↓から
(まぐまぐ!)『(古典から始める)レフティやすおの楽しい読書』
*参照:
『昔なつかしいクリスマス』ワシントン・アーヴィング/著 ランドルフ・コールデコット/挿絵 齊藤昇/訳 三元社 2016.12.1
―1920年刊『スケッチ・ブック』第5分冊(クリスマス編)を基に、コールデコットの挿絵をつけて1876年に刊行された。
『スケッチ・ブック』下巻 ワシントン・アーヴィング/著 齊藤昇/訳 岩波文庫 2015.1.16
―『スケッチ・ブック』上巻(20編)に続く後半14編+あとがき収録。冒頭にクリスマスもの5編、他に「スリーピー・ホローの伝説」等。上記の原本から6枚のイラストと『スケッチ・ブック』原本からもイラストを何葉か収録。
--
『レフティやすおのお茶でっせ』より転載
クリスマス・ストーリーをあなたに~(8)『昔なつかしいクリスマス』ワシントン・アーヴィング
--
★古典から始める レフティやすおの楽しい読書★
2018(平成30)年11月30日号(No.236)
「クリスマス・ストーリーをあなたに~(8)『昔なつかしいクリスマス』ワシントン・アーヴィング」
------------------------------------------------------------
(目次)
過去の「クリスマス・ストーリーをあなたに」の紹介
~過去の私のおススメの〈クリスマス・ストーリー〉~
●『昔なつかしいクリスマス』の紹介
●イギリスのクリスマスの概略(第1章)
●ステージコートの旅(第2章)
●クリスマス前夜(第3章)
●クリスマス当日(第4章)
●クリスマス・ディナー(第5章)
------------------------------------------------------------
本誌は、例年恒例の私のお気に入りのクリスマス・ストーリーを紹介する「~クリスマス・ストーリーをあなたに~」の8回目、「『昔なつかしいクリスマス』ワシントン・アーヴィング」です。
『クリスマス・キャロル』以前のクリスマス物語といいますか、クリスマス紹介エッセイです。
200年前のイギリスの地方地主のお屋敷に招かれたアメリカ人の見たクリスマス風景の紹介です。
長々と書いた割には、思うように要点をまとめられず、あまりいい紹介はできませんでした。
でも、それなりに何かしらは伝えられたのでは、と心は慰めています。
・・・
では、詳細は本誌で!
*本誌のお申し込み等は、下↓から
(まぐまぐ!)『(古典から始める)レフティやすおの楽しい読書』
*参照:
『昔なつかしいクリスマス』ワシントン・アーヴィング/著 ランドルフ・コールデコット/挿絵 齊藤昇/訳 三元社 2016.12.1
―1920年刊『スケッチ・ブック』第5分冊(クリスマス編)を基に、コールデコットの挿絵をつけて1876年に刊行された。
『スケッチ・ブック』下巻 ワシントン・アーヴィング/著 齊藤昇/訳 岩波文庫 2015.1.16
―『スケッチ・ブック』上巻(20編)に続く後半14編+あとがき収録。冒頭にクリスマスもの5編、他に「スリーピー・ホローの伝説」等。上記の原本から6枚のイラストと『スケッチ・ブック』原本からもイラストを何葉か収録。
--
『レフティやすおのお茶でっせ』より転載
クリスマス・ストーリーをあなたに~(8)『昔なつかしいクリスマス』ワシントン・アーヴィング
--