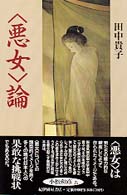放射能物質は現在、垂れ流しの状況です。汚染された水は、どこにももっていきようがないほどになっています。先日の台風(幸いというか、被災地では熱帯低気圧になりかなりおさまりましたが、それでも1号機から4号機はさらに原子炉内の水位があがって深刻な状況にたっしました)。本格的な台風がきたら、放射能物質は撹拌され関東一円にばらまかれる可能性もあります。
放射能物質は眼にみえなません。種々の放射線(α線、β線、γ線)は、長い時間をかけて自然、人間生活をむしばんでいきます。「ただちに」人間がバタバタ死んでいくのではないので、まだひとごとのように考えている人がいます。今後のエネルギー政策は原子力発電も自然発電も適度に是々非々で使えばいいのではという考え方がありますが、原発依存のエネルギー政策はただちに変更するのが得策です。
さて、本書は市民科学者であり、原子力問題に多くの著者のあった著者が癌との闘病のなかで、どうしてもこれだけは伝えなければならないと思って書いた遺言です。著者は2000年に亡くなりましたが、今回の原発事故をまのあたりにしたら、きっと日本はまだ凝りもせず原発を推進していたのかと、あきれたことでしょう。
冒頭で、本書の刊行(2000年)の前年に起きた茨城県東海村のJCO社のウラン加工施設での臨界事故に触れています。この事故で二人の作業員が亡くなりました。95年12月の高速増殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故、97年3月の動燃の東海再処理工場でのアスファルト固化処理施設での火災爆発事故に続くもので大騒ぎになった大事故です(日本人は忘れっぽいのでもう覚えていない人が多いかもしれません)。
著者は日本で原子力文化、安全文化がその開発の初発から議論も、批判も、思想もなく、その状態が原子力産業の在り方についても同じであったことを指摘しています。
アメリカからのつぎはぎ的導入で、国家まかせの施策として、トップダウンで進められたのが日本の原子力行政でした。議論が全くないままにいわばなし崩し的に措置されてきたのが原子力開発であり、原子力行政だというわけです。
著者は実際に若いころに日本原子力事業、東京大学原子核研究所で仕事をしていて、上記の指摘はそのなかでの実感なので説得力があります。
著者はさらに原子力産業の自己検証能力のなさ、本来の意味でのアカウンタビィリティの欠如、総じて「自己に甘い体質」(p.142)に言及しています。
また、現場で「手触り感」をもたない研究者が、いとも簡単にデータの隠蔽、改竄をおこなっている現状を告発しています。
最後に「友へ」というメッセージで高木さんは次のように書いています、「残念ながら、原子力最後の日は見ることができず、私の方が先に逝かねばなりましたが、せめて『プルトニウム最後の日』くらいは、目にしたかったです。でも、それはもう時間の問題でしょう。すでにあらゆる事実が、私たちの主張が正しかったことを示しています。なお、楽観できないのは、この末期症状の中で、巨大な事故や不正が原子力の世界を襲う危険でしょう。JCO事故からロシア原潜事故までのこの一年間を考えるとき、原子力時代の末期症状による大事故の危険と結局は放射性廃棄物がたれ流しになっていくのではないかということに対する危惧の念は、今、先に逝ってしまう人間の心を最も悩ますものです」と(pp.182-183)。


















![女優岡田茉莉子 [本]](https://a248.e.akamai.net/f/248/37952/1h/image.shopping.yahoo.co.jp/i/j/7andy_32333401)