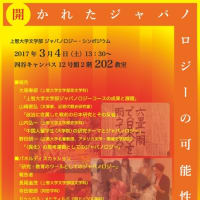また遡り記事になるが、3月25日(火)は、左のイベント「エンサイクロペディア・シネマトグラフィカを見る(6):ECフィルムからのパフォーマンス創造 vol.1」に参加してきた。今回は、6度に及ぶ上映会のなかでも初めて「生物学」ジャンルの映像を使用し、また単にそれらを観るだけではなく、現代のダンス・パフォーマンスと組み合わせ新たな創造的可能性を探求しようという試み。解説者は民博の川瀬慈さんで、まずはECフィルムの概要から説明をいただいた。ECフィルム作成の経緯についてはすでに1回目の上映会で伺っていたし、その後目録も購入したのである程度の知識はあったが、今回、民族学のモダン/ポストモダン的潮流とどのように関わるのかが分かってよかった。ECフィルムが生まれた1950年代の民族学では、すでに客観主義的・科学主義的態度の批判が始まっており、記録映像自体にも、記録者と対象との双方向性や、主観性・芸術性を重視した試みもなされるようになっていた。そのようななかでECフィルムは、主体をとことん消し去ろうとするストイックな科学主義を維持し、記録した映像は定期的に開かれる編集委員会で審査され、その水準が保たれたという。確立された技法は世界中の人類学者へ伝授されたらしいが、個人的に興味を惹かれたのは、1998~2003年にかけての雲南省東アジア映像人類学研究所への指導。1992年に北京映像人類学会が設立されたことを契機としたようだが、ここから現在のドキュメンタリー映画を担う多くの人材が輩出されたという。確かに、雲南を舞台にしたドキュメンタリーには秀作が多い。昨年公開されて話題になった『三姉妹~雲南の子』のワン・ビンも、ひょっとするとECフィルムの影響を受けているのだろうか。
また遡り記事になるが、3月25日(火)は、左のイベント「エンサイクロペディア・シネマトグラフィカを見る(6):ECフィルムからのパフォーマンス創造 vol.1」に参加してきた。今回は、6度に及ぶ上映会のなかでも初めて「生物学」ジャンルの映像を使用し、また単にそれらを観るだけではなく、現代のダンス・パフォーマンスと組み合わせ新たな創造的可能性を探求しようという試み。解説者は民博の川瀬慈さんで、まずはECフィルムの概要から説明をいただいた。ECフィルム作成の経緯についてはすでに1回目の上映会で伺っていたし、その後目録も購入したのである程度の知識はあったが、今回、民族学のモダン/ポストモダン的潮流とどのように関わるのかが分かってよかった。ECフィルムが生まれた1950年代の民族学では、すでに客観主義的・科学主義的態度の批判が始まっており、記録映像自体にも、記録者と対象との双方向性や、主観性・芸術性を重視した試みもなされるようになっていた。そのようななかでECフィルムは、主体をとことん消し去ろうとするストイックな科学主義を維持し、記録した映像は定期的に開かれる編集委員会で審査され、その水準が保たれたという。確立された技法は世界中の人類学者へ伝授されたらしいが、個人的に興味を惹かれたのは、1998~2003年にかけての雲南省東アジア映像人類学研究所への指導。1992年に北京映像人類学会が設立されたことを契機としたようだが、ここから現在のドキュメンタリー映画を担う多くの人材が輩出されたという。確かに、雲南を舞台にしたドキュメンタリーには秀作が多い。昨年公開されて話題になった『三姉妹~雲南の子』のワン・ビンも、ひょっとするとECフィルムの影響を受けているのだろうか。 さて、この日に上映された映像は、1)ジャーマン・シェパードの走行、2)ヒグマの走行、3)キンカジュウの登攀、4)スローロリスの登攀、5)マリミズムシの分泌物による身繕い、6)オランウータンの走行、7)モモイロペリカンの協働漁撈、8)サケを捕るオオカミ、9)サケを捕るヒグマ、いずれも3~4分程度の作品。このうち4)~8)は、京都で活躍する前衛的ダンス・ユニット「双子の未亡人」のパフォーマンスと併せて「上演」された。「未亡人」2人の恐るべき身体能力と、画面のなかの動物たちの動きが、特定の律動を通じてシンクロしてゆく。先日の環境思想シンポの懇親会でも、野田研一さんと身体/リズムの関係の話になったのだが、個々の生命に固有のリズム、そして自然界を貫くリズムの存在は間違いなくあろう。それゆえに、人間の舞踏は動物を真似することから始まり、言語を超えてあらゆる観衆を巻き込む熱狂を生む。そんなことを考えながらみていると、最前列に座っていたからだろうか、とつぜん「未亡人」の2人に舞台へと引き出された。2人のパフォーマンスに一部参加させていただき、一緒に立位体前屈。若い頃と比べるとかなり硬くなったが、それでも掌くらいは床に着けられる。おかげで、ずいぶんと体を伸ばすことができた。この日は何人かが「生け贄」になっていたが、ぼくがその最初。学生の頃から、「指名されたくないときに指名される」情況は変わっていない…。
さて、この日に上映された映像は、1)ジャーマン・シェパードの走行、2)ヒグマの走行、3)キンカジュウの登攀、4)スローロリスの登攀、5)マリミズムシの分泌物による身繕い、6)オランウータンの走行、7)モモイロペリカンの協働漁撈、8)サケを捕るオオカミ、9)サケを捕るヒグマ、いずれも3~4分程度の作品。このうち4)~8)は、京都で活躍する前衛的ダンス・ユニット「双子の未亡人」のパフォーマンスと併せて「上演」された。「未亡人」2人の恐るべき身体能力と、画面のなかの動物たちの動きが、特定の律動を通じてシンクロしてゆく。先日の環境思想シンポの懇親会でも、野田研一さんと身体/リズムの関係の話になったのだが、個々の生命に固有のリズム、そして自然界を貫くリズムの存在は間違いなくあろう。それゆえに、人間の舞踏は動物を真似することから始まり、言語を超えてあらゆる観衆を巻き込む熱狂を生む。そんなことを考えながらみていると、最前列に座っていたからだろうか、とつぜん「未亡人」の2人に舞台へと引き出された。2人のパフォーマンスに一部参加させていただき、一緒に立位体前屈。若い頃と比べるとかなり硬くなったが、それでも掌くらいは床に着けられる。おかげで、ずいぶんと体を伸ばすことができた。この日は何人かが「生け贄」になっていたが、ぼくがその最初。学生の頃から、「指名されたくないときに指名される」情況は変わっていない…。ECフィルムを創造的に活かそうとするこの試み、果たして成功していたのかどうかは分からないが、観る者の想像力をさまざまに刺激したことは確かなようだ。