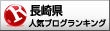平成新山の初冠雪や初雪があったために1日間が空いてしまいました。
万灯山から見えた山の中腹まで延びる階段の下までやってきました。
大きな建物は神社でした。
上り口に大きな由緒書きがあります。
それによると、この神社は「河上神社」と言います。
旧称は、四面宮(おしめんさん)。
なんと!四面宮の分社でしたか!!
御祭神は、大己貴命(おおなむろのみこと)・少彦名命(すくなひこなのみこと)。
「元は、水神の闇遊迦神(くらおかみのかみ)・闇御津羽神(くらみつはのかみ)ならびに四面菩薩をお祀りする神仏習合の古社なり。」
長い階段を登り上がると、立派なお社が。

縁起によると、
「正確な創立年号は不祥なれど、奈良時代中期から末期と推定される。往古より鎮座し、森山村(本村・慶師野・田尻・杉谷)の氏神なり。江戸時代中期に境内を整備し、旧鳥居額は若杉春后の書なり。明治期の祭事費用は土橋貞恵翁の寄進を以て充てた。明治四十一年、昭和五十五年にそれぞれ氏子一同の寄進により神殿拝殿等と改修。昭和七年秋の台風で御神木の大杉(樹齢千二百余年の大木)が倒木した。」
よもや、こんな所で今まで学習してきた若杉春后や土橋貞恵の名前が繋がるとは思っていなかった。w
「縁は奇なるもの」とはよく言ったものです。
河上神社からの眺めです。

万灯山から見えた山の中腹まで延びる階段の下までやってきました。
大きな建物は神社でした。
上り口に大きな由緒書きがあります。
それによると、この神社は「河上神社」と言います。
旧称は、四面宮(おしめんさん)。
なんと!四面宮の分社でしたか!!
御祭神は、大己貴命(おおなむろのみこと)・少彦名命(すくなひこなのみこと)。
「元は、水神の闇遊迦神(くらおかみのかみ)・闇御津羽神(くらみつはのかみ)ならびに四面菩薩をお祀りする神仏習合の古社なり。」
長い階段を登り上がると、立派なお社が。

縁起によると、
「正確な創立年号は不祥なれど、奈良時代中期から末期と推定される。往古より鎮座し、森山村(本村・慶師野・田尻・杉谷)の氏神なり。江戸時代中期に境内を整備し、旧鳥居額は若杉春后の書なり。明治期の祭事費用は土橋貞恵翁の寄進を以て充てた。明治四十一年、昭和五十五年にそれぞれ氏子一同の寄進により神殿拝殿等と改修。昭和七年秋の台風で御神木の大杉(樹齢千二百余年の大木)が倒木した。」
よもや、こんな所で今まで学習してきた若杉春后や土橋貞恵の名前が繋がるとは思っていなかった。w
「縁は奇なるもの」とはよく言ったものです。
河上神社からの眺めです。