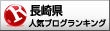先日から暫くの間、汲上げポンプが故障して水が出ませんでした。
トイレの水は別系統だったので、ひどく困ったわけではありませんでしたが、手洗い用の水のため以前紹介した「内野湧水」に時々水を汲みに行っていました。(なんだか昔話みたい)
雲仙から下ってきた時に立ち寄るのですが、なにかしら近道がないかとあの辺り一帯を車で走り回っていた時に見つけました。
ご覧の通り、看板だけしか残っていないので詳しいことは分かりません。
多分このまま朽ちていきそうなので、無くならないうちに記録として書かれていることをそのまま記載します。
「梶木遺跡は温泉岳連峰の野岳(1147m)のスロープを形成する扇状台地の麓、標高280mの地に位置している。
戦後、この地は開拓地で、開墾や耕作のたびに多数の石器や土器が出土した。日本考古学協会会員吉田正隆氏はこの地から、二片の土器を採取した。驚いたことにその土器からモミの圧痕が発見された。
更にまた、吉田氏は糸をつむぐ道具の紡錘車二個も採取している。
その遺跡から出土した遺物は独特の土器文化を展開し、考古学会の森貞二郎博士は出土した土器を「山の寺式土器」と名付けられた。
年代を2500年前、その時代は縄文晩期の末葉と比定された。
従来日本における稲の出現は弥生期とされているが、この地 山の寺梶木ではすでに縄文の晩期に米作りが行われていたのではなかろうか、昭和35年8月、「西北九州総合調査特別委員会」は山の寺梶木遺跡の学術調査を実施した。
発掘された遺物は、農耕用石器と山の寺式土器の各種、その他組織痕土器、甕・壺は口が小さく赤色や黒色に塗彩されたものもあり、更にかつて吉田氏が採取した紡錘車二個に加えて新に二個が発掘され、この地における織物技術の存在をいよいよ明確にした。
吉田氏採取のモミ痕土器を柱に、多くの資料を組み合わせると、山の寺文化に米作りの農業があったことは動かせない事実である。
平成12年3月建立 深江町教育委員会」
・・・肝心の土器はどこかに保管されているのであろうか?
トイレの水は別系統だったので、ひどく困ったわけではありませんでしたが、手洗い用の水のため以前紹介した「内野湧水」に時々水を汲みに行っていました。(なんだか昔話みたい)
雲仙から下ってきた時に立ち寄るのですが、なにかしら近道がないかとあの辺り一帯を車で走り回っていた時に見つけました。
ご覧の通り、看板だけしか残っていないので詳しいことは分かりません。
多分このまま朽ちていきそうなので、無くならないうちに記録として書かれていることをそのまま記載します。
「梶木遺跡は温泉岳連峰の野岳(1147m)のスロープを形成する扇状台地の麓、標高280mの地に位置している。
戦後、この地は開拓地で、開墾や耕作のたびに多数の石器や土器が出土した。日本考古学協会会員吉田正隆氏はこの地から、二片の土器を採取した。驚いたことにその土器からモミの圧痕が発見された。
更にまた、吉田氏は糸をつむぐ道具の紡錘車二個も採取している。
その遺跡から出土した遺物は独特の土器文化を展開し、考古学会の森貞二郎博士は出土した土器を「山の寺式土器」と名付けられた。
年代を2500年前、その時代は縄文晩期の末葉と比定された。
従来日本における稲の出現は弥生期とされているが、この地 山の寺梶木ではすでに縄文の晩期に米作りが行われていたのではなかろうか、昭和35年8月、「西北九州総合調査特別委員会」は山の寺梶木遺跡の学術調査を実施した。
発掘された遺物は、農耕用石器と山の寺式土器の各種、その他組織痕土器、甕・壺は口が小さく赤色や黒色に塗彩されたものもあり、更にかつて吉田氏が採取した紡錘車二個に加えて新に二個が発掘され、この地における織物技術の存在をいよいよ明確にした。
吉田氏採取のモミ痕土器を柱に、多くの資料を組み合わせると、山の寺文化に米作りの農業があったことは動かせない事実である。
平成12年3月建立 深江町教育委員会」
・・・肝心の土器はどこかに保管されているのであろうか?