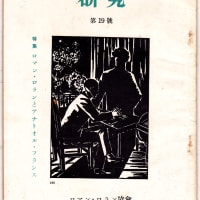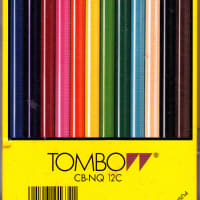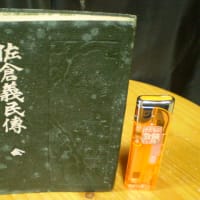三田で思い出したのだけど、三田藩の殿様と福沢諭吉は懇意にしていて、明治の初め、福沢は大阪から三田まで旅をしています。大阪から三田まで15里とある。
その道中のことが「福翁自伝」に書いてあるのですが、これが傑作。わたしの好きな一節です。
諭吉は、道中、向こうから行きかう人ごとに、態度を変えて話しかけると、こちらの態度のちがいでむこうもまるでゴム人形のように態度を変える、と驚く。諭吉は、これは文明開化以前のそれまでの封建時代のなごりと思っていたようだが、なんのなんの文明開化した今でも、このしょうもない国民性はあるのではなかろうか。
福沢の実験精神、イタズラ精神が出ていておもしろいので、ここは福翁自伝を引用します。
「ころは旧暦の3,4月、まことによい時期で、私はパッチをはいて羽織かなにかを着てこうもりがさを持って、-略ー たったひとりで供もなければ連れもない、話相手がなくておもしろくないところから、なんでも人に会うて言葉を交えてみたいと思い、往来の向こうから来る百姓のような男に向かって道を聞いたら、そのときの私のそぶりが、なにか横風で昔の士族の正体が現れて言葉も荒かったとみえる。
するとその百姓がまことにていねいに道を教えてくれておじぎをしていく。こりゃおもしろいと思い、自分の身を見れば持っているのはこうもりがさ1本きりでなんにもない。
も1度やってみようと思うて、その次に来るやつにむかってどなりつけ、「コリャ待て、向こうに見える村はなんと申す村だ。シテ村の家数はおよそ何軒ある。あのかわら屋の大きな家は百姓か町人か、主人の名はなんと申す」などと、くだらぬことをたたみかけて士族丸出しの口調で尋ねると、そいつは道のはたに小さくなって、恐れながらお答え申し上げますというような様子だ。
こっちはますますおもしろくなって、今度はさかさまにやってみようと思いつき、またむこうから来るやつに向かって「モシモシはばかりながらちょいとものをお尋ね申します」というような口調にでかけて相変わらずくだらぬ問答を始め、私は大阪生まれでまた大阪にも久しく寄留していたから、そのときにはたいてい大阪のことばも知っていたから、すべてやつの調子に合わせてごてごて話をすると、やつは私を大阪の町人が掛けとりにでも行く者と思うたか、なかなか横風でろくに会釈もせずにさっさと別れていく。
そこで、今度はまたその次のヤツに横風をきめこみ、またその次にはていねいに出かけ、いっさい先の顔色に取捨なく、だれでもただ向こうから来る人間1匹ずつ1つおきときめてやってみたところが、およそ3里ばかり歩く間、思うとおりになったが、そこで私の心中ははなはだおもしろくない。
いかにもこれはしょうもないやつらだ。だれもかれも小さくなるなら小さくなり、横風ならば横風でもよし、こうどうも先の人を見て自分の身を伸び縮みするようなことではしょうがない。推して知るべし。地方小役人らのいばるのも無理はない。世間に圧制政府という説があるが、これは政府の圧制ではない。人民の方から圧制を招くのだ」
福沢諭吉といえば、1万円札の肖像が有名だけど、あれはよくない。われわれとは縁もゆかりもないおじさんに見える。それよりも若いころの顔がいい。
天保5年生まれで、清河八郎より5歳下、坂本竜馬よりも一つ上。幕末の志士ではないけど、あの乾いたサバサバした精神は幕末の英雄豪傑以上のものがあります。
その道中のことが「福翁自伝」に書いてあるのですが、これが傑作。わたしの好きな一節です。
諭吉は、道中、向こうから行きかう人ごとに、態度を変えて話しかけると、こちらの態度のちがいでむこうもまるでゴム人形のように態度を変える、と驚く。諭吉は、これは文明開化以前のそれまでの封建時代のなごりと思っていたようだが、なんのなんの文明開化した今でも、このしょうもない国民性はあるのではなかろうか。
福沢の実験精神、イタズラ精神が出ていておもしろいので、ここは福翁自伝を引用します。
「ころは旧暦の3,4月、まことによい時期で、私はパッチをはいて羽織かなにかを着てこうもりがさを持って、-略ー たったひとりで供もなければ連れもない、話相手がなくておもしろくないところから、なんでも人に会うて言葉を交えてみたいと思い、往来の向こうから来る百姓のような男に向かって道を聞いたら、そのときの私のそぶりが、なにか横風で昔の士族の正体が現れて言葉も荒かったとみえる。
するとその百姓がまことにていねいに道を教えてくれておじぎをしていく。こりゃおもしろいと思い、自分の身を見れば持っているのはこうもりがさ1本きりでなんにもない。
も1度やってみようと思うて、その次に来るやつにむかってどなりつけ、「コリャ待て、向こうに見える村はなんと申す村だ。シテ村の家数はおよそ何軒ある。あのかわら屋の大きな家は百姓か町人か、主人の名はなんと申す」などと、くだらぬことをたたみかけて士族丸出しの口調で尋ねると、そいつは道のはたに小さくなって、恐れながらお答え申し上げますというような様子だ。
こっちはますますおもしろくなって、今度はさかさまにやってみようと思いつき、またむこうから来るやつに向かって「モシモシはばかりながらちょいとものをお尋ね申します」というような口調にでかけて相変わらずくだらぬ問答を始め、私は大阪生まれでまた大阪にも久しく寄留していたから、そのときにはたいてい大阪のことばも知っていたから、すべてやつの調子に合わせてごてごて話をすると、やつは私を大阪の町人が掛けとりにでも行く者と思うたか、なかなか横風でろくに会釈もせずにさっさと別れていく。
そこで、今度はまたその次のヤツに横風をきめこみ、またその次にはていねいに出かけ、いっさい先の顔色に取捨なく、だれでもただ向こうから来る人間1匹ずつ1つおきときめてやってみたところが、およそ3里ばかり歩く間、思うとおりになったが、そこで私の心中ははなはだおもしろくない。
いかにもこれはしょうもないやつらだ。だれもかれも小さくなるなら小さくなり、横風ならば横風でもよし、こうどうも先の人を見て自分の身を伸び縮みするようなことではしょうがない。推して知るべし。地方小役人らのいばるのも無理はない。世間に圧制政府という説があるが、これは政府の圧制ではない。人民の方から圧制を招くのだ」
福沢諭吉といえば、1万円札の肖像が有名だけど、あれはよくない。われわれとは縁もゆかりもないおじさんに見える。それよりも若いころの顔がいい。
天保5年生まれで、清河八郎より5歳下、坂本竜馬よりも一つ上。幕末の志士ではないけど、あの乾いたサバサバした精神は幕末の英雄豪傑以上のものがあります。