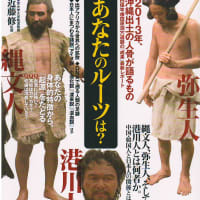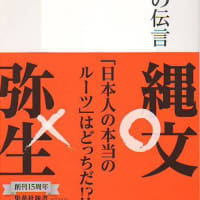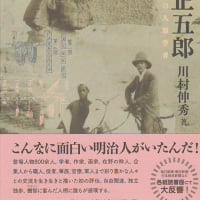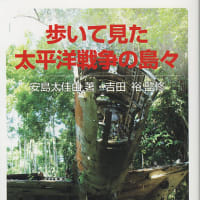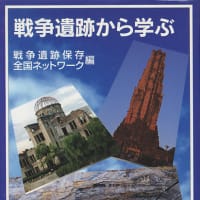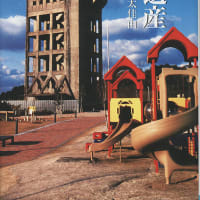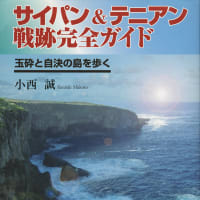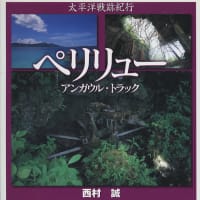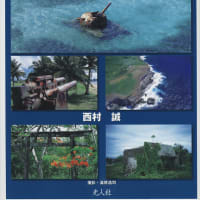若林勝邦(Katsukuni WAKABAYASHI)[1862-1904][杉山(2003)より改変して引用](以下、敬称略。)
若林勝邦は、1862年10月7日に、江戸城内馬場先門近郊で生まれました。若林家は、旧幕臣の家系でした。やがて、1885年に東京物理学校(現・東京理科大学)を卒業し、神田小学校に勤務します。但し、杉山博久の論文によると、東京理科大学同窓会名簿には、名前を見つけることができないとありますが、この辺の事情はわかりません。
若林勝邦は、1885年に日本人類学会に入会しています。当時は、「じんるいがくのとも」という名前でしたが、1884年に創立されていますので、翌年に入会したことになります。1887年8月には、坪井正五郎[1863-1913]と一緒に埼玉県の吉見百穴遺跡の調査を行っています。やがて、若林勝邦に大きな転機が訪れました。
若林勝邦は、1889年に理科大学人類学研究室勤務となりました。1890年に理科大学技手となり、1893年には理科大学助手に就任します。ちなみに、教室主任である坪井正五郎は、1889年から1892年までヨーロッパに遊学しました。若林勝邦は、坪井が不在にしている間、人類学教室の留守番をしていたことになります。
ところが、この間、事件が起こりました。後に、東京帝国大学理学部人類学教室の助教授となる鳥居龍蔵[1870-1953]が1953年に出版した『ある老学徒の手記』(朝日新聞社)によると、「若林氏に、ここにある人類学の本を読みたいと申入れ、小さなガラス張りの書箱の中の本に手をかけようとしたところが、若林氏の気色は忽ち変じ”君は生意気なり”と大声で叫ばれ・・・(中略)・・・私はその日はそのままに帰ったが、翌日になって若林氏から一通の葉書が届いた。これには”君に明日より教室に来ることを断る”云々とあった。仕方なく私はそれから断然教室に行くことをよした。」とあります。当時、坪井正五郎はヨーロッパに遊学中でした。
やがて、坪井正五郎が帰国すると、坪井正五郎から鳥居龍蔵宛に書面が来ていて「人類学教室に来られ度し」とあり、鳥居龍蔵は人類学教室に出入りします。坪井正五郎は、鳥居龍蔵に人類学選科生になることを勧めましたが標本整理係に就任しました。その後、若林勝邦が人類学教室の多額な旅費を使っていることに不満を述べています。若林勝邦と鳥居龍蔵の間には、教室への出入り禁止事件以来、確執が続いていたのかもしれません。
実際、若林勝邦は、亀ヶ岡遺跡(青森県)・三貫地貝塚(福島県)・新地貝塚(福島県)・山崎貝塚(千葉県)・蜆塚遺跡(静岡県)・曽畑貝塚(熊本県)等、東北から九州まで精力的に調査を行っています。若林勝邦を研究した、杉山博久さんの調査によると、1889年から1894年まで、公務出張が15回・私事旅行が9回と、合計24回にも及ぶそうです。交通手段が発達していない当時の事ですから、その調査は困難を極め、莫大な費用がかかったことが推定されます。
1895年に若林勝邦は東京帝国大学理学部人類学教室助手から帝国博物館歴史部(現・東京国立博物館)の技手に移籍します。若林勝邦が移籍した理由はわかりませんが、人類学から考古学の分野に興味が移ったと指摘する説もあります。その後、1902年には博物館の列品監査掛に任命されますが、1904年12月30日に、42歳という若さで死去しました。
若林勝邦は、東京帝国大学理学部人類学教室に、1889年から1895年の6年間しか在籍していませんが、坪井正五郎のヨーロッパ遊学中の3年間、人類学教室と学会を取り仕切りました。1歳年下の坪井正五郎は、若林勝邦を「探究に熱心なる人」と称したそうです。若林勝邦が活躍した期間は、短くも濃いものでしたが人類学の草創期を支えた一人であったことは間違いありません。
*若林勝邦に関する資料として、以下の文献を参考にしました。
- 杉山博久(2003)「探究に熱心なる人(1):若林勝邦小伝」、『考古学雑誌』、第87巻第1号、pp.39-50
- 杉山博久(2003)「探究に熱心なる人(2):若林勝邦小伝」、『考古学雑誌』、第87巻第2号、pp.57(137)-65(145)
- 杉山博久(2003)「探究に熱心なる人(3):若林勝邦小伝」、『考古学雑誌』、第87巻第3号、pp.61(217)-76(232)
- 杉山博久(2003)「探究に熱心なる人(4):若林勝邦小伝」、『考古学雑誌』、第87巻第4号、pp.65(317)-74(326)
- 杉山博久(2004)「探究に熱心なる人(5):若林勝邦小伝」、『考古学雑誌』、第88巻第1号、pp.69(69)-81(81)
- 杉山博久(2004)「探究に熱心なる人(6):若林勝邦小伝」、『考古学雑誌』、第88巻第2号、pp.53(145)-66(158)











![日本の人類学者51.小金井良精(Ryosei KOGANEI)[1859-1944]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0a/97/46d972234646556faff44f0f58d1bae6.jpg)