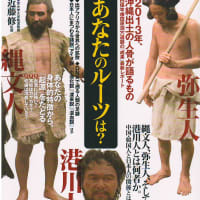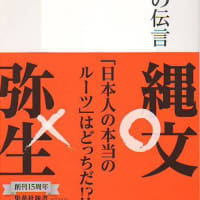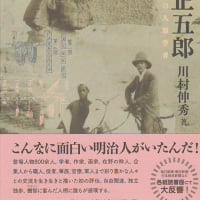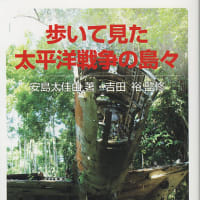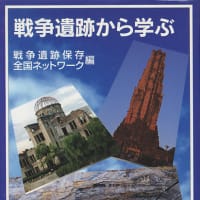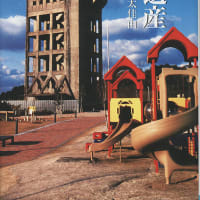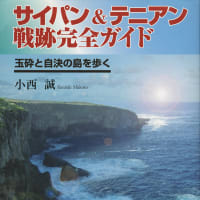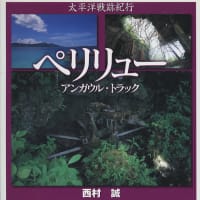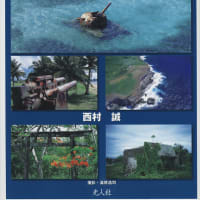1953年1月、東京大学理学部人類学教室の人類学者・鈴木 尚は、研究室にいました。そこへ、学生の岩本光雄(現・京都大学名誉教授)が訪ねてきて、1月8日付けの「毎日新聞」を差し出しました。鈴木 尚は、その新聞を読むと目が釘付けになりました。そこには、鎌倉在住で『ビルマの竪琴』を執筆したことで有名な独文学者の竹山道雄[1903-1984]の自宅の裏山から人骨が出土したことが書かれていたのです。早速、鈴木 尚は、竹山家を訪問し、竹山の母親から1935年頃に多数の人骨が出土し、九品寺に無縁仏として埋葬されたという情報を得ました。早速、九品寺を訪ねるとその通りの情報がえられましたが、住職の代も変わっていて正確な場所は不明との返答を得ます。鈴木 尚は、それらが、鎌倉時代の人骨に違いないと確信し、鎌倉付近を歩き回りました。すると、簡易裁判所建設予定地の地表面に多くの人骨片が散乱していることに気付きます。
鈴木 尚は、早速、東京大学理学部人類学教室主体で発掘調査を行うことにし、1953年の5月と10月及び1956年3月の3回にわたり材木座で発掘調査を行いました。
写真1.1956年の第3次調査で出土した集積墓(209個の頭蓋骨が出土)[日本人類学会編(1956)『鎌倉材木座発見の中世遺跡とその人骨』より改変して引用]
東京大学理学部人類学教室による3回の発掘調査で、合計約910体の人骨が出土しました。これらは、通常の土に埋められた人骨とは異なり、砂浜に埋められていたため保存状態が非常に良いことが特筆されます。
人骨の多くには刀創が認められ、歴史学者の三上次男[1907-1987]により、1333(元弘3)年の新田義貞による鎌倉攻めの際の死者であることが判明しました。
材木座遺跡出土人骨は、1951年に東京大学医学部解剖学教室の骨格標本室で発見した、鍛冶橋出土の室町時代人骨と同様に、頭が前後の方向に長い長頭型で、鼻は低く、反っ歯(歯槽性突顎)でした。頭蓋骨は、半数以上の54.2%が長頭型でした。
写真2.鎌倉材木座No.27頭蓋骨前面観[日本人類学会編(1956)『鎌倉材木座発見の中世遺跡とその人骨』より改変して引用]
写真3.鎌倉材木座No.27頭蓋骨上面観(前後に長い長頭型)[日本人類学会編(1956)『鎌倉材木座発見の中世遺跡とその人骨』より改変して引用]
写真4.鎌倉材木座No.27頭蓋骨左側面観(反っ歯・歯槽性突顎)[日本人類学会編(1956)『鎌倉材木座発見の中世遺跡とその人骨』より改変して引用]
この報告は、1956年に『鎌倉材木座発見の中世遺跡とその人骨』として、岩波書店から出版されました。報告書は、当初、東京大学理学部人類学教室編として出版される予定でしたが、直前に日本人類学会編として出版するように進言したと、日本人類学会会長(当時)の長谷部言人[1882-1969]により書かれています。
東京の鍛冶橋出土室町時代人骨とこの鎌倉材木座出土鎌倉時代人骨を発見した事で、鈴木 尚は、中世時代人骨が他の時代の人骨と異なる形質を持っていると確信し、頭の形は時代と共に変化すると発表します。当時、日本の人類学会では頭の形が時代と共に変化するという意見は全くとりいれられず、鈴木 尚は孤立しました。しかし、その後、日本各地で出土した中世時代人骨がこの鎌倉材木座出土人骨と同様の形質を持つことが判明し、今では、鈴木 尚の説が正しかったことが証明されています。
*鎌倉材木座出土人骨に関する資料として、以下の文献を参考にしました。
- 日本人類学会編(1956)『鎌倉材木座発見の中世遺跡とその人骨』、岩波書店
- 鈴木 尚(1960)「鎌倉の人骨群」『骨』、学生社、pp.120-143
- 鈴木 尚(1962)「Ⅱ.鎌倉時代の戦士」『日本人の骨』、岩波書店(岩波新書)、pp.36-52
- 鈴木 尚(1996)「6.鎌倉材木座の中世人骨群」『改訂新版・骨』、学生社、pp.120-142














![日本の人類学者51.小金井良精(Ryosei KOGANEI)[1859-1944]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0a/97/46d972234646556faff44f0f58d1bae6.jpg)