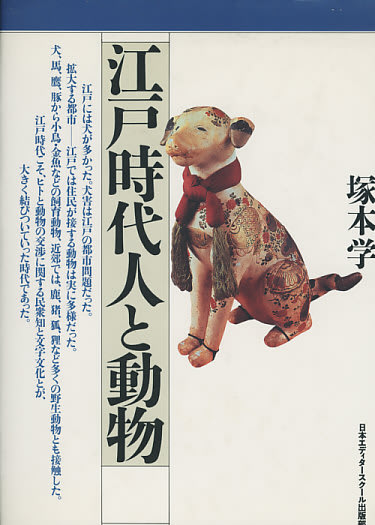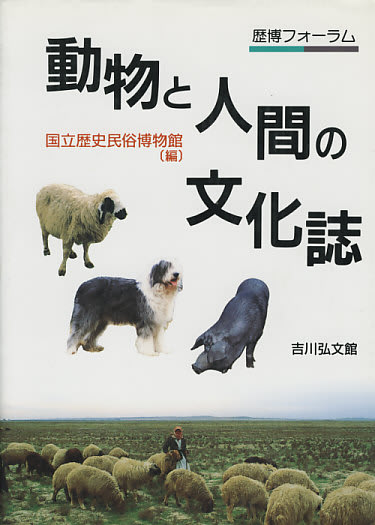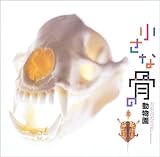| 第四紀試料分析法 価格:¥ 12,600(税込) 発売日:1993-09 |
この本は、日本第四紀学会編により、試料調査法や試料分析法について書かれたものです。1993年に、東京大学出版会から出版されました。
本書の内容は、以下のように、全2冊からなります。
- 試料調査法
- 研究対象別分析法
第1巻の「試料調査法」には、脊椎動物の試料調査法が書かれています。
- 2.6.1 魚類(高橋正志・中島経夫)
- 2.6.2 両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類(河村善也・樽野博幸)
第2巻の「研究対象別分析法」には、脊椎動物の分析法が書かれています。
4.1 魚類
- 4.1.1 耳石(高橋正志)
- 4.1.2 鱗(小寺春人)
- 4.1.3 咽頭歯(中島経夫)
4.2 両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類
- 4.2.1 歯・骨の形態(河村善也・樽野博幸)
- 4.2.2 微細構造(小澤幸重)
本書は、調査法や分析法について書かれた事典ですが、前出の部分は動物考古学にも大変、参考になります。