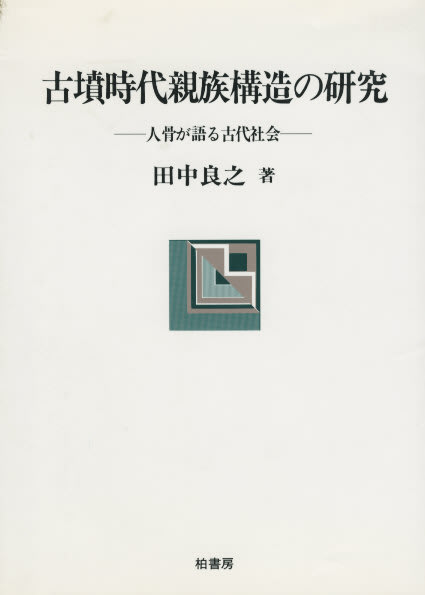|
北京原人物語 価格:¥ 2,520(税込) 発売日:2005-03 |
 |
Dragon Bone Hill: An Ice-Age Saga of Homo Erectus 価格:¥ 3,451(税込) 発売日:2004-02-16 |
この本は、アメリカのロス医科大学のノエル・ボアズ[Noel T. BOAZ]さんとアイオワ大学のラッセル・ショホーン[Russell L. CIOCHON]さんが、北京原人について書いた本です。原書は2004年に出版されており、タイトルは、『Dragon Bone Hill』で、これは、北京原人が発見された周口店の龍骨山を意味します。長野 敬さんと林 大さんの翻訳で、2005年に青土社から出版されました。ただ、ショホーンさんというのは、私が聞いた感じではショハーンだと思います。
本書の内容は、以下のように全9章からなります。
- 龍骨山の骨
- 竜の再主張
- 進化上の意義: 巨人か遺伝子か
- 第三の機能: 北京原人の謎の頭蓋についての仮説
- なりかけの人類による適応行動
- ホモ・エレクトゥスの時代と気候
- 龍骨山に見られるヒトらしさ: 脳、言語、火、人肉食
- 究極の疑問を解決する: ホモ・エレクトゥスの始まりと終わり
- 新しい仮説の検証
この北京原人は、1920年代から1930年代にかけて発見され、1941年の太平洋戦争勃発の前夜に行方不明になったまま、未だにその行方がわからない北京原人の物語です。本書では、この北京原人のみならず、今では、ホモ・エレクトスと呼ばれている化石人類について、アフリカ・西アジア・インドネシア出土のものも合わせて解説しています。