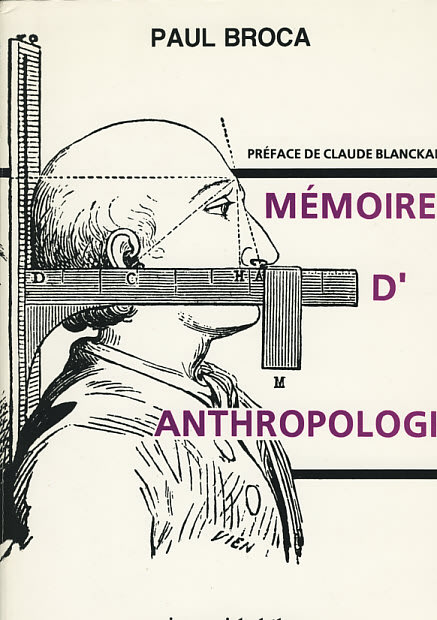オスマン・ヒル(Osman HILL)[1901-1975](Journal of Anatomy, 120巻第2号より改変して引用)
ウィリアム・チャールズ・オスマン・ヒル(William Charles Osman HILL)は、1901年7月13日に生まれました。やがて、バーミンガム大学医学部に入学し、1924年に卒業します。卒業後、母校の動物学講師に就任しましたが、1925年には医学博士号を取得し、解剖学の講師に就任しました。
やがて、ヒルに転機が訪れました。1930年にセイロン医科大学[現・コロンボ大学医学部]の解剖学主任教授として赴任したのです。ヒルは、ここで、比較解剖学やヴェッダ人の研究に没頭しました。特に、南アジアや東南アジアに生息する霊長類の研究を行っています。ヒルは、解剖の技術に優れており、かつ、スケッチに優れていたと言われています。
ヒルに、次の転機が訪れました。1945年、ヒルは帰国するとエディンバラ大学の人類学リーダー(Reader)に就任しました。1950年には、ロンドン動物学協会に解剖学者として勤務し、1962年まで務めています。このロンドン動物園では、リチャード・オーウェン(Richard OWEN)[1804-1892]の時代から、獣医ではなく解剖学者が動物園で死亡した動物を解剖し、その死因を探り、標本を保存していました。ところが、ここで悲劇が起きました。1962年にヒルが辞任すると、そのポストは閉鎖され、それまで保存されていた標本が捨てられてしまったのです。ヒルは、1962年にアメリカのヤーキース霊長類研究センターの副所長に就任し、1969年までそのポストに留まりました。ヒルが後に収集した霊長類の資料は、現在、王立外科学校に収蔵されています。
ヒルは、生涯に248本の論文や本を残しましたが、その中でも代表的な仕事は、1953年から1974年にかけて霊長類の比較解剖や分類について書いた全8巻からなる大著でした。
- HILL, Osman (1953)『Primates Comparative Anatomy and Taxonomy I.Strepsirhini』、Edinburgh University Press
- HILL, Osman (1955)『Primates Comparative Anatomy and Taxonomy II.Haplorhini: Tarsioidea』、Edinburgh University Press
- HILL, Osman (1957)『Primates Comparative Anatomy and Taxonomy III.Pithecoidea Platyrrhini』、Edinburgh University Press
- HILL, Osman (1960)『Primates Comparative Anatomy and Taxonomy IV.Cebidae: PartA』、Edinburgh University Press
- HILL, Osman (1962)『Primates Comparative Anatomy and Taxonomy V.Cebidae: PartB』、Edinburgh University Press
- HILL, Osman (1966)『Primates Comparative Anatomy and Taxonomy VI.Catarrhini Cercopithecoidea: Cercopithecinae』、Edinburgh University Press
- HILL, Osman (1974)『Primates Comparative Anatomy and Taxonomy VII.Cynopothecinae(Cercocebus, Macaca, Cynopithecus)』、Edinburgh University Press
- HILL, Osman (1970)『Primates Comparative Anatomy and Taxonomy VIII.Cynopithecinae(Papio, Mandrillus, Theropithecus)』、Edinburgh University Press
これらの本には、多くの写真や挿絵が掲載されていますが、挿絵のほとんどは、妻のイヴォンヌ・ヒル(Yvonne HILL)が描いたそうです。元々、このシリーズは、全9巻で完結する予定でしたが、未完に終わってしまいました。
1975年1月25日、オスマン・ヒルは、73歳でこの世を去りました。第9巻の原稿は完全ではありませんでしたが、遺稿が残されており、周囲の人々は妻のイヴォンヌが引き継いで完成させることを期待していました。ところが、そのイヴォンヌも1976年に死去したために未完となってしまったのです。
ヒル夫妻は、夫唱婦随で霊長類研究に一生を捧げました。なお、ヒルは、エリマキキツネザル・トクモンキー・スレンダーロリスの亜種を記載しています。また、ヒルの名前は、マンガベイの一種の学名として残されています。