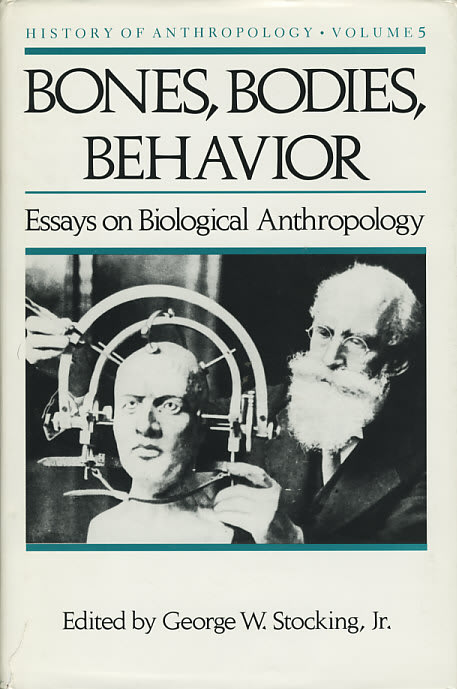この本は、ケニアの古人類学者、リチャード・リーキー(Richard LEAKEY)[1944-]さんの自叙伝です。原題は、『One Lefe』で、直訳すると、「ある人生」となるでしょうか。1984年に、Salem Housen社より出版されました。リチャード・リーキー、弱冠40歳の年です。
リチャード・リーキーさんは、著名な古人類学者、ルイス・リーキー(Louis LEAKEY)[1903-1972]さんと著名な先史人類学者、メアリー・リーキー(Mary LEAKEY)[1913-1996]さんとの間に2男として生まれています。
本書の内容は、以下のように、全14章からなります。
- An African Childhood
- Go and Find Your Own Bone
- Caught in my Own Trap
- Encounters with Lions
- Safari Business
- Making my Mark
- Out of my Father's Shadow
- In Conflict Again
- Camels at Koobi Fora
- Making Changes
- The Discovery of 1470
- Filming, Finding and Dating
- Fighting for Time
- The End of One Life
私も、1986年にケニアを訪問した際に、当時、ケニア国立博物館館長だったリチャード・リーキーさんにお会いしたことがあります。当時は、世界で最も有名な古人類学者の一人でした。本書は、1984年に出版されていますが、その後、1989年には野生動物保護センターの所長に、1990年にはケニア野生動物サービスの長官になっています。この時には、密猟者を厳しく取り締まったことで有名です。また、1989年には、押収した密猟者による象牙12トンを焼いたことでも話題になりました。
1993年には、自身で操縦していた小型セスナ機が墜落し、両足の下部を切断するという事故に巻き込まれました。現在は、義足で元気に歩いているそうです。1994年には、ケニア野生動物サービスの長官を辞任しました。1999年には内閣官房長に就任しましたが、2001年には辞任しています。現在は、ニューヨーク州立大学ストーニー・ブルック校の、トゥルカナ盆地センターの所長兼教授として活躍しています。ちなみに、このセンターには、奥様の古人類学者、ミーヴ・リーキー(Meave LEAKEY)さんと次女のルイーズ・リーキー(Louise LEAKEY)さんもスタッフになっています。