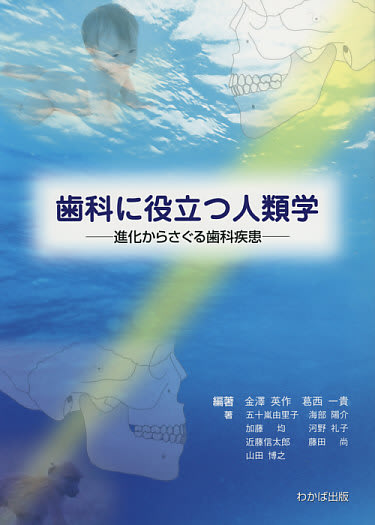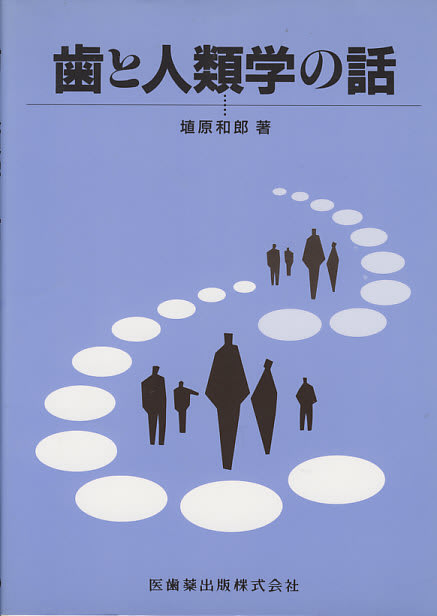この本は、日本大学松戸歯学部解剖学第1講座教授の金澤英作先生が、歯の特徴・過去と現在の日本人の歯・世界の民族の歯等について書かれたものです。私は、著者の金澤英作先生から寄贈していただきました。2011年10月17日に、わかば出版から出版されました。アマゾンで検索しましたが、ヒットしませんでしたのでリンクさせていません。
以下にリンクした、デンタルブックセンター・シエン社から購入することができます。
本書の内容は、以下のように、全4章からなります。
第1章.ルーツ探しの道具
- 歯の名称の基本的知識
- それぞれの歯の特徴
- 歯の内部構造
- 歯の形態学
- 世界の多様な集団と歯
第2章.日本人の歯
- 旧石器時代
- 縄文時代
- 弥生時代
- 古墳時代
- 中世・鎌倉時代
- 近世・江戸時代
- 近代から現代へ
第3章.日本人の歯のルーツ
- モンゴロイド・デンタル・コンプレックス
- スンダドントとシノドント
- アジア仁の起源をめぐる論争
- 縄文人の歯のルーツ
- 弥生人の歯のルーツ
- 民族のるつぼ中国
- フィリピンの人
第4章.太平洋の親類たち
- 最初の航海者
- メラネシア
- ポリネシア
- ミクロネシア
- ニューギニア
- オーストラリア
- 太平洋民族の歯の比較
本書は、新書サイズの本ですが、歯についてわかりやすく系統的に書かれており、歯学部の学生や研究者のみならず、人類学・法医人類学の分野にも参考になります。特に、著者の金澤英作先生ご自身が調査されてきた、太平洋諸島の人々の歯について書かれている点が他の類書と異なる点です。