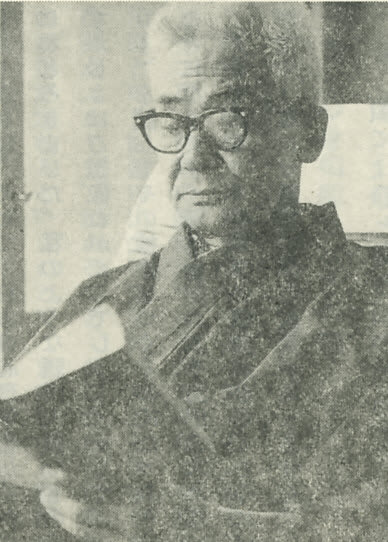鹿野忠雄(Tadao KANO)[1906-1945][山崎柄根(1992)『鹿野忠雄』、平凡社のp.187の写真を改変して引用](以下、敬称略)
鹿野忠雄は、1906年、鹿野直司と欽との間に5人兄妹の長男として東京に生まれました。子供の頃は、昆虫採集に熱中し野外調査の基本を身につけました。1921年に台湾へ旅行し、昆虫採集をする内に、昆虫から民族に興味が移ったといわれています。やがて、開成中学校を卒業すると、1925年に台北高校へ入学しました。この台北高校には、後輩として、将来民族考古学者として活躍する、国分直一[1908-2005]と出会っています。ちなみに、国分直一は、台北高校卒業後、京都帝国大学文学部史学科を卒業します。
1928年、台北帝国大学文政学部に、土俗人種学教室が設置され、移川子之蔵[1884-1947]が教授として赴任し、スタッフには、宮本延人[1901-1989]が赴任しています。この教室には、馬淵東一[1909-1988]が学生として入学しました。ちなみに、学生はこの馬淵だけだったそうです。
1929年に台北高校を卒業した鹿野忠雄は、1920年に東京帝国大学理学部地理学科に入学します。大学では、生物地理学を専攻しました。この頃、鹿野は、同じ理学部の人類学教室に出入りしていたそうです。1933年に東京帝国大学を卒業すると、母校の大学院に進学しました。
1934年には、台湾総督府の嘱託職員として台湾に渡り、民族学調査を継続しています。1936年には、渋沢敬三[1896-1963]の知遇を得ます。渋沢敬三は、渋沢栄一[1840-1931]の孫で、日本銀行総裁や大蔵大臣を歴任した政治家ですが、私費を投じてアチックミューゼアムを設立し民族学や民俗学の研究を行っていました。その後、日本常民文化研究所や民族学博物館へとなり、現在は、神奈川大学日本常民文化研究所や国立民族学博物館に発展解消されています。渋沢敬三は、多くの民族学者・民俗学者・考古学者・人類学者に財政援助をしたことで有名な人物です。
1937年、鹿野忠雄は、渋沢敬三の財政援助を受け、パイワン族やヤミ族の調査を行っています。1938年には、東京人類学会(現・日本人類学会)で発表も行っています。1940年に、丹那静子と結婚しました。1941年には、京都帝国大学理学部から『次高山彙の動物地理学的研究』で、理学博士号を取得しています。なぜ、母校の東京帝国大学からでなかったのかという事情は、母校の恩師・辻村太郎[1890-1983]との確執があったと言われています。しかし、辻村太郎にすれば、地理学から民族学に興味を移している鹿野忠雄を快く思わなかったのは仕方がないことかもしれません。
1942年7月、鹿野忠雄は陸軍の嘱託としてフィリピンのマニラに赴任します。ここで、鹿野は、フィリピン大学の人類学者・バイヤー(ベイヤー)が捕虜としてサント・トーマス大学で拘束されていることを知り、軍部と交渉して救出することに成功しました。ここに出てくるバイヤー(ベイヤー)とは、ヘンリー・バイヤー(ベイヤー)(Henry Otley BEYER)[1883-1966]のことです。バイヤー(ベイヤー)は、アメリカのアイオワ州出身で、デンヴァー大学にて化学専攻で卒業後、フィリピンのルソン島でで教師として務めます。ハーヴァード大学大学院で人類学を専攻する内、フィリピン博物館の館長に就任しました。やがて、1914年にはフィリピン大学の人類学講師に就任し、1925年に人類学部長兼教授となります。
1941年12月に、第16師団・陸軍軍医大尉として召集され、フィリピンのレイテ島に赴任していた元京都帝国大学の人類学者・三宅宗悦[1905-1944]も、たびたび、このバイヤー(ベイヤー)の元を訪問しています。鹿野忠雄は、フィリピンで、大学の標本・資料・図書を疎開させる仕事をしました。保管していたビルはその後爆撃を受け、図書は焼失したそうですが、標本は奇跡的に無事だったそうです。バイヤー(ベイヤー)は、戦後、鹿野の努力に敬意を払ったと言われています。
1943年3月、帰国した鹿野忠雄は台湾の民族学及び先史学をまとめた『台湾原住民族図譜:ヤミ族編』の原稿執筆に専念します。ちなみに、それより遡った1935年には、台北帝国大学の移川子之蔵・宮本延人・馬淵東一により、『台湾高砂族系統所属の研究』が出版されていました。
1944年3月、鹿野忠雄は陸軍専任嘱託に就任し、同年7月に北ボルネオへ赴任しました。ここで、鹿野は、金子総平と合流し2人で奥地へ調査に赴きます。ところが、1945年5月頃、第37軍に現地召集されましたが、本人達は、奥地に入っていたためそのことをずいぶんと後で知ったそうです。1945年7月15日の目撃情報を最後に、2人の消息はぷっつりと途絶えました。
鹿野忠雄と金子総平の2人は、現地住民の反乱に巻き込まれて亡くなったとか、あるいは憲兵により撲殺されたという説もありますが、未だにその死は謎に包まれています。生前、鹿野は国分直一に、ニューギニアあたりで死ぬかもしれないと漏らしたことがあったそうです。恐らく、調査は常に危険を伴っていたのでしょう。しかし、鹿野は自らが予言したニューギニアではなく、北ボルネオで消息を絶ちました。
鹿野忠雄の著作は、1941年から1952年に出版されました。1941年に出版された本を除くと、本人が出版されたこれらの本を見ることはありませんでした。しかし、鹿野の精神は、台湾時代に行動を共にしていた国分直一に受け継がれ、国分は民族考古学を専門として多くの業績を残しています。
- 鹿野忠雄(1941)『山と雲と蕃人と:台湾高山行』、中央公論社
- KANO, T. [鹿野忠雄]& SEGAWA, K.[瀬川幸吉] (1945)『IIllustrated Ethnography of Fomosan Aborigines, The Yami Tribe』
- 鹿野忠雄(1946)『東南亜細亜先史学民族学研究1』、矢島書房
- 鹿野忠雄(1952)『東南亜細亜先史学民族研究2』、矢島書房

*鹿野忠雄に関する資料として、以下のものを参考にしました。
- 山崎柄根(1988)「18.鹿野忠雄:比較文化史に示した高い視点」、『文化人類学群像3.日本編』(綾部恒雄編著)、アカデミア出版会、pp.353-372
- 山崎柄根(1992)『鹿野忠雄:台湾に魅せられたナチュラリスト』、平凡社