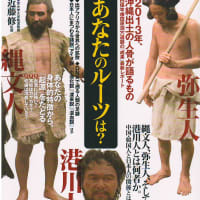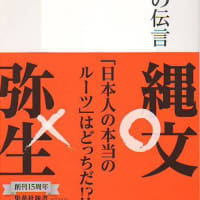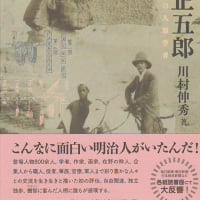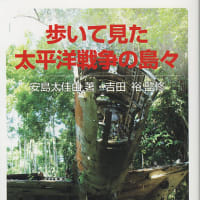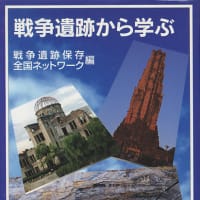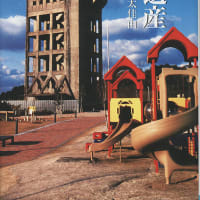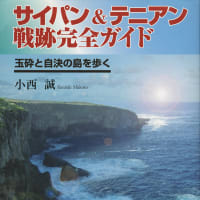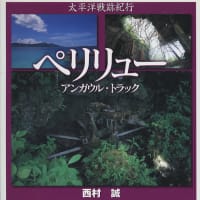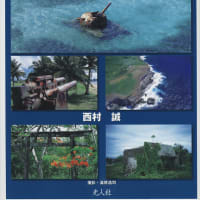直良信夫(Nobuo NAORA)[1902-1985][明石市立博物館(2002)より改変して引用](以下、敬称略)
直良信夫は、1902年1月10日に、大分県臼杵町(現・臼杵市)で、村本幸一・シメの次男として生まれました。
1917年に、昼間は上野保線事務所で給仕として働きながら、早稲田大学付属早稲田工手学校夜間部(現・早稲田大学芸術学校)に入学します。しかし、身体をこわしたため、早稲田工手学校は中退しました。1918年には、岩倉鉄道学校工業化学科夜間部(現・岩倉高等学校)に入学し、1920年に同校を卒業します。卒業後、農商務省臨時窒素研究所(現・産業技術総合研究所)に勤務しました。
この頃、著名な歴史学者の喜田貞吉[1871-1939]と出会い、土器の化学分析を行っています。しかし、結核になったため農商務省臨時窒素研究所を退職し、故郷で療養するために1923年8月31日に東京駅から夜行列車に乗り込みました。ところが、その翌日の1923年9月1日には関東大震災が発生します。この9月1日に、直良信夫は、兵庫県明石駅で途中下車しました。ここには、かつての恩師である直良 音[1891-1965]が住んでいました。
直良 音は、1891年11月14日に、島根県簸川郡今市町(現・出雲市)で、直良杏次郎・モンの長女として生まれました。やがて、1916年に奈良女子高等師範学校(現・奈良女子大学)を卒業すると、臼杵町立実科高等女学校(現・大分県立臼杵高等学校)に勤務し、1917年に島根県立浜田高等女学校(現・島根県立浜田高等学校)に転勤し、1922年に兵庫県立姫路高等女学校(現・兵庫県立姫路東高等学校と兵庫県立姫路西高等学校)に転勤していました。直良信夫と直良 音は、臼杵で知り合いだったそうで、直良 音は「世界一偉い人になりなさい。」と励ましていたそうです。その後、直良信夫は、東京に残した恋人の安否を気づかい上京しますが、行方はわかりませんでした。直良 音は、1924年に兵庫県立姫路高等女学校を退職し、兵庫県明石高等女学校(現・兵庫県立明石南高等学校)に転職します。1925年、二人は結婚しました。村本信夫は、直良信夫に改姓します。
1926年、直良信夫は、「直良石器時代文化研究所」を開設し、研究成果をコンニャク版印刷で印刷し研究を続けていました。やがて、大きな発見が訪れます。1931年4月18日、直良信夫は、明石市西八木海岸で、後に「明石原人」と呼ばれる左寛骨を発見したのです。
明石原人の左寛骨[Nishiyagi(西八木)・18.4.31.(昭和18年4月31日)]
直良信夫は、早速、この明石原人の左寛骨を、東京帝国大学理学部人類学教室の松村 瞭[1880-1936]に送ります。1931年5月5日、松村から手紙が届きます。その手紙には、「人骨に間違いなく、死亡年齢は約16歳から17歳。しかし、世界の化石人類で寛骨はあまり出土していないため比較するのが困難である。」とありました。当時の日本は、旧石器という時代自体が存在しないと考えられていた時代です。
1932年、直良信夫は、早稲田大学理工学部の徳永重康[1874-1940]の個人助手となり、獣類化石研究室という看板を掲げて、獣骨の整理を行います。1938年に早稲田大学理工学部採鉱冶金学科図書室に勤務し、1944年に早稲田大学専門部工科鉱山地質学科で地質学や古生物学を講義し、1945年には早稲田大学理工学部非常勤講師に就任しました。やがて、悲劇が訪れました。1945年5月25日、東京大空襲により、自宅が全焼し明石原人の骨も焼失してしまったのです。
1948年7月、元東京帝国大学理学部人類学教室の長谷部言人[1882-1969]が、『人類学雑誌』第61巻第1号に、「明石市附近西八木最新世前期堆積出土人類腰骨(石膏型)の原始性に就いて」という論文を発表し、ニッポナントロプス・アカシエンシス(Nipponanthropus akasiensis)という通称を提示し、原人級であると鑑定しました。最初に人骨を鑑定した松村 瞭は1936年に急逝していましたが、精巧な石膏模型を作成し写真も撮影していたのです。長谷部言人は、この石膏模型と写真で研究しました。1948年10月には、長谷部言人を中心として明石原人が発見された西八木海岸の発掘調査が実施されましたが、何も発見されません。直良信夫によると、発掘調査が行われた地点は、発見地点とは異なる場所だったそうです。
なお、翌年の1949年には、群馬県岩宿遺跡で相沢忠洋[1926-1989]等により旧石器も発見され、日本にも旧石器時代があったことが証明されました。
直良信夫は、1956年、早稲田大学理工学部専任講師に就任しました。翌年の1957年には、『日本古代農業発達史』により、早稲田大学文学部から文学博士号も取得します。そして、1960年には、早稲田大学理工学部資源工学科教授に就任しました。直良信夫は、58歳になっていました。
私生活では、長年連れ添った妻の直良 音が1965年5月5日に死去します。1966年12月には、直良 音のいとこの春江と再婚しました。1972年3月に、直良信夫は早稲田大学を定年退職します。他大学へ再就職の誘いがあったそうですが、健康に自信が無い直良信夫は、1973年10月に妻の故郷である島根県出雲市へ転居しました。
明石人骨は、さらに話題を提供することになりました。1982年10月15日、東京慈恵会医科大学で開催された第36回日本人類学会・日本民族学会連合大会で東京大学理学部人類学教室(当時)の遠藤萬里と獨協医科大学解剖学教室(当時)の馬場悠男が連名で、明石原人は1万年以内の人類であるという学会発表を行います。それは、明石原人が発見された1931年当時から約50年経過した時点では、すでに世界各国で様々な段階の寛骨が発見されており、形態の比較検討が可能になっていたからです。
その後、この明石原人を巡っては、愛知学院大学(当時)の吉岡郁夫やオーストラリア国立大学(当時)の直良博人等と大きく論争が行われました。直良博人は、直良信夫の長男で生物学者です。しかし、化石化していたいないという論争や形態を巡る論争は、やがて終息しました。やはり、実物が無いと年代測定ができないという制約があったのです。
直良信夫は、様々な分野を研究しましたが、人類学に関連した研究は、以下の通りです。
- 1931年:明石人骨を発見。
- 1950年:葛生人骨を発見。
- 1951年:日本橋人骨を発見。
- 1970年:夜見ヶ浜人骨を発見。
直良信夫は、膨大な著書と論文を残しています。代表的な著書は、以下の通りです。
- 直良信夫(1954)『日本旧石器時代の研究』、寧楽書房
- 直良信夫(1956)『日本古代農業発達史』、さ・え・ら書房
- 直良信夫(1959)『人類発達史』、校倉書房
- 直良信夫(1965)『古代人の生活と環境』、校倉書房
- 直良信夫(1965)『日本産狼の研究』、校倉書房[このブログで紹介済み]
- 直良信夫(1968)『狩猟』、法政大学出版局
- 直良信夫(1970)『日本および東アジア発見の馬歯・馬骨』、日本中央競馬会[このブログで紹介済み]
- 直良信夫(1972)『古代遺跡発掘の脊椎動物遺体』、校倉書房[このブログで紹介済み]
- 直良信夫(1973)『古代遺跡発掘の家畜遺体』、日本中央競馬会弘済会[このブログで紹介済み]
- 直良信夫(1985)『日本旧石器人の探究』、六興出版
直良信夫は、1985年11月2日に、83歳で死去しました。死去の前日の11月1日には、縁のある明石市文化功労賞を受賞しています。苦学しながら努力を重ねて、早稲田大学教授となった波乱万丈の人生だと言えるでしょう。研究した範囲は、考古学・古生物学・動物考古学・動物学・生態学・人類学と幅広く、「日本で最後の博物学者」と呼ばれています。なお、直良信夫の遺骨は、1985年11月8日に、神奈川県秦野市にある太岳院に納骨されました。戒名は、「秋成院洪化清信居士」です。
直良信夫の大分県臼杵市の生家は、現在、「直良信夫顕彰記念館」として保存公開されています。直良信夫の波乱万丈な人生に興味を抱いた松本清張[1909-1992]は、1955年に直良信夫をモデルにして小説「石の骨」を発表します。また、直良信夫と明石原人を題材として、2004年から2008年にかけて、劇団民藝が『明石原人:ある夫婦の物語』を上演しました。小説や劇団のテーマになるほど、直良信夫の人生は波瀾万丈の人生だったということでしょう。
*直良信夫に関する資料として、以下の文献を参考にしました。
- 直良信夫(1981)『学問への情熱』、佼成出版会
- 高橋 徹(1984)『明石原人の発見』、社会思想社
- 金子浩昌(1986)「直良信夫先生を偲んで」『人類学雑誌』、第94巻第3号、pp.269-273
- 春成秀爾(1994)『「明石原人」とは何であったか』、NHKブックス
- 直良三樹子(1995)『見果てぬ夢「明石原人」』、時事通信社
- 明石市立文化博物館(2002)『「明石原人」の発見者・直良信夫生誕100年展』、明石市立文化博物館
- 白崎昭一郎(2004)『「明石原人」と直良信夫』、雄山閣












![日本の人類学者51.小金井良精(Ryosei KOGANEI)[1859-1944]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0a/97/46d972234646556faff44f0f58d1bae6.jpg)