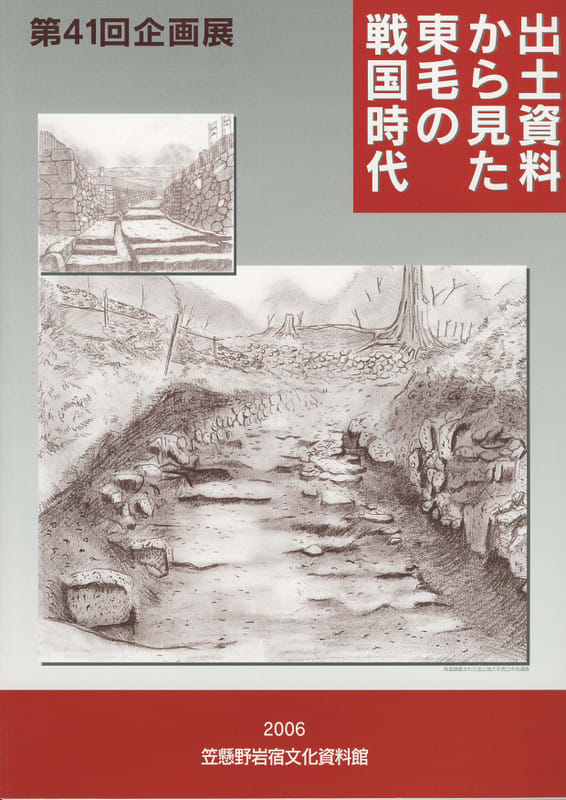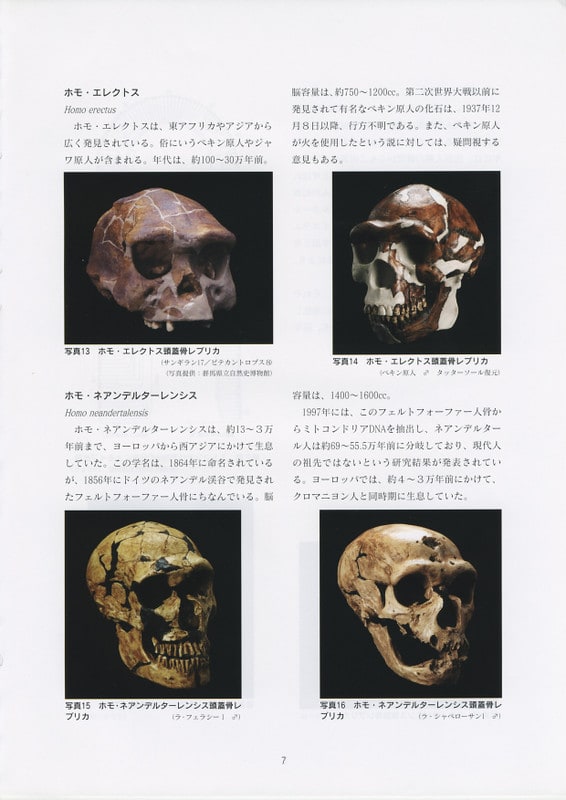『日本人のルーツを探る』展図録表紙[笠懸野岩宿文化資料館](*画像をクリックすると、拡大します。)
『日本人のルーツを探る:日本人類史の検討』展は、第33回企画展として、2001年9月29日~同年11月18日に、笠懸野岩宿文化資料館で開催されました。この博物館は、相沢忠洋[1926-1989]さんが、1946年に岩宿で旧石器を発見し、1949年に明治大学による発掘調査で確かめられた岩宿遺跡のすぐそばにあります。1992年に「笠懸野岩宿文化資料館」として開館し、合併に伴い、2006年に「岩宿博物館」と名称が変更されました。
この図録では、多くの頁に執筆させていただきましたので、3回にわたりご紹介します。今回は、第Ⅱ章「日本人類史の検討」の内、「2.日本更新世人類化石の検討」(p.18~p.22)と「4.縄文時代の人類」(p.25)をご紹介します。
日本更新世人類は、葛生(栃木県)[レプリカ]・泊洞穴(富山県)[レプリカ]・浜北(静岡県)[レプリカ]・三ヶ日(静岡県)[レプリカ]・牛川(愛知県)[レプリカ]・明石(兵庫県)[レプリカ・オリジナル化石は1945年の東京大空襲の際に焼失]・聖嶽(大分県)[レプリカと表面採集人骨オリジナル]・港川(沖縄県)[レプリカ]・ピンザアブ(沖縄県)[レプリカ]を展示しました。この図録の内、p.18の地図に掲載した多古遺跡は、後に古墳時代人に同定されていますので、注意が必要です。

『日本人のルーツを探る』展図録目次(*画像をクリックすると、拡大します。)

「日本更新世人類化石の検討」・『日本人のルーツを探る』展図録p.18[註:地図の多古は、後に古墳時代人であることが判明。](*画像をクリックすると、拡大します。)

「日本更新世人類化石の検討」・『日本人のルーツを探る』展図録p.19(*画像をクリックすると、拡大します。)

「日本更新世人類化石の検討」・『日本人のルーツを探る』展図録p.20(*画像をクリックすると、拡大します。)

「日本更新世人類化石の検討」・『日本人のルーツを探る』展図録p.21(*画像をクリックすると、拡大します。)

「日本更新世人類化石の検討」・『日本人のルーツを探る』展図録p.22(*画像をクリックすると、拡大します。)

「日本更新世人類化石の検討」・『日本人のルーツを探る』展図録p.23(*画像をクリックすると、拡大します。)
縄文時代の人類は、大森貝塚出土四肢骨のレプリカと蝦島貝塚出土男女のオリジナル頭蓋骨を国立科学博物館から借用して展示しました。

「日本更新世人類化石の検討」・『日本人のルーツを探る』展図録p.25(*画像をクリックすると、拡大します。)

「日本更新世人類化石の検討」・『日本人のルーツを探る』展図録p.26(*画像をクリックすると、拡大します。)
*以下は、「Ⅱ.日本人類史の検討・2.日本更新世人類化石の検討と4.縄文時代の人類」・『日本人のルーツを探る』展図録p.18~p.22・p.25~p.26のPDF(1.16MB)です。
「IM2001-2.pdf」をダウンロード