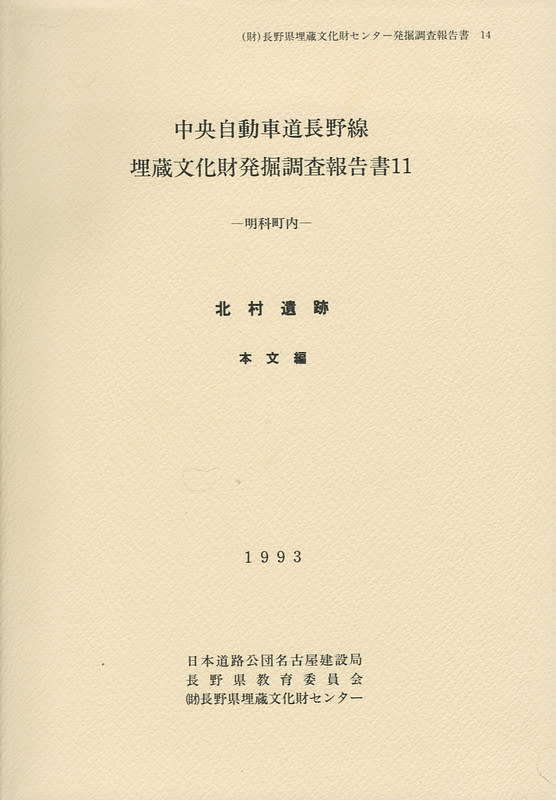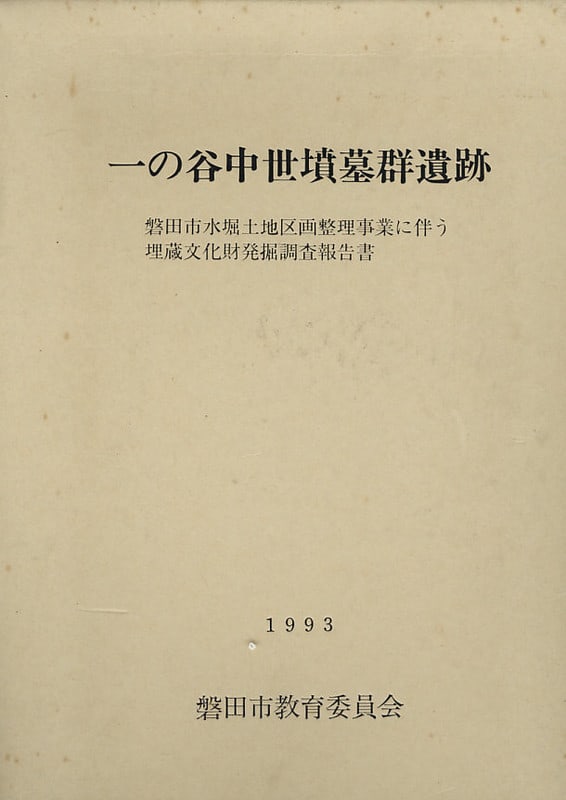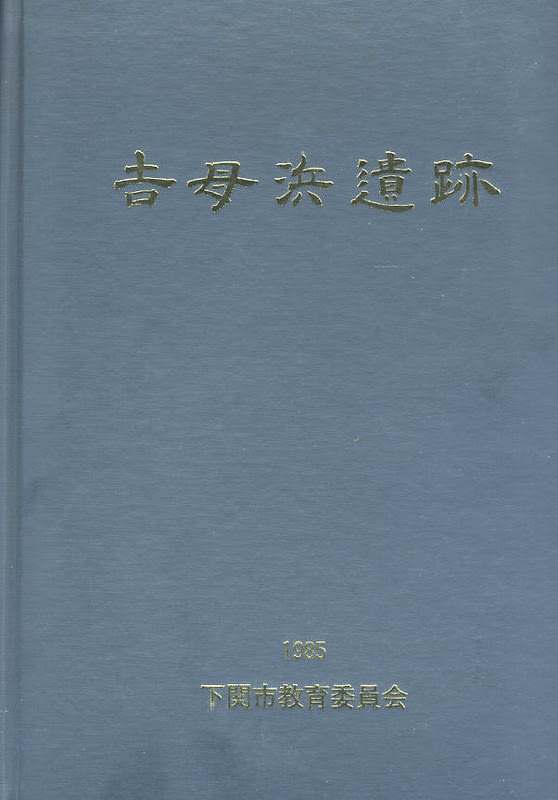この報告書『由比ヶ浜南遺跡』は、神奈川県鎌倉市に所在する、中世の埋葬遺跡である由比ヶ浜南遺跡の発掘調査報告書です。2001年に、由比ヶ浜南遺跡発掘調査団と鎌倉遺跡調査会による編で出版されました。アマゾンで検索しましたが、ヒットしませんでしたのでリンクさせていません。
本報告書の内容は、以下のように、全4分冊からなります。
◎第1分冊:本分編
- 調査地の位置と周辺の環境
- 調査の経緯
- 検出された遺構と遺物
- まとめと考察
◎第2分冊:分析編1
- 由比ヶ浜南遺跡の単体埋葬遺構出土人骨について(平田和明・奥 千奈美・星野敬吾・塘 総一郎・高橋慎一)
- 由比ヶ浜南遺跡出土の動物遺体(西本豊弘・鵜澤和宏・太田敦子・姉崎智子・樋泉岳二)
◎第3分冊:分析編2
- 神奈川県鎌倉市由比ヶ浜南遺跡出土の中世人骨(松下孝幸)
- 鎌倉市由比ヶ浜南遺跡出土中世人骨の埋葬と個体数および受傷人骨(松下孝幸)
- 由比ヶ浜南遺跡の花粉化石(鈴木 茂・新山雅広・松葉礼子)
- 由比ヶ浜南遺跡のプラント・オパール(鈴木 茂)
- 由比ヶ浜南遺跡の古環境(鈴木 茂)
- 鎌倉市由比ヶ浜南遺跡出土木材樹種同定結果(松葉礼子)
- 由比ヶ浜南遺跡の砂層堆積環境(上本進二・土屋浩美)
- 目溜り遺構出土の貝類(小島奈々子)
- 出土遺物法量表
◎第4分冊:写真図版編