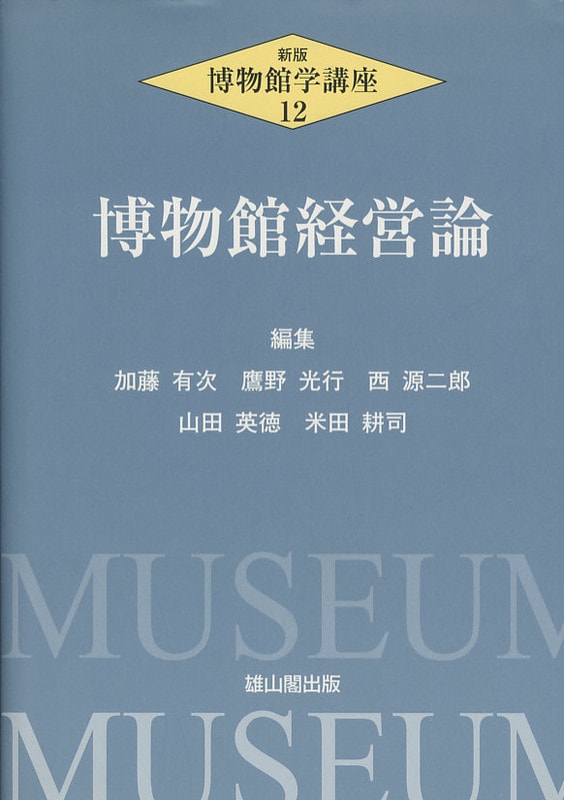この『屋根裏の恐竜たち』は、副題に「世界最大の自然史博物館物語」とあるように、アメリカのニュー・ヨークにある、アメリカ自然史博物館の物語です。ダグラス・プレストンさんが書いた、原題『Dinosaurs in the Attic』を、野中浩一さんが翻訳して1991年に心交社から出版されました。
このアメリカ自然史博物館は、1869年に開館した、世界最大の自然史博物館です。毎年、世界中から約300万人もの入館者を惹きつけています。収蔵品は約3,600万点・科学者は約200人・その他の職員約700人という、文字通りの巨大な博物館です。
この博物館を舞台にして製作された映画に、2006年にアメリカで、2007年に日本で公開された映画、『ナイト・ミュージアム』(夜の博物館という意味)があります。
本書の内容は、以下のように、全2部18章に分かれます。
第1部.歴史(1~9)・第2部.博物館大旅行(10~18)
- むかしの博物館の姿
- ビッグモア教授の博物館
- 最初の大探検隊
- 世界のてっぺんの探検
- 北極のアトランティスを求めて
- 大恐竜たちの「ゴールドラッシュ」
- アフリカの最奥地で
- 外モンゴル地方の化石
- 30年代以降
- 骨の図書館
- 哺乳類
- 昆虫類
- 両生類と爬虫類
- 鳥類
- 人類学
- ハリー・シャピロと北京原人
- 隕石
- 鉱物と宝石
個人的には、骨格標本を作製する苦労を描いた第2部第10章の「骨の図書館」と、かつてこの博物館に在籍した人類学者のハリー・シャピロの活躍を描いた第2部第16章の「ハリー・シャピロと北京原人」がお気に入りです。私も、この博物館は何回か訪問していますが、毎回、「世界一」という冠がつく標本に驚かされます。