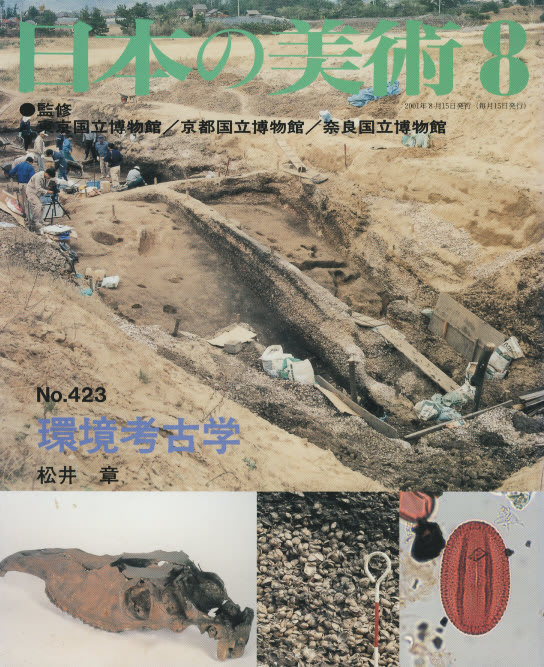|
Palaeopathology |
この本は、ベルギーの産業医のポール・ジャンセン[Paul JANSSENS]さんが、古病理学について書いた本です。1970年に、John Bakerから出版されました。少し古い本ですが、当時は古病理学に関する本はあまりありませんでした。副題は、「古代人の病気と怪我」となっています。私も、イギリス留学中に購入しています。
本書の内容は、以下のように全27章からなります。
- 定義
- 気候・経済・環境の影響
- 病気の定義
- 第四紀の年代
- 標本
- 古病理学の重要性
- 出土人骨
- 外傷
- 石器による傷
- 先史時代の芸術
- 先史学:伝統と民俗
- 発達障害
- ヴィーナス像
- 平均死亡年齢
- 欠乏症(クル病・壊血病)
- 腫瘍
- 感染と免疫
- 関節炎
- 歯の病気
- 結核
- 梅毒
- 急性灰白髄炎(小児麻痺)
- 感染症
- 軟部の病気
- 医学から見た先史時代人の手
- 頭蓋穿孔
- 結論
この本は、他の古病理学の本とは異なり、人骨の古病理だけではなく、先史時代の考古学的情報とあわせて、古病理学的解釈をするというユニークな本で、参考になります。