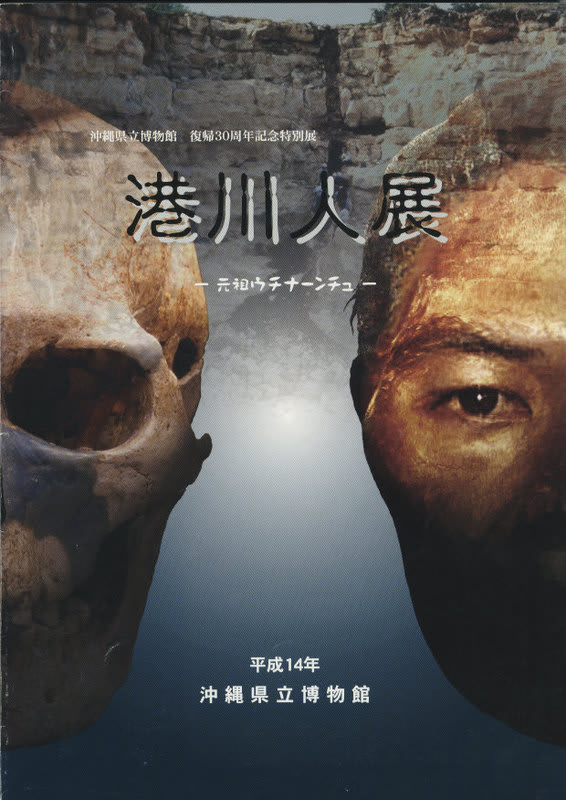|
ホモ・サピエンスの誕生 (市民の考古学) 価格:¥ 1,995(税込) 発売日:2007-11 |
この本は、元朝日新聞社の科学ジャーナリスト・河合信和さんが、人類進化についてまとめられたものです。「朝日総研レポート(AIR21)」に掲載したレポートをもとにしています。2007年に、同成社から出版されました。
河合さんの著書は、以前にもご紹介しましたが、これまでに人類学や考古学の著書や翻訳書を多数出版されています。
本書の内容は、以下のように全7章からなっています。
- 第1章.最古の人類はどこ?
- 第2章.その後の猿人とホモ属
- 第3章.ホモ・サピエンスのアフリカ単一起源説の勝利
- 第4章.アフリカで遡る現代的行動の起源
- 第5章.書き換えられる「狩猟民」としてのネアンデルタール人復元像
- 第6章.自立的な発展だったのか? 末期ネアンデルタール人の選んだ途
- 第7章.小さな脳の人類がもたらした大きな衝撃
人類進化の最新の情報を中心に書かれた本です。