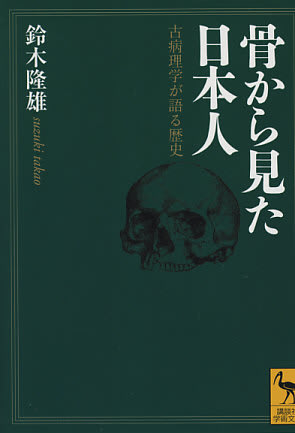| 古代アンデスの謎―2000年前の脳外科手術 価格:¥ 1,631(税込) 発売日:1992-07 |
この本『古代アンデスの謎』は、日本大学医学部の脳神経外科医の片山容一さんが、南米の古代アンデス文明で盛んに行われていた頭蓋穿孔について書いたものです。副題には、「二〇〇〇年前の脳外科手術」とあります。1992年に、廣済堂出版から出版されました。
本書の内容は、以下のように、全10章からなります。
- 穴の開いた頭蓋骨の発見
- 古代アンデスの謎をさぐる
- 古代アンデスの文化と環境
- 古代アンデスの脳外科手術
- 魔術的儀式か医学的治療か
- 古代アンデスの外科医の活躍
- 合理的だった古代アンデスの脳外科手術
- 古代外科医が克服した迷い
- 現代に通じる古代外科医の情熱
- 現代の脳外科にみる共通性
本書は、古代アンデス文明の頭蓋穿孔について、脳神経外科医である片山容一さんが医学的に解明しており、大変、参考になります。