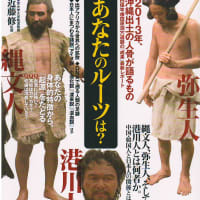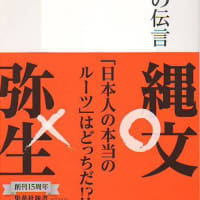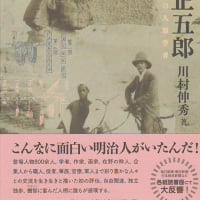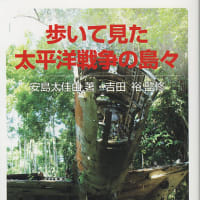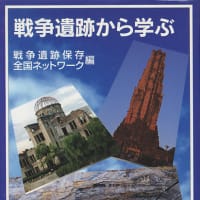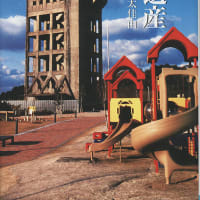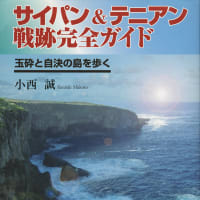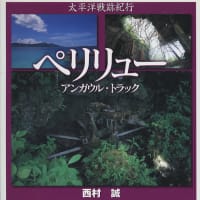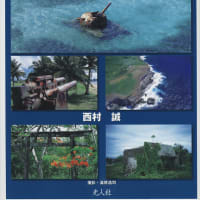池田次郎(Jiro IKEDA)[1922-2012][池田次郎(1982)『日本人の起源』の著者紹介より改変して引用](以下、敬称略)
池田次郎は、1922年11月3日に、山梨県甲府市で生まれました。やがて、旧制甲府中学校と旧制松本高校を卒業し、東京帝国大学理学部人類学科に入学します。東京帝国大学に進学した際は、医者になれとすすめられたそうですが、当の本人は、考古学や歴史学に興味を持っていたと言われています。東京大学では、長谷部言人[1882-1969]に師事して、長谷部の指導により土器を研究しました。1945年9月に、石斧を調べた卒業論文を提出し、東京帝国大学理学部を卒業します。同級生は、北川秀生でした。ちなみに、卒業論文は、1948年に「磨製石斧の分類」『人類学雑誌』第60巻第1号と「打製石斧の分類」『人類学輯報』第1号.に発表されました。卒業後は、母校の大学院に残ります。
やがて、池田次郎に第1の転機が訪れました。1948年に、広島県立医科大学(現・広島大学医学部)の解剖学第1講座の助手に就任したのです。広島県立医科大学は、広島県立医学専門学校を前身として、1948年3月10日に設立が認可されました。当時の解剖学教室は、今村 豊[1896-1971]教授・鈴木 誠[1914-1973]助教授・文化人類学者の蒲生正男[1927-1981]助手という顔ぶれでした。この中で、今村 豊と鈴木 誠は、京城帝国大学医学部の元教員と卒業生で、京城学派と呼ばれています。この広島県立医科大学時代は、今村 豊のみが解剖を行い、池田次郎は中国地方の貝塚の発掘や考古学調査ばかりやっていたそうです。池田次郎は、広島県立医科大学解剖学教室で、助手・講師・助教授と昇任しました。1951年に、鈴木 誠が信州大学医学部第2解剖学教室教授に転出すると、その後任の助教授に就任します。助教授に昇任したため、解剖学を教える必要性が生じ、この時から骨学を専門とすることになります。
池田次郎に、第2の転機が訪れました。恩師の今村 豊が、1952年4月に新潟大学医学部の第1解剖学教室教授に転任することになったため、一緒に助教授として移籍したのです。移籍した翌年の1953年8月31日付けで、「血縁家族間に於ける頭長・頭幅及び頭長幅示数の類似に就いて」のテーマで、勤務先の新潟大学医学部で医学博士号を取得しました。この生体計測のテーマは、京城学派が得意としたもので、池田次郎もその影響を受けています。今村 豊は、60歳の還暦の時に、小浜基次[1904-1970]・鈴木 誠[1914-1973]・池田次郎・三上美樹の名前を挙げて、この4名は自分の弟子だと公表しました。この新潟大学時代には、江上波夫[1906-2002]を団長とする、東京大学イラン・イラク遺跡調査団に1956年~1957年・1959年・1964年と3回、自然人類学担当として参加しました。但し、1964年の時は新潟大学から京都大学に移籍しています。
池田次郎に、第3の転機が訪れました。1962年に、京都大学理学部に自然人類学教室が新設され、その助教授として転任したのです。当時の教室は、今西錦司[1902-1992]が京都大学人文科学研究所と併任で教授に就任し、助教授には、池田次郎と伊谷純一郎[1926-2001]の2名が就任しました。この時、今西錦司は、「彼ならええやろう」とうなずいたと伝えられています。奇遇でしょうが、京都大学は、恩師・今村 豊の母校でした。1966年、池田次郎は教授に昇任します。京都大学時代は、1967年と1968年に京都大学アフリカ学術調査隊に、自然人類学担当として参加しています。その後は、フィールドをイランへと移し、1971年・1973年・1975年・1977年と調査を行いました。ところが、これからという時の1979年2月に、イラン革命が起こり、このプロジェクトは打ち切りとなります。
池田次郎が書いた主な著書は、以下の通りです。石田(2013)によると、著書は14冊とあります。
- 池田次郎・大野 晋編(1973)『論集日本文化の起源5.日本人種論・言語学』、平凡社
- 池田次郎編著(1978)『人類学講座6.日本人Ⅱ』、雄山閣出版
- 池田次郎(1982)『日本人の起源』、講談社
- 池田次郎(1998)『日本人のきた道』、朝日新聞社
池田次郎が『人類学雑誌』に発表した主な論文は、以下の通りです。石田(2013)によると、論文と報告書が116編・総説とその他が50編とあります。
- 池田次郎(1953)「血縁家族間に於ける頭長・頭幅及び頭長示数の類似に就いて」『人類学雑誌』、第63巻第1号、pp.15-21
- 池田次郎(1974)「沖縄・宮古島現代人頭骨の計測」『人類学雑誌』、第82巻第2号、pp.150-160
- 多賀谷 昭・池田次郎(1976)「頭骨計測値の多変量解析からみた現代琉球人(男性)」『人類学雑誌』、第84巻第3号、pp.204-220
- 池田次郎(1979)「プレ・アイヌ説をめぐって」『人類学雑誌』、第87巻第3号、pp.297-302
- 池田次郎・多賀谷 昭(1979)「刀痕のある中世人頭蓋について」『人類学雑誌』、第87巻第3号、pp.347-351
- 池田次郎・多賀谷 昭(1980)「生体計測値からみた日本列島の地域性」『人類学雑誌』、第88巻第4号、pp.397-410
- 池田次郎(1982)「前頭洞計測値の集団間変異」『人類学雑誌』、pp.91-104
池田次郎と日本人類学会との関わりは、1943年10月1日付けの日本人類学会会員名簿に記載されていますので東京帝国大学の学生時代に入会したのでしょう。その後、1967年~1969年と1978年~1980年にかけて理事を務め、1980年~1984年にかけては日本人類学会会長に就任しました。
1986年、池田次郎は京都大学を定年退官します。その後は、1986年に岡山理科大学理学部教授、1991年に九州国際大学法経学部教授として後進の指導を行いました。1993年には、九州国際大学を退職しています。
池田次郎は、京都大学時代に、片山一道(現・京都大学名誉教授)・多賀谷 昭(現・長野県看護大学)・毛利俊雄(現・京都大学霊長類研究所)等を育てました。
2012年11月11日に、「京都大学人類学講座50周年記念会」が行われました。しかし、池田次郎は、2001年に脳内疾患から車椅子生活を余儀なくされており、当日は出席できずにビデオレターを寄せたそうです。2012年12月19日、池田次郎は肺炎により、90歳で死去しました。先史学から始まった研究テーマは、生体人類学と骨学に変わりましたが、先史学への興味も持ち続けており、『人類学雑誌』に4回にわたって発表された「日本の古人骨に関する文献」は、今でも貴重なデータを提供しています。
私は、池田次郎先生とは学生時代からお付き合いさせていただいておりました。池田次郎先生は、広島県立医科大学に赴任されておられた関係なのか、広島県出身者を特に可愛がっておられました。実際、お弟子さん達の片山一道先生・多賀谷 昭先生・毛利俊雄先生の3人共に広島県のご出身です。私は、父母が広島県出身で現在も本籍が広島県というだけで可愛がっていただきました。私が留学中の1988年にユーゴスラヴィア(現・クロアチア)で開催された、第12回国際人類学民族学会議(IUAES)では、偶然、泊まっていたホテルが一緒で、池田次郎先生ご夫妻と夕食をご一緒させていただいたことを思い出します。その時、奥様の静江様も広島県のご出身であることを知りました。池田次郎先生と最後にお目にかかったのは、1998年11月7日と11月8日に、福岡県福岡市の大手門会館で開催された、第13回「大学と科学」公開シンポジウム『検証・日本列島』に参加した際に、2次会でご一緒させていただいた時だと思います。その頃は、福岡県にお住まいでまだお元気でお酒も召し上がっておられたのを記憶しています。穏やかな語りですが、人類学や先史学に関する知識は驚くほど広くて深く、随分と勉強になりました。
*以下は、「京都大学大学院理学研究科」で公表されている池田次郎名誉教授業績集へのリンクです。
*池田次郎に関する資料として、以下の文献を参考にしました。
- 馬場 功(1971)「ひと:池田次郎氏」『季刊人類学』、第2巻第4号、pp.107-109
- 日本解剖学会(1995)『日本解剖学会100周年記念:教室史』、日本解剖学会
- 石田英実(2013)「追悼文:池田次郎教授追悼文」『Anthropological Science(Japanese Series)』、第121巻第2号、pp.85-87











![日本の人類学者51.小金井良精(Ryosei KOGANEI)[1859-1944]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0a/97/46d972234646556faff44f0f58d1bae6.jpg)