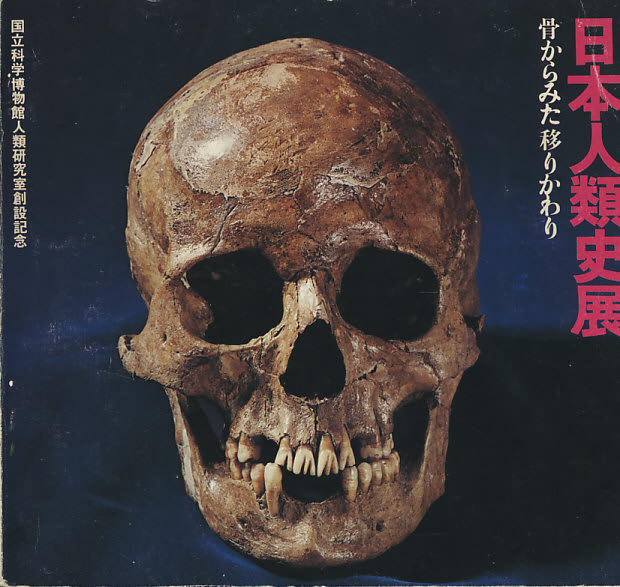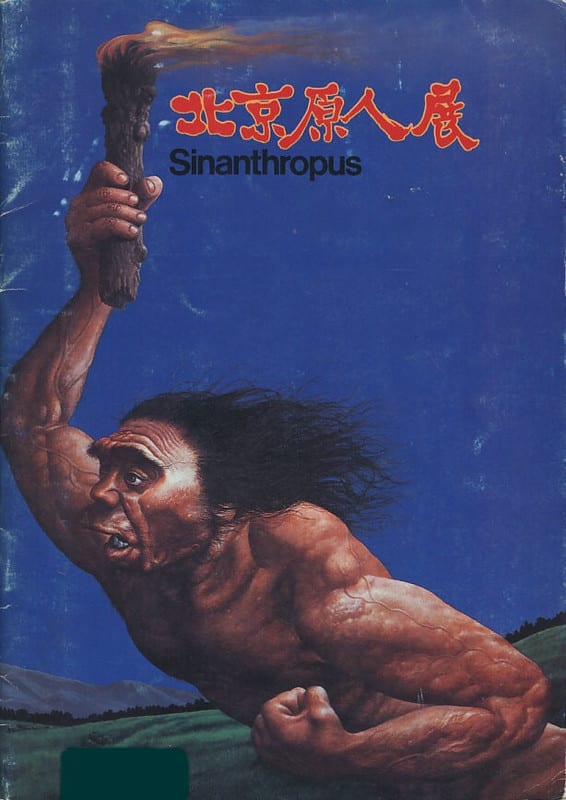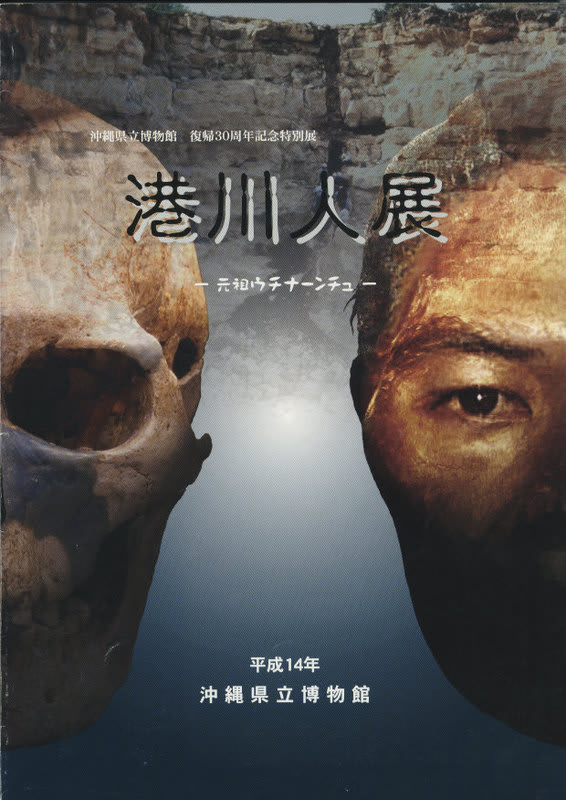この図録は、現在、国立科学博物館の特別展として行われている『グレートジャーニー人類の旅』展の図録です。私は、監修者の国立科学博物館名誉研究員の馬場悠男先生から寄贈していただきました。アマゾンで検索しましたが、ヒットしませんでしたのでリンクさせていません。上野の国立科学博物館で購入できます。
企画展名: 国立科学博物館特別展『グレートジャーニー人類の旅』(この星に、生き残るための物語)
開催期間: 2013年3月16日(土)~同年6月9日(日)
本図録の内容は、以下のように、全6章からなります。
第1章.旅の始まり:2つのグレートジャーニー
- ラエトリの足跡化石:旅の始まり、旅の終わり
- 人類遙かなる旅(関野吉晴)
- 対談「グレートジャーニー」で学んだこと経験したこと(篠田謙一・関野吉晴)
- 人類の拡散:サピエンスのグレートジャーニー(馬場悠男)
第2章.熱帯雨林[アマゾン]
第3章.高地[アンデス]
- 高地の知恵:共同体を生かす
- 対談「文明の危機といくつかの可能性」(佐藤洋一郎・関野吉晴)
第4章.極北[アラスカ・シベリア]
第5章.乾燥地帯[アタカマ・ゴビ・ヌビア・ダナキル]
第6章.縄文号の旅と日本[温帯モンスーン]
- 関野が挑んだ日本人への道(篠田謙一)
- 手がかりは足元にある:江戸期日本の暮らしのカタチ(鞍田 崇)
- 「ラエトリ遺跡の猿人家族を復元する」(馬場悠男)
- 未来を紡ぐ物語(関野吉晴)
関野吉晴さんは、1949年に東京都で生まれ、1975年に一橋大学法学部を卒業します。一橋大学在学中に探検部を創設して、1971年にはアマゾン全域踏査隊長としてアマゾン川全域を調査しました。その後、25年間の間に、32回・通算10年間以上にわたって、南米を探検したそうです。現地調査の際に、医療が必要だと感じ1976年に横浜市立大学医学部医学科に入学し、1982年に同大学を卒業して医師になります。1993年12月からは、グレートジャーニーを始め、徒歩・ラクダ・自転車・犬ぞり・トナカイぞり・カヌー・カヤック・シーカヤック・カユック等を使って、世界中を旅しながら、人類が辿った道を訪ねています。2002年には、武蔵野美術大学造形学部教養文化研究室教授に就任して、後進の指導も行っています。