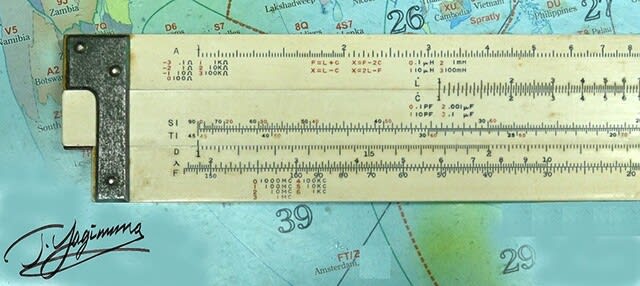昨年、NHKが「二人のロバートキャパ」と言う形で取り上げた事を記憶している。
亦最近、東京のライカギャラリーで「ロバートキャパ生誕100年記念の写真展」が予定されているそうだ。
ロバートキャパと言えば、嘗ての第二次世界大戦の戦場の様子を報道した最先端の報道カメラマンとしてその名が知られた名カメラマンだ。

私の手元に、1961年に銀座「松屋」デパートでの「ロバートキャパ」写真展の記念誌が保存して有った。
終戦と共に、日本にも平和な日々が訪れた。
人々がカメラで日常を記録しアルバムを「我が家の想い出」てきな形で残そうと盛んに写真を撮る様な平和な日々が訪れた。
巷には、町工場が簡単に作れる 6x6版の二眼レフが溢れた。6x6版のルールフィルムは、六桜社(→さくらフィルム→コニカ。小西六兵衛さんが日本で最も古い写真の会社を作った。)
や、富士フイルムが、これまた簡単で作り易い6x6版のロールフィルムが出回った事も重なったのだろう。
勿論、ドイツ製のローライフレックス。更にエントリー用のローライコードなど、この当時のプロカメラマンの愛用したメインカメラだった。
そして、ニッコールレンズを付けた「アイレスフレックス」、ロッコールレンズの「ミノルタオートコード」等々、庶民が買えた安物には「ヤシカフレックス」「リコーフレックス」「xxフレックス」等々、数え切れない程の二眼レフが巷に出回っていた。
かの有名な写真家大竹省二さんもローライで稼いでいた。
そして、新聞報道カメラマンが、日々愛用した最前線は「スピグラ」だ。正式には「スピードグラフィックス」と言うのだが、大きなフラッシュライトを横に取り付けた、これまた大きな蛇腹式の一枚撮りカメラだった。カメラマンは、政治家の前で、「パッ」とフラッシュを一発焚く、その一発が勝負だから、タイミングを間違えれば、失敗写真に成る事必定だ。
今みたいに、連続で一秒間に8枚も10枚も撮れる便利な物では無かったのだから、その当時のカメラマンは、大変だったのだ。
「決定的瞬間」と言う言葉が流行った。単なる飾り文句では無く、事実決定的な瞬間が物を言った時代だった。
アメリカの有名な写真家達が、朝鮮戦争の取材の為に、その足がかり地として東京に来て、予備機のつもりで手にした日本製のニコンSを持って朝鮮に行ったのが、意外にも、その写りが良くて頑丈だったニコンを絶賛、彼らのメインカメラになった話は有名だ。
そして、ニコンS2、キャノンⅣsb が花形カメラにのし上がった。
当時、ニコンS2は8万3千円、キャノンは8万5千円だった。
大学卒業者の給料が千円~三千円位だったのだから、如何に高価だったか、正に「垂涎(スイゼン)の華」だったのだ。
話が脱線したが、ロバートキャパは、戦場で多くの写真を撮って、戦場の過酷さや非戦闘員の庶民の姿など、多くを伝えたカメラマンの一人として、その功績が戦後間も無い時代に於いても、人々の感動を呼んでいた。

昭和36年に開かれた、銀座松屋でのキャパの写真展には、158点の写真が展示された。




功績と感動を今の世に伝えている「ロバートキャパ」の名は、写真とカメラを愛する者として忘れる事は出来ない。