
今回のお気に入りは、舘野鴻です。
久しぶりに昆虫細密画の名手・舘野鴻の絵本を鑑賞しました。
今回鑑賞したのは「ぎふちょう」(2013/6)と「つちはんみょう」(2016/4)の2冊。
しめて4320円は大きな出費でしたが、それだけの価値があるため息の出るような素晴らしい作品でした。
作家のことは以前「しでむし」(2009/4)を鑑賞したときにブログに書きました。
メレ山メレ子の「ときめき昆虫学」に紹介されていて知ったこと。
ファーブル昆虫記の表紙絵で有名な熊田千佳慕の弟子であること。
点のひとつひとつ、線の一本一本を正確に描いており、どれだけの時間をかけて観察し、どれだけの時間をかけて描いたのか、想像できないこと。
今回の2冊も同様の出来栄え。
特にギフチョウは大のお気に入り。
鱗粉の1枚1枚、体毛の1本1本を丁寧に描いており、この美しさは本物以上。
以前ご紹介した田淵行男の「安曇野の蝶」がこれまでで一番感動した作品ですが、それに近い作品でした。
まさしく絵を鑑賞するだけでも満足、という絵本。
ただし作者が長い時間をかけて観察したことで知りえた「虫たちの生涯」をつづった文章も魅力的。
以下は、作者が書いた虫たちの物語についての感想です。
ギフチョウは早春に蝶になり、早々にオスメスが出会って産卵すると生涯を終えます。
卵のいくつかはダニに吸われカラになります。
孵化した幼虫の何匹かはアリに連れ去られます。
葉を食い尽くして地上に降り、次の葉を探していると、カエルやネズミに襲われます。
抵抗といえば、隠していた赤いツノを出して威嚇するだけ。
そしてようやく生き残った幼虫は蛹となり、10か月もの長い眠りにつきます。
この間に捕食者に見つからなかった者だけが、翌春、蝶として羽ばたくことが許されます。
このようにギフチョウは、ほとんど抵抗らしい抵抗をせずに生涯を過ごします。
弱肉強食の自然界でよく生き残ってこれたものです。
きっと抵抗しないことも自然のひとつのかたちなのですね。
作者はあとがきで、観察を続けてきたギフチョウたちを根こそぎ捕まえていった男たちのことを書いています。
ギフチョウが森の生態系の中でも弱者に位置することを知った後で、このあとがきを読むと、居たたまれない気持ちになりました。
絶妙なバランスの上に成り立っている大自然を破壊するのは人・・・。
ツチハンミョウの幼虫は、ハナバチの巣の中で、ハチの幼虫と花粉ダンゴを食べて成長し、蛹を経て成虫になります。
成虫は地上に出ると葉を食べて食べてどんどん太ります。
その栄養を元にして4000個もの卵を生み、その生涯を閉じます。
孵化したたくさんの幼虫たちは、大群でハナバチの巣にたどり着き、飛び立つハチにしがみついて花にたどりつきます。
そこで目指す特定の種のハナバチに出会い、しがみついて巣にたどり着きます。
たまたま同じハチの巣にたどりついたツチハンミョウの幼虫2匹。
相手を倒した最後の1匹が成虫になることができます。
幼虫の寿命はわずか4日間と書かれています。
その間にこのような難関を突破して安住の地にたどりつくことができるのは4000匹の内、2~3匹。
生存率0.1%以下とは、とんでもないサバイバルゲームです。
何もそこまで複雑にしなくてもいいのに!と言いたくなるようなルートをたどる生涯。
以前ブログに書いたユキムシの生涯も複雑でしたが、ツチハンミョウも負けていませんね。
こんなわずかばかりの幸運にすがって生をつないでいる生きものもいるのですね。
そういえば以前、特定のハチに寄生する寄生バチに寄生する寄生バチがいると、読んだことがあります。
2段構えの寄生という複雑さに驚いたものです。
自然界の多様性や複雑さは深遠な宇宙そのもの。
とても人間に把握しきれるものではない、と思い知らされます。
久しぶりに昆虫細密画の名手・舘野鴻の絵本を鑑賞しました。
今回鑑賞したのは「ぎふちょう」(2013/6)と「つちはんみょう」(2016/4)の2冊。
しめて4320円は大きな出費でしたが、それだけの価値があるため息の出るような素晴らしい作品でした。
作家のことは以前「しでむし」(2009/4)を鑑賞したときにブログに書きました。
メレ山メレ子の「ときめき昆虫学」に紹介されていて知ったこと。
ファーブル昆虫記の表紙絵で有名な熊田千佳慕の弟子であること。
点のひとつひとつ、線の一本一本を正確に描いており、どれだけの時間をかけて観察し、どれだけの時間をかけて描いたのか、想像できないこと。
今回の2冊も同様の出来栄え。
特にギフチョウは大のお気に入り。
鱗粉の1枚1枚、体毛の1本1本を丁寧に描いており、この美しさは本物以上。
以前ご紹介した田淵行男の「安曇野の蝶」がこれまでで一番感動した作品ですが、それに近い作品でした。
まさしく絵を鑑賞するだけでも満足、という絵本。
ただし作者が長い時間をかけて観察したことで知りえた「虫たちの生涯」をつづった文章も魅力的。
以下は、作者が書いた虫たちの物語についての感想です。
ギフチョウは早春に蝶になり、早々にオスメスが出会って産卵すると生涯を終えます。
卵のいくつかはダニに吸われカラになります。
孵化した幼虫の何匹かはアリに連れ去られます。
葉を食い尽くして地上に降り、次の葉を探していると、カエルやネズミに襲われます。
抵抗といえば、隠していた赤いツノを出して威嚇するだけ。
そしてようやく生き残った幼虫は蛹となり、10か月もの長い眠りにつきます。
この間に捕食者に見つからなかった者だけが、翌春、蝶として羽ばたくことが許されます。
このようにギフチョウは、ほとんど抵抗らしい抵抗をせずに生涯を過ごします。
弱肉強食の自然界でよく生き残ってこれたものです。
きっと抵抗しないことも自然のひとつのかたちなのですね。
作者はあとがきで、観察を続けてきたギフチョウたちを根こそぎ捕まえていった男たちのことを書いています。
ギフチョウが森の生態系の中でも弱者に位置することを知った後で、このあとがきを読むと、居たたまれない気持ちになりました。
絶妙なバランスの上に成り立っている大自然を破壊するのは人・・・。
ツチハンミョウの幼虫は、ハナバチの巣の中で、ハチの幼虫と花粉ダンゴを食べて成長し、蛹を経て成虫になります。
成虫は地上に出ると葉を食べて食べてどんどん太ります。
その栄養を元にして4000個もの卵を生み、その生涯を閉じます。
孵化したたくさんの幼虫たちは、大群でハナバチの巣にたどり着き、飛び立つハチにしがみついて花にたどりつきます。
そこで目指す特定の種のハナバチに出会い、しがみついて巣にたどり着きます。
たまたま同じハチの巣にたどりついたツチハンミョウの幼虫2匹。
相手を倒した最後の1匹が成虫になることができます。
幼虫の寿命はわずか4日間と書かれています。
その間にこのような難関を突破して安住の地にたどりつくことができるのは4000匹の内、2~3匹。
生存率0.1%以下とは、とんでもないサバイバルゲームです。
何もそこまで複雑にしなくてもいいのに!と言いたくなるようなルートをたどる生涯。
以前ブログに書いたユキムシの生涯も複雑でしたが、ツチハンミョウも負けていませんね。
こんなわずかばかりの幸運にすがって生をつないでいる生きものもいるのですね。
そういえば以前、特定のハチに寄生する寄生バチに寄生する寄生バチがいると、読んだことがあります。
2段構えの寄生という複雑さに驚いたものです。
自然界の多様性や複雑さは深遠な宇宙そのもの。
とても人間に把握しきれるものではない、と思い知らされます。


















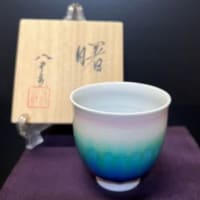

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます