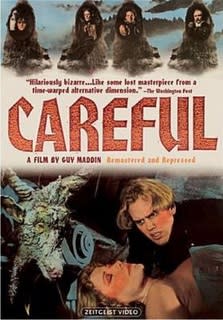(原題:L'anglaise & Le duc)2001年作品。フランス革命期における混乱をオルレアン公爵の元愛人であった英国人女性グレース・エリオットの目を通して描く。監督はエリック・ロメール。当初、若い女性の“惚れたの別れたのという話”が得意なロメールにこういう歴史ドラマが描けるのかと思っていたが、映画を観て大いに納得した。これは良い映画だ。
1792年、パリの民衆はルイ16世の王権停止を求めて蜂起し、国王一家は投獄される。グレースは何と別邸へと避難するが、まもなく民衆による反革命分子の大虐殺が始まる。彼女は助けを求めてきたシャンスネ侯爵を匿うものの、彼はオルレアン公爵の政敵であり、オルレアンはいい顔はしない。それでもシャンスネをイギリスに逃がす手筈を整える。翌年、ルイ16世は処刑される。やがてロベスピエール率いるジャコバン派が台頭。グレースとオルレアンは審判を受けることになる。

ここには史劇らしいスペクタクル場面やケレン味たっぷりの演技はまったくない。泰西名画のような背景の中に俳優たちをデジタル合成するという方法で難しい歴史考証をすべてクリアし、いわば舞台劇のような空間の中で、映画の焦点を登場人物の心理描写のみに絞り込ませている。そうすると膨大なセリフによってキャラクターを造形するというロメール本来の手法が活きてくるのだ。
考えてみれば、この方法は彼が今まで撮ってきた恋愛喜劇だけに通用するものではなく、登場人物の内面を掘り下げるという意味でシリアスな題材にも十分応用が利くのである。それがまた“市民革命”とは名ばかりの弾圧と殺戮に満ちたこの時代の真実と、犠牲になる人々の有様を鮮烈かつ冷静に描き出すことに成功している。物量主義だけが歴史ドラマの方法論ではないのである。
グレースに扮するルーシー・ラッセルは堂々たる名演。革命の在り方に疑問を持つモラリストのヒロイン像を見事に創出している。公爵役のジャン=クロード・ドレフュスの存在感も捨てがたい。フランソワ・マルトゥレやレオナール・コビアン、キャロリーヌ・モラン、アラン・リボールといった脇を固める顔ぶれも確かな仕事ぶり。映像処理の素晴らしさも含めて、これはこの頃のヨーロッパ映画を代表するクレバーな秀作と断言したい。
1792年、パリの民衆はルイ16世の王権停止を求めて蜂起し、国王一家は投獄される。グレースは何と別邸へと避難するが、まもなく民衆による反革命分子の大虐殺が始まる。彼女は助けを求めてきたシャンスネ侯爵を匿うものの、彼はオルレアン公爵の政敵であり、オルレアンはいい顔はしない。それでもシャンスネをイギリスに逃がす手筈を整える。翌年、ルイ16世は処刑される。やがてロベスピエール率いるジャコバン派が台頭。グレースとオルレアンは審判を受けることになる。

ここには史劇らしいスペクタクル場面やケレン味たっぷりの演技はまったくない。泰西名画のような背景の中に俳優たちをデジタル合成するという方法で難しい歴史考証をすべてクリアし、いわば舞台劇のような空間の中で、映画の焦点を登場人物の心理描写のみに絞り込ませている。そうすると膨大なセリフによってキャラクターを造形するというロメール本来の手法が活きてくるのだ。
考えてみれば、この方法は彼が今まで撮ってきた恋愛喜劇だけに通用するものではなく、登場人物の内面を掘り下げるという意味でシリアスな題材にも十分応用が利くのである。それがまた“市民革命”とは名ばかりの弾圧と殺戮に満ちたこの時代の真実と、犠牲になる人々の有様を鮮烈かつ冷静に描き出すことに成功している。物量主義だけが歴史ドラマの方法論ではないのである。
グレースに扮するルーシー・ラッセルは堂々たる名演。革命の在り方に疑問を持つモラリストのヒロイン像を見事に創出している。公爵役のジャン=クロード・ドレフュスの存在感も捨てがたい。フランソワ・マルトゥレやレオナール・コビアン、キャロリーヌ・モラン、アラン・リボールといった脇を固める顔ぶれも確かな仕事ぶり。映像処理の素晴らしさも含めて、これはこの頃のヨーロッパ映画を代表するクレバーな秀作と断言したい。