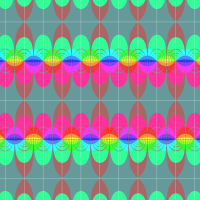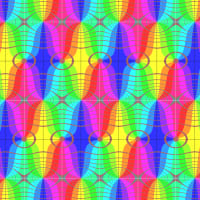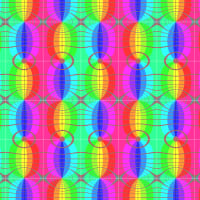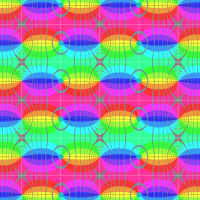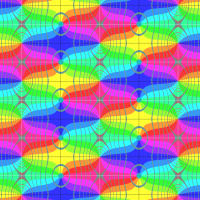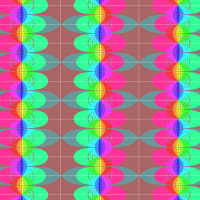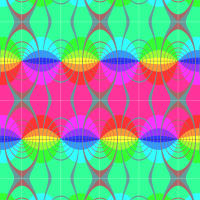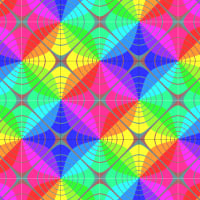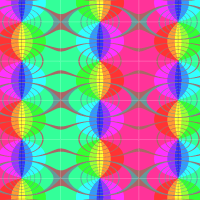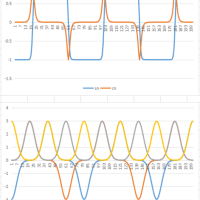本日は一日出張で、午後は短時間で済んだので早めに帰社しました。なので若干の考察と確認をする時間が取れました。
まず、やりたいことをまとめないといけません。出発点はPROLOGマシンを作って論理型言語の構成を確認すること。これにはWAMと呼ばれるPROLOG仮想マシンの決定版の論文があって、しかしこれを読むためには若干というかかなりの予備知識が必要です。
あわよくば第五世代コンピュータ計画の後半に作られたGHC言語の後追いをしようと考えていて、おそらく並列化やガードによる決定性の確保は単一のマイコン上で動作していて、データフローというかUNIXで言うストリームのパイプでの接続がローカルネットで実現されていて、いま追試をやるならイーサネットで十分と思います。
で、言語処理系の設計ですから最初から大きなものを作るとたちまち巨大な壁にぶち当たるので、1970年代のマイコンのソフト設計を持ち出した、ということ。tiny BASICが有名なのでそこから私の考察を開始したら、B言語みたいになってしまいました。これの実際例が前項の8080マイコンのμPlan言語です。
今はCPUは速いし、メモリはふんだんに使えますから日常的にはWindows等を使うのがお得で、マイコンソフトの経験にはArduinoとかラズベリーパイとかがハードの組み立てが最小限になるので有用と思います。ただし、後者は資料を集めただけで実際の経験はありません。別の小型マイコンボードのプログラミングの経験は多少あります。
思い立ったのが吉日と、とある電子部品小売店が設計したRX621マイコンボードを買って、動作させる前にあれこれ考えている、これが今の地点です。幸いというか、キーボードとLCDディスプレイは何とか接続できそうで、開発系のPCから切り離して自律動作をさせることができそうです。拡張性はSPI接続のEEPROMとSRAMで確保します。この拡張ができれば知識処理に到達できる小型ハードが手に入ることになります。
ここで考察上に出てくるのがFPGAと呼ばれるソフトでハード設計をする素子の学習用ボードです。こちらもあらかじめ配線されているので、追加回路が無ければソフト部分もハード部分もWindowsの画面上で設計できます。FPGA試作ボードはプロが試行段階で使うので各種取りそろっていて、アマチュアでも使えそうな経済的価格帯のがいくつかあります。これの操縦は参考書があるのでその通り実施すれば経験できますが、思い通りのものを作ろうとすると論理回路からCPUを組み立てるような過程が必要となります。
FPGAにはCPUが入っているものと入っていないものがあり、どちらも手頃な価格で手に入ります。CPUが入っているものはかなり高度なARMで、クロックが1GHz近くあるのでキャッシュ等が無いと性能が出ません。これのソフト設計は難しいので、提供側はあっさりとLinux等を使用していて、これではWindowsとあまり変わらない感じがします。
CPUが無いタイプのものは、PS/2キーボードやVGAなどの端末はすぐに接続できるもののCPUが無いので、CPU無しで済ませるか、あるいはCPUを作らないといけません。CPUと言っても8080程度は無いと論理プログラミングなど夢のまた夢。しかし高度なCPUは手応え十分です。メーカーはFPGAのためのCPUの配線情報を用意していますが、かなり高度なCPUで、何となく私の今の目標からは寄り道をさせられそうな感じがします。
面白いことにCPUを論理回路から組み立てて、PASCALレベルの計算機言語を用意する解説の本は複数売られています。で、それを読み直そうとしています。
RX621マイコンボードからは多少離れてはいるものの、どこまでかアマチュアで手の出せる範囲なのかを見極める考察の範囲と思っています。