雪の元旦

昨夜から降り積もった雪に、今朝はいい天気になって雪が眩しかった。家の前の道路はもう早くに除雪車が出て、写真のようにいつもの冬の道路である。しかし、やっとお正月らしい雪のお正月になった。朝食には餅を喰って、近くの阿弥陀院というお寺に「年賀」のお参りに行って来て、今日の元旦の日はもう何もすることがない。元旦の朝にはCDで音楽を聴いて餅を喰うのが定番で、積雪の少ない年は雪掻きもしないでいいのだから、有難きかな、今年は静かなお正月になった。屋根の雪の融け落ちる雨垂れの音が部屋に音響して、これから昼風呂を沸かして、頂き物の薬湯の粉末の偽・家庭内温泉に浸かって「一年の計は元旦にあり」の「計画」イメージを膨らませてみようか、どうしようか、と思ってみるのもこれも一興であるだろう。
ところで、昨夜は床の間の掛物を変えて見た。新しい年を迎えるにあたっては、やっぱりまた違ったものに掛け変えることで、気分もまた変化する。お正月バージョンというところか。それで、今までは、新進の抽象画家・新井美紀の赤いモノクローム油彩画を掛けていたが、この度は西脇順三郎 (1894-1982) の横物を出した。茫洋とした湖水の中で、人間と鳥類の会話が聞こえてくるような詩人らしい超現実的モノクローム・デッサンである。これも、面白い床の間の景観になった。『定本 西脇順三郎全詩集 300部限定版』(昭和56年 筑摩書房刊) も添えてみた。そこで、『全詩集』の中から詩集『あむばるわりあ』の詩情(あとがき)の一部を下記長々と抜粋してみる。
昔からの哲人の言葉を借りるなら、詩の世界は老子の玄の世界で、有であると同時に無である世界、現実であると同時に夢である。またロマン主義的哲学を借りたなら、詩の世界は円心にあると同時に円周にあるといふ状態の世界であらう。さうした詩の世界から受ける印象をいろいろの名称で呼ぶ、美を好むものは美といふ、神を好むものは神といふ。それがために詩の精神のこと或は善或は真ともいはれてゐる。また或る人は (私もさうであるが) 詩やその他一般の芸術作品のよくできたか失敗したかを判断する時、その中に何かしら神秘的な「淋しさ」の程度でその価値を定める。淋しいものは美しい、美しいものは淋しい、といふことになる。
さうした方法で成功した詩の世界に表れて来る美または淋しさは永遠を象徴する。また神秘的世界を象徴する。円心にあると同時に円周にある一つの世界は神秘的な世界である。
詩の世界には何かしらの人生観が包まれてくる。人生観は詩の重大な要素ではない。また人生観は直ちに詩にならない。ただ円心にあると同時に円周にある状態を生ずる人生観は詩の世界となる。
だが詩でない人生観は詩を作る前に必要である。それには原始的な人生観がよい。
人間の生命の目的は他の動物や植物と同じく生殖して繁殖する盲目的な無情な運命を示す。
人間は土の上で生命を得て土の上で死ぬ「もの」である。だが人間には永遠といふ淋しい気持の無限の世界を感じる力がある。
このいたましい淋しい人間の現実に立って詩の世界をつくらないと、その詩が単なる思想であり、空虚になる。
このいたましい現実から遠ざかれば遠ざかる程その詩の現実性が貧弱になる。
詩の世界は言葉でない。絵画彫刻でも表される。韻文でも散文でも亦よいことである。詩の世界の材料は「もの」の世界である。
外がだんだん暗くなってきて、いつの間にまた雪が降り出してきた。相変わらず雨垂れの音は止まないでいるが、この冬景色は一個の雪の韻文である。灰色の空と家々の白い屋根と、田んぼや畑の水路の黒い溝にも雪が降っている。雪が現実世界を抒情している。













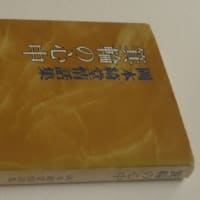

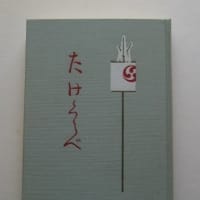




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます