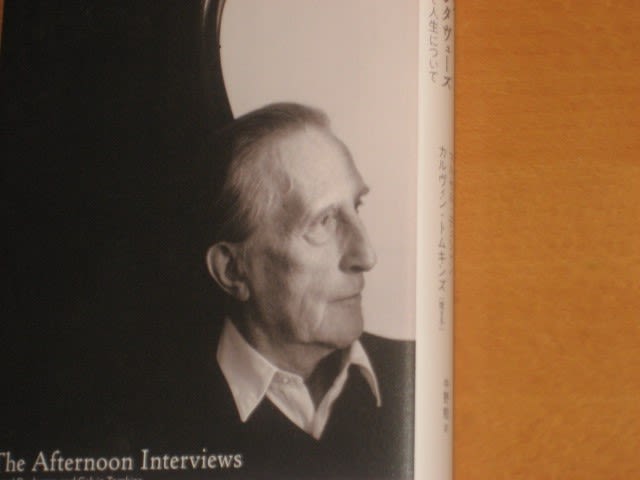この写真は今月の17日に降った初雪の日の写真である。ストックしておいたもので、いつ掲載しようかと思っていたのだったが、日が空いてしまって、それでつい忘れていてしまっていて、だけどどうも掲載したくて、それで今になってしまったのだった。意味があるのかないのか、あんまり意味はないのだったが、掲載しておけばまたいつか思い出すだろう、ということなのである。いつも通る国道351号線沿いのコンビニ店の裏から西谷川を望んでいる。
それで、今日はもう12月30日の日曜であった。久し振りに何もせずに家で過ごしたが、僕のところは新潟県のほぼ真ん中の中越地方の山間部なのだが、報道で言うほどの “ 最大級の年末寒波 ” はなくて、穏やかな一日になった。このまま天候が荒れてくれなければいいのだが、と思う。それで今日は一日中何もしなかった。ただ、先日来からの読書が続いていて、どうもそれを読まずにはいられなかったからその本を読んでいたのだった。三浦篤著『 エドゥアール・マネ 西洋絵画史の革命 』( 角川選書版 平成30年10月19日刊 ) である。ここでその読後感を書くつもりはないが、ただ気に入った文章がいくつかあったから、その中のひとつをここに備忘録として書いておくことは、僕にとってはまた大切なことであるので、以下その抜粋である。
ベラスケスとマネは西洋絵画史をレアリスムの視点から見たときに、要の画家であると位置づけることができる。両者ともに現実の理想化を拒否する冷徹な写実表現を実践するが、それは単に卑俗な現実の再現を目指すものではない。あらゆる存在を等価なまなざしで捉える無差別なレアリスム、卑俗なものに尊厳と輝きを与えるレアリスムにほかならない。現実の特殊な相を保持しつつ、絵画の造形力によってそれを典型化する、いわば高貴化する点が肝要で、その意味では絵画芸術の栄光に捧げられたレアリスム絵画と言ってもよかろう。そうした歴史的系譜において、タブローにおける古典的な現実表象の頂点をベラスケスに見て、近代絵画におけるその臨界点と崩壊をマネに見ることが可能となる。二十世紀からマネを捉えて「モダニズム絵画」の創始者に据えるだけでは、マネのポテンシャルを汲み尽くしたことにはならない。未来も知れぬ十九世紀後半の時点に降り立ってみれば、マネの作品に変革の斬新さのみならず、タブローの崩壊、伝統絵画の黄昏を感じることはむしろ自然だったと思われるのである。
マネのレアリスムと言うのは、絵画の造形力によって「卑俗なものに尊厳と輝きを与える」のだった。マネ以降の「近代絵画」を見る時にはぜひこの言葉を参考にして見てみたいと思うのである。革新とか斬新さとかを感じるのは、どうも僕ではなかなか感じられないから、少しでもこういう論文から参考になるものを学習しておきたいと思うが、なかなか身に着かないのが現実で、これもレアリスムのひとつだろうか。