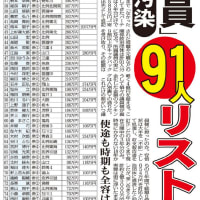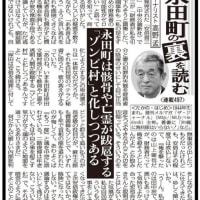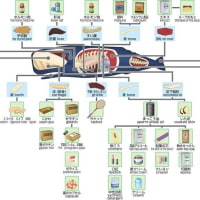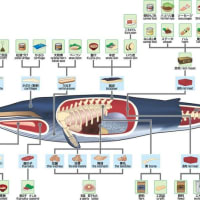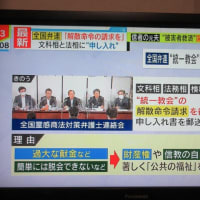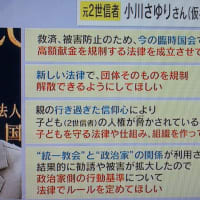2月22日(水): 
459ページ 所要時間2:25 古本93円
俺が読んだことのある三浦綾子の作品は「道ありき」「旧約聖書入門」が思い出される。
前から名前だけは知ってるし、古本として買っておいたのを本棚から取り出して、何となく「眺め読みだけでも…」という気分になって読んだ。一日の仕事を終えて、400ページ以上の作品をまともに読む体力も気力もない。1ページ15秒のペースで筋だけを追いかけた。最後まで行ける自信はなかったが、何とか最後までたどり着くことができた。その意味では作品の持つ力だと思う。
感想4はあくまで、短時間の眺め読みだからである。味わって読めば感想5になる可能性が高い。ただ、それをしようとすれば結局俺はこの作品を読めなかった。作品の概略を理解し、縁を結べただけでも満足すべきだろう。
まず予定調和ではない終わり方にびっくりした。キリスト教の精神のあり方(特に「犠牲」に対する精神)は、日本人の一般的仏教の精神とは全く異質であることをこれでもかというように知らしめてくれる作品だった。
この作品には、元になる旭川市近くの塩狩峠における列車事故(1909年)と殉職したキリスト者がいた。それを著者が、キリスト教団体の要請を受けて後世に残すべく作品化したものである。明治時代後半(日清・日露戦役頃)の日本におけるキリスト教信仰と、仏教的伝統をもつ日本社会との軋轢、確執のあり様を知ることができる。明治にキリスト教がどう見られていたのか、キリスト教徒となることの重さ、大変強い土性骨の必要さ、神と向かい合うことの本気さがよく伝わってきた。
「信仰」というものの語感が、少しだけ現実味をもって感じられた。
【表紙裏紹介文】結納のため、札幌に向った鉄道職員永野信夫の乗った列車は、塩狩峠の頂上にさしかかった時、突然客車が離れて暴走し始めた。声もなく恐怖に怯える乗客。信夫は飛びつくようにハンドブレーキに手をかけた……。明治末年、北海道旭川の塩狩峠で、自らを犠牲にして大勢の乗客の命を救った一青年の、愛と信仰に貫かれた生涯を描き、生きることの意味を問う長編小説。

459ページ 所要時間2:25 古本93円
俺が読んだことのある三浦綾子の作品は「道ありき」「旧約聖書入門」が思い出される。
前から名前だけは知ってるし、古本として買っておいたのを本棚から取り出して、何となく「眺め読みだけでも…」という気分になって読んだ。一日の仕事を終えて、400ページ以上の作品をまともに読む体力も気力もない。1ページ15秒のペースで筋だけを追いかけた。最後まで行ける自信はなかったが、何とか最後までたどり着くことができた。その意味では作品の持つ力だと思う。
感想4はあくまで、短時間の眺め読みだからである。味わって読めば感想5になる可能性が高い。ただ、それをしようとすれば結局俺はこの作品を読めなかった。作品の概略を理解し、縁を結べただけでも満足すべきだろう。
まず予定調和ではない終わり方にびっくりした。キリスト教の精神のあり方(特に「犠牲」に対する精神)は、日本人の一般的仏教の精神とは全く異質であることをこれでもかというように知らしめてくれる作品だった。
この作品には、元になる旭川市近くの塩狩峠における列車事故(1909年)と殉職したキリスト者がいた。それを著者が、キリスト教団体の要請を受けて後世に残すべく作品化したものである。明治時代後半(日清・日露戦役頃)の日本におけるキリスト教信仰と、仏教的伝統をもつ日本社会との軋轢、確執のあり様を知ることができる。明治にキリスト教がどう見られていたのか、キリスト教徒となることの重さ、大変強い土性骨の必要さ、神と向かい合うことの本気さがよく伝わってきた。
「信仰」というものの語感が、少しだけ現実味をもって感じられた。
【表紙裏紹介文】結納のため、札幌に向った鉄道職員永野信夫の乗った列車は、塩狩峠の頂上にさしかかった時、突然客車が離れて暴走し始めた。声もなく恐怖に怯える乗客。信夫は飛びつくようにハンドブレーキに手をかけた……。明治末年、北海道旭川の塩狩峠で、自らを犠牲にして大勢の乗客の命を救った一青年の、愛と信仰に貫かれた生涯を描き、生きることの意味を問う長編小説。