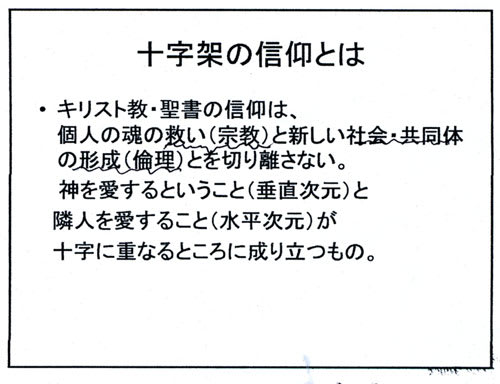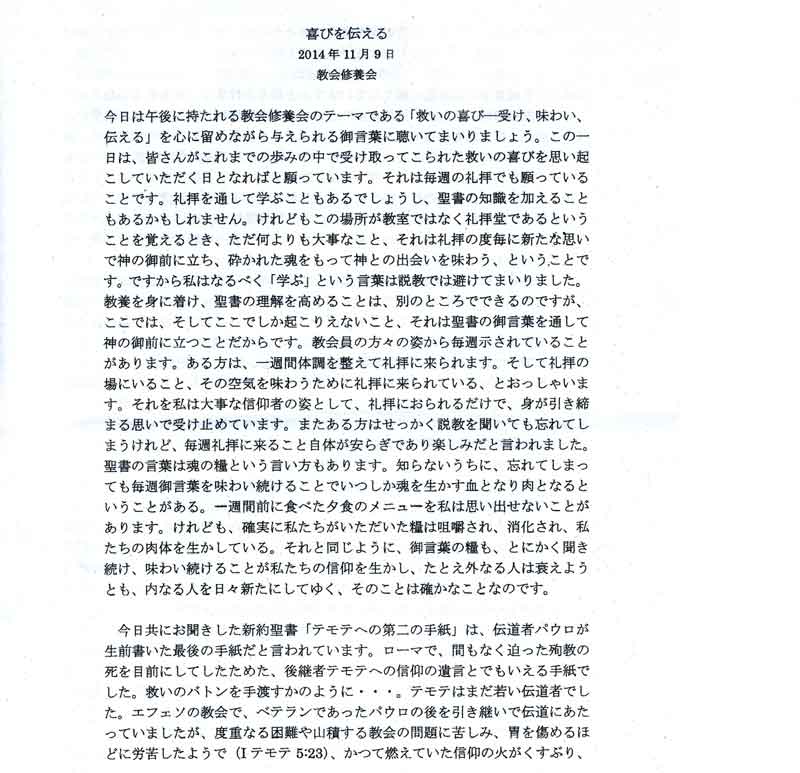讃美歌529番 「ああうれし、我が身も」 先週の礼拝で歌いました。
1)ああうれし、我が身も 主のものとなりけり
浮世だにさながら 天つ世の心地す
Chorus:
歌わでやあるべき 救われし身の幸(さち)
たたえでやあるべき 御救いのかしこさ
2)残りなく御旨(みむね)に 任せたる心に
えも言えず妙なる 幻を見るかな
Repeat Chorus.
3)胸の波収まり 心いと静けし
我もなく世もなく ただ主のみいませり
Repeat Chorus.
この讃美歌は、アメリカの盲目詩人Frances Jane (Crosby)Van Alstyne(1820-1915 一般にファニー・クロスビーと呼ばれている)が
歌詞した。 彼は友人であり作曲家及び歌手として知られていた Phoebe Parlmer Knapp(1839-1908)がある曲を作り
これに合った歌詞を書いて欲しいと頼まれて、その曲の美しさに感動してこの歌詞を書いたという。
これは曲の方が先にでき、歌詞がそれに従った少数の場合の一つである。
ファニー・クロスビー:生涯に6000以上もの歌詞を作詞したが、その単純さと熱誠が人気をもたらした。
Phoebe Parlmer Knapp(1839-1908)は讃美歌の作曲者でありまたオルガニストでもあった。
彼女はW.C.Parlmerの娘としてニューヨーク市に生まれた。
結婚したJ.F.Knapp氏は保険会社の設立者で会社の副社長でもあり、家にはパイプオルガンが設置されていた。
彼女と夫はJohn Street Methodist Episcopal church の会員で、美歌作家のファニー・クロスビーは会員であり
彼らの友人でもあった。
彼女は500以上の讃美歌曲を書いた。
最も親しまれているのはクロスビーの詩“ASSERANCE” のために書いた“Blessed Assurance” であろう。
彼女は Poland, Mine in USA で亡くなった。 (以上、ネットからの引用です。)
ココをクリックすると讃美歌529番を聴くことができます。
女性8名、男性3名の奈良教会の聖歌隊、こんなにも力強い歌声が出せるんですね~
美竹教会では毎月第一主日の礼拝後、少人数ですが、讃美歌練習をしています。
大丈夫、大丈夫! 聖歌隊として十分活躍できますね! ファイッ!!

冬鳥の<ツグミ>を今シーズン初めて見ました。
春に旅立つまで、公園で姿を見せてくれることでしょう。
美竹教会のホームページです、クリックしてお訪ねください。
1)ああうれし、我が身も 主のものとなりけり
浮世だにさながら 天つ世の心地す
Chorus:
歌わでやあるべき 救われし身の幸(さち)
たたえでやあるべき 御救いのかしこさ
2)残りなく御旨(みむね)に 任せたる心に
えも言えず妙なる 幻を見るかな
Repeat Chorus.
3)胸の波収まり 心いと静けし
我もなく世もなく ただ主のみいませり
Repeat Chorus.
この讃美歌は、アメリカの盲目詩人Frances Jane (Crosby)Van Alstyne(1820-1915 一般にファニー・クロスビーと呼ばれている)が
歌詞した。 彼は友人であり作曲家及び歌手として知られていた Phoebe Parlmer Knapp(1839-1908)がある曲を作り
これに合った歌詞を書いて欲しいと頼まれて、その曲の美しさに感動してこの歌詞を書いたという。
これは曲の方が先にでき、歌詞がそれに従った少数の場合の一つである。
ファニー・クロスビー:生涯に6000以上もの歌詞を作詞したが、その単純さと熱誠が人気をもたらした。
Phoebe Parlmer Knapp(1839-1908)は讃美歌の作曲者でありまたオルガニストでもあった。
彼女はW.C.Parlmerの娘としてニューヨーク市に生まれた。
結婚したJ.F.Knapp氏は保険会社の設立者で会社の副社長でもあり、家にはパイプオルガンが設置されていた。
彼女と夫はJohn Street Methodist Episcopal church の会員で、美歌作家のファニー・クロスビーは会員であり
彼らの友人でもあった。
彼女は500以上の讃美歌曲を書いた。
最も親しまれているのはクロスビーの詩“ASSERANCE” のために書いた“Blessed Assurance” であろう。
彼女は Poland, Mine in USA で亡くなった。 (以上、ネットからの引用です。)
ココをクリックすると讃美歌529番を聴くことができます。
女性8名、男性3名の奈良教会の聖歌隊、こんなにも力強い歌声が出せるんですね~
美竹教会では毎月第一主日の礼拝後、少人数ですが、讃美歌練習をしています。
大丈夫、大丈夫! 聖歌隊として十分活躍できますね! ファイッ!!

冬鳥の<ツグミ>を今シーズン初めて見ました。
春に旅立つまで、公園で姿を見せてくれることでしょう。
美竹教会のホームページです、クリックしてお訪ねください。