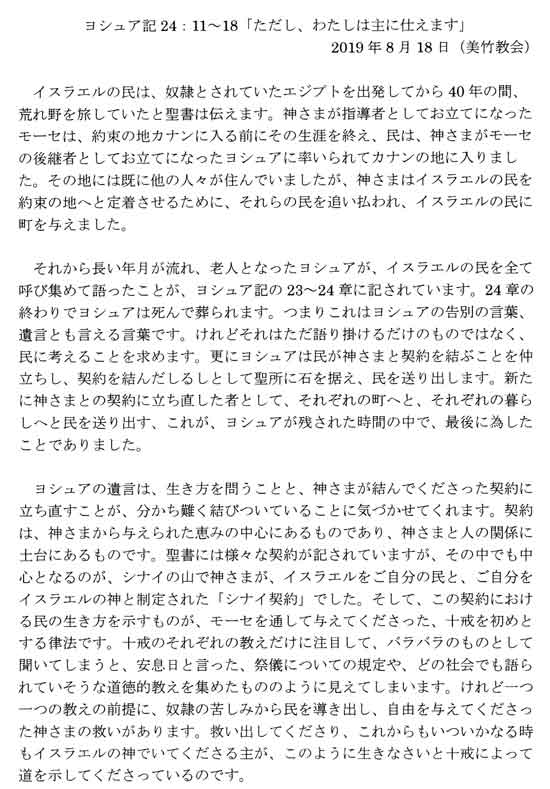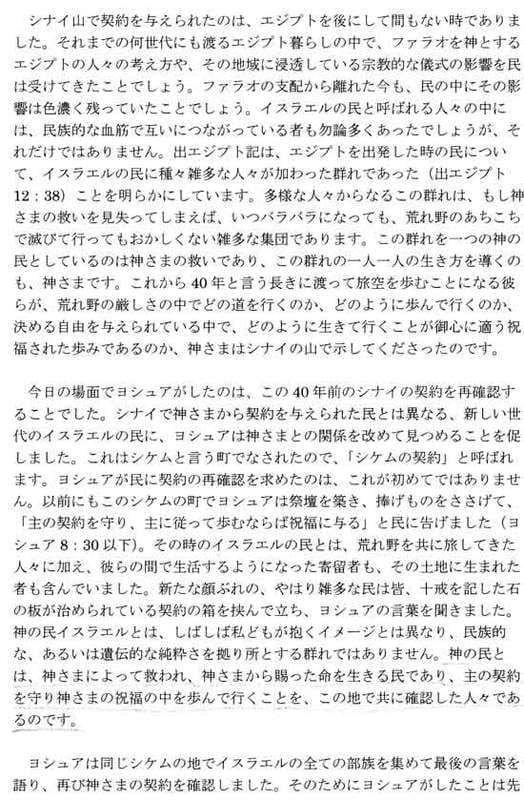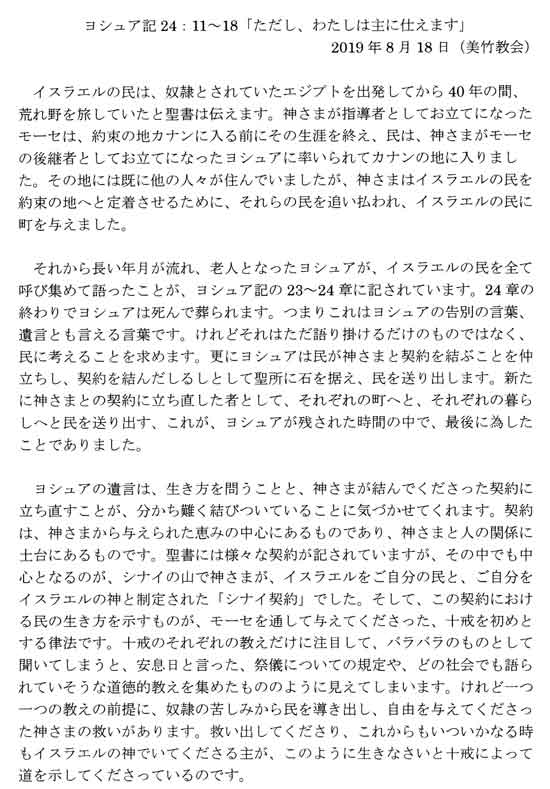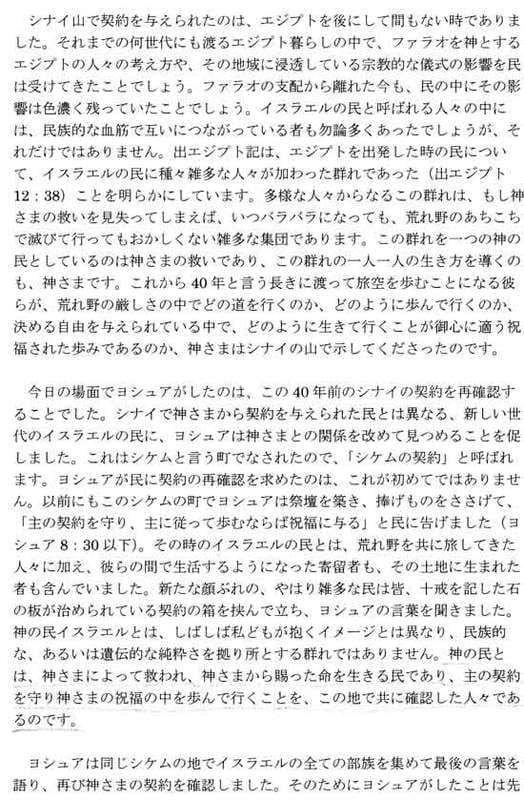讃美歌288番 「たえなるみちしるべの光よ」
“Lead, Kindly Light, amid the encircling gloom” by John Henry Newman, 1833
「LUX BENIGNA」by John Bacchus Dykes, 1865
1)たえなる道しるべの光よ、家路もさだかならぬやみ夜に、
さびしくさすらう身を 導きゆかせたまえ。
2)行く末遠く見るを願わじ、主よ、わが弱き足を守りて、
ひとあし、またひとあし、道をば示したまえ。
3)あだなる世の栄えを喜び、誇りておのが道を歩みつ、
むなしく過ぎにし日を わが主よ、忘れたまえ。
4)標(しるべ)となりたまいし光よ、今よりなおも野路に山路に、
闇夜のあけゆくまで、導きゆかせたまえ。
5)とこ世の朝に覚(さ)むるそのとき、しばしの別れをだに嘆きし
愛するものの笑顔、御国にわれを迎えん
■ジョン・ヘンリー・ニューマン(John Henry Newman 1801-1890 英国)の代表作であり、
近代讃美歌の代表と言える。
彼の初めてのイタリア訪問の時、シチリアで病気になり、Giovanni城で静養した後、
帰国のため到着したパレルモで、国に向かう船がなく3週間滞在を余儀なくされた。
その時、パレルモにある教会を巡り歩きやっと心の平安を得ることが出来た。
マルセイユ行きの船に乗り込んだが、コルシカ島とサルジニア島との間のボニファチオ海峡で
霧のため丸一週間船は行く手を阻まれた。その時に、この詞が浮かんだという。
詞の題名は「雲の柱 The Piller of Cloud」で、モーゼがイスラエルの民を引き連れて
エジプトより逃れてカナンの地に向かう途中で、イスラエルの神が「雲の柱」で行く手を
先導した物語を想定したものと思われる。讃美歌の題名「みちびきゆかせたまえ Lead,
Kindly Light....」は、歌詞の出だしから取ったものである。
■作曲者ジョン・B・ダイクス(John Bacchus Dykes 1823-1876 英国)はある日、霧のかかった
ロンドンのテムズ河畔を散歩している時、空の一方に美しい虹を見た。
その時、彼の心に浮かんだのがニューマンの詞「雲の柱」であった。
彼は直ちにこれに対する楽想を練って、一気に作曲した。1865年8月29日であった。
翌々年、この曲はBarryの出版した「Psalms and Hymns」に讃美歌の曲名となった「LUX BENIGNA
(kindly lightのラテン語)」という曲名で発表された。更に翌1868年、「Hymns Ancient and
Modern」の初版(1861年)の補遺版が出版された時、ダイクスは、この曲を書き改めて、
同じ曲名でその補遺に取り入れた。以来この形が英米の讃美歌集に載ることとなった。
作詞者ニューマンは、この讃美歌の註解において、『この讃美歌が普及したのは、歌詞の
ためではなく、その曲のためである。この曲を作ったのはダイクスであり、ダイクス博士こそ
偉大な芸術家である』と謙譲に曲を称賛している。この原詩は、心の底から光を求める叫びで
あり、曲はその気持ちを充分に現している。
■ジョン・ヘンリー・ニューマンは、ロンドンの銀行家の子として生まれ、オックスフォードに学び、
優秀の成績で卒業後、特別校友、学生監等を経て、同学内の聖メアリ教会牧師に任じられ、幾多の
名説教をした。
1845年、ローマ・カトリック教会に転じ、イギリスの社会に非常な衝撃を与えた。
■ジョン・B・ダイクスは、牧師を祖父とし、銀行家を父にもち、ケンブリッジ在学中に大学音楽協会
(University Musical Society)の指揮者に推され、、1849年には、ダラム(Durham)大聖堂の
評議員兼聖歌隊長となり、後にダラム大学は彼に『音楽博士』の学位を贈った。
300曲に上る讃美歌の作曲をし、又、英国讃美歌史上の歴史的事業である「Hymns Ancient and Modern」の
編集に関与して重要な役割を果した。特に保守的な英国讃美歌の伝統を破って、当時の通俗的歌曲に
もとづいた新しい形の讃美歌曲を書いた点に彼の特色が認められる。ダイクスの曲が英国的でありながら、
民謡的色彩を持ち、大衆通俗性を持っているのは、彼の曲のこういう性格にもとづいている。
讃美歌に採用されているダイクス作曲の曲は「聖なる、聖なる、聖なるかな 66番」他18曲ある。
ココをクリックすると讃美歌288番を聴くことができます。
この讃美歌は以前このブログに載せたことがありますが、
今回ネットで調べたらさらに詳しい解説が載っていました。再掲いたします。
美竹教会のホームページです、クリックしてお訪ねください。
フェイスブックやツィッターもご覧ください。

梅雨が開けた途端に物凄い暑さ!
皆さま、お大事にお過ごしください。
花は梅雨の朝の<ヒルガオ>です。