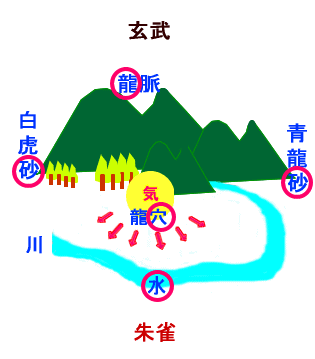今まで数十年間も日月星の神霊を追いかけてきたし
日月神示も相当に読み解いてきたのだが
日月星と日月は別の神霊系統(信仰系統)であることに
全く気づいていなかった。
日月星は三柱であり造化三神であり三位一体の系統である。
「天之御中主神」「高御産巣日神」「神産巣日神」
「天照大神」「月読大神」「素盞嗚神」
「妙見神」「妙音神」「妙理神」
「幸の神」「久那斗の大神」「猿田彦大神」
あるいはカバラで表わすと
「峻厳の柱=女性性」「慈悲の柱=男性性」「均衡の柱=子の柱」
キリスト教では三位一体を
唯一神の父(神)、子(キリスト)、聖霊の3つの姿というが
△図のように上に頂点があるということを一神教では強調している。
それでも母を精霊の中に隠したことは罪深く感じられる。
筆者的には▽の方がシックリくる。
私の感応においては
おおざっぱに云って日月星は生命の血統を意味している。
それに対して
日月とは日=陽 月=陰の陰陽太極の系統であり
そこから全てが産まれ出るという事でつまりは神羅万象となる。
おおざっぱに云って霊的な生成であり生まれ変わりの神霊系統である。
感覚としては0と1で成り立つ二進法の世界をイメージしていただきたい。
現在のコンピューターを含めた電子情報世界は
日=陽=(+)と月=陰=(-)で驚くことに全てが表現されていて
星の入り込む余地がないように観える。
量子コンピューターが登場して初めて日月星の世界となるのであろう。
最近になって周易を研究している。
そこに至った理由は興味深いので後で示すが、
「易に太極あり、これ両儀を生じ、両儀は四象を生じ、四象は八卦を生ず」と云われている。

私見ではこの太極図の発案は縄文の二個の勾玉由来である。
魏志倭人伝より
「壹與遣倭大夫率善中郎將掖邪拘等二十人 送政等還
因詣臺 獻上男女生口三十人 貢白珠五千孔 青大句珠二枚 異文雑錦二十匹」
「壱与は大夫の率善中郎将、掖邪拘等二十人を派遣して、張政等が帰るのを送らせた。
そして、 臺(中央官庁)に至り、男女の生口三十人を献上し、
白珠五千孔、青大句珠二枚、模様の異なる 雑錦二十匹を貢いだ。」
白玉5000個と青くて大きく曲がった青い玉≒緑の玉(翡翠の勾玉)2個を
献上している。
この時に勾玉の形状の由来についての説明もされたはずだと思う。
ビルマの本翡翠が中国にもたらされるのは後代の18世紀の事なので
中国での本翡翠の初見となると思われる。
そして勾玉が2個であることに深い意味が感じられる。
記紀においてまず登場するのは造化三神なのだが
何故か具体的に国生みをするのはイザナギ・イザナミの二柱神で
今まで何の違和感も感じていなかったが
イザナギ・イザナミの神の話と造化三神の話は
二つの民族の信仰系統を一つの神話にまとめ上げたものであり
具体的にいうと『日月星と日月は別の神霊系統』ということである。
さて周易を研究するに至った話であるが ⇒記載途中 写真準備
周易の世界観は陰と陽を中心として成り立っている。
占法としては基本的に銭の裏表を複数回確認することにより占うのであるが
これを簡略化?というか可視化して竹ひご50本使った筮竹で占う事が多い。
これだと三回の手順で下卦8種×上卦8種×爻6種=384種を導き出せる。
ところが周易から発展したと思われる断易(四柱推命と共通項目が多い)では
一回の擲銭(投銭)に三枚の銭を使って単なる表裏だけでなく
8回に1度の確率の表表表と裏裏裏を重視して陰陽を入れ替えたりと
プログラム的には不可思議な変数を挿入している。
なぜ二進法の易の世界に三の世界が貫入しているのか、
今まで不思議とも思わなかったが
日月の陰陽の信仰系統に
日月星の信仰系統が攻め込んできたと考えると納得出来る。
たぶん「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」の
十干は日月系で
「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」の
3×4の十二支は日月星系だと仮定すると
日月系神霊と日月星系神霊との系統上の交わりで
齟齬が生じる部分が空亡=天中殺となるのがなんとなく理解できる。
断易や四柱推命では十二支の巡りの中で2組の相性だけでなく
3組の組み合わせも重視している。
説明は省くが三合・支合・七冲・六害・三刑と自刑などの組み合わせであるが
周易の陰陽の世界観を超えているように感じる。
もっとも断易や四柱推命には五行「木・火・土・金・水」も組み込まれており
筆者に神霊世界の全貌が見えている訳ではない。
※空亡=天中殺とは十干と十二支を組み合わせたときに出来る余りの
二支のことで干支において天が味方しない時を意味する。
あと関係があるのか判らないがロムルス暦では一年を10か月としているらしい。
※周易の世界が384種で成り立つのに対して断易はさらに多くの要素が含まれ
相当な展開となる。その分曖昧な解釈ともなり易い欠点もある。
記載途中
日月神示も相当に読み解いてきたのだが
日月星と日月は別の神霊系統(信仰系統)であることに
全く気づいていなかった。
日月星は三柱であり造化三神であり三位一体の系統である。
「天之御中主神」「高御産巣日神」「神産巣日神」
「天照大神」「月読大神」「素盞嗚神」
「妙見神」「妙音神」「妙理神」
「幸の神」「久那斗の大神」「猿田彦大神」
あるいはカバラで表わすと
「峻厳の柱=女性性」「慈悲の柱=男性性」「均衡の柱=子の柱」
キリスト教では三位一体を
唯一神の父(神)、子(キリスト)、聖霊の3つの姿というが
△図のように上に頂点があるということを一神教では強調している。
それでも母を精霊の中に隠したことは罪深く感じられる。
筆者的には▽の方がシックリくる。
私の感応においては
おおざっぱに云って日月星は生命の血統を意味している。
それに対して
日月とは日=陽 月=陰の陰陽太極の系統であり
そこから全てが産まれ出るという事でつまりは神羅万象となる。
おおざっぱに云って霊的な生成であり生まれ変わりの神霊系統である。
感覚としては0と1で成り立つ二進法の世界をイメージしていただきたい。
現在のコンピューターを含めた電子情報世界は
日=陽=(+)と月=陰=(-)で驚くことに全てが表現されていて
星の入り込む余地がないように観える。
量子コンピューターが登場して初めて日月星の世界となるのであろう。
最近になって周易を研究している。
そこに至った理由は興味深いので後で示すが、
「易に太極あり、これ両儀を生じ、両儀は四象を生じ、四象は八卦を生ず」と云われている。

私見ではこの太極図の発案は縄文の二個の勾玉由来である。
魏志倭人伝より
「壹與遣倭大夫率善中郎將掖邪拘等二十人 送政等還
因詣臺 獻上男女生口三十人 貢白珠五千孔 青大句珠二枚 異文雑錦二十匹」
「壱与は大夫の率善中郎将、掖邪拘等二十人を派遣して、張政等が帰るのを送らせた。
そして、 臺(中央官庁)に至り、男女の生口三十人を献上し、
白珠五千孔、青大句珠二枚、模様の異なる 雑錦二十匹を貢いだ。」
白玉5000個と青くて大きく曲がった青い玉≒緑の玉(翡翠の勾玉)2個を
献上している。
この時に勾玉の形状の由来についての説明もされたはずだと思う。
ビルマの本翡翠が中国にもたらされるのは後代の18世紀の事なので
中国での本翡翠の初見となると思われる。
そして勾玉が2個であることに深い意味が感じられる。
記紀においてまず登場するのは造化三神なのだが
何故か具体的に国生みをするのはイザナギ・イザナミの二柱神で
今まで何の違和感も感じていなかったが
イザナギ・イザナミの神の話と造化三神の話は
二つの民族の信仰系統を一つの神話にまとめ上げたものであり
具体的にいうと『日月星と日月は別の神霊系統』ということである。
さて周易を研究するに至った話であるが ⇒記載途中 写真準備
周易の世界観は陰と陽を中心として成り立っている。
占法としては基本的に銭の裏表を複数回確認することにより占うのであるが
これを簡略化?というか可視化して竹ひご50本使った筮竹で占う事が多い。
これだと三回の手順で下卦8種×上卦8種×爻6種=384種を導き出せる。
ところが周易から発展したと思われる断易(四柱推命と共通項目が多い)では
一回の擲銭(投銭)に三枚の銭を使って単なる表裏だけでなく
8回に1度の確率の表表表と裏裏裏を重視して陰陽を入れ替えたりと
プログラム的には不可思議な変数を挿入している。
なぜ二進法の易の世界に三の世界が貫入しているのか、
今まで不思議とも思わなかったが
日月の陰陽の信仰系統に
日月星の信仰系統が攻め込んできたと考えると納得出来る。
たぶん「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」の
十干は日月系で
「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」の
3×4の十二支は日月星系だと仮定すると
日月系神霊と日月星系神霊との系統上の交わりで
齟齬が生じる部分が空亡=天中殺となるのがなんとなく理解できる。
断易や四柱推命では十二支の巡りの中で2組の相性だけでなく
3組の組み合わせも重視している。
説明は省くが三合・支合・七冲・六害・三刑と自刑などの組み合わせであるが
周易の陰陽の世界観を超えているように感じる。
もっとも断易や四柱推命には五行「木・火・土・金・水」も組み込まれており
筆者に神霊世界の全貌が見えている訳ではない。
※空亡=天中殺とは十干と十二支を組み合わせたときに出来る余りの
二支のことで干支において天が味方しない時を意味する。
あと関係があるのか判らないがロムルス暦では一年を10か月としているらしい。
※周易の世界が384種で成り立つのに対して断易はさらに多くの要素が含まれ
相当な展開となる。その分曖昧な解釈ともなり易い欠点もある。
記載途中