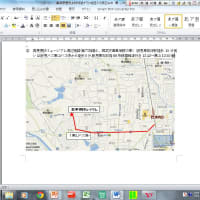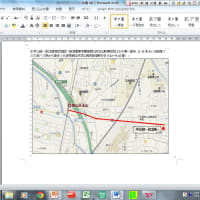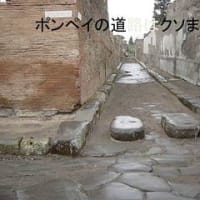谷井さん!ささやかな論文集を捧げます。あちらでご笑覧下さいよろしくお願いします。
僕たちの大事な大事な仲間谷井さんが亡くなって昨日で丁度1年になる。僕が実際にこの事実を知ったのは昨年の今日、京都第1赤十字病院の病室でだった。あまりのショックに自分のことなどどうでもよく悲嘆に暮れた。
もうあれから1年が経つのかと思うと、本当に月日の経つのは早い。
大学の最も親しかった仲間だけで『三重大史学第8号』を追悼号として出すことにした。奥様で同じ時代の研究者でもある谷井陽子さんが谷井さんの残された研究をまとめて巻頭論文として載せて下さった。
『宗国史』の歴史叙述 谷井俊仁・谷井陽子
嗚呼、谷井俊仁さん 廣岡義隆
慰労詔書書式の変遷に関する覚書 山中 章
道中記研究の可能性 塚本明
鈴鹿峠と坂上田村麻呂 山田雄司
私の駄文を除けば、みなさん、心のこもった追悼論文ばかりである。
(ちなみに1冊1000円で〒514-8507 津市栗真町屋町1577 三重大学人文学部 山田雄司研究室 で取り扱っている。)
彼を死へ追いやった病の原因は私には判っている。その追及の手は今は取りあえず封印して、改めて追悼の気持ちをここに捧げておくことにする。本当に悲しく、寂しい。そしてこれだけの逸材を失った三重大学の損失は計り知れない。しかしそのことに気付くこともなく人文学部文化学科は益々骨の髄まで腐敗が進行している。
追悼
拙文が対象とした慰労詔書(制書)のような中国の制度に由来する日本の制度研究には東洋史の素養が欠かせない。1年前までは、こうした時にいつも気軽に谷井俊仁さんに相談することができた。もちろん谷井さんは明清史が専門なのだが、その漢文の素養から文章の読みや意味をご教示頂いたのだった。
そんな谷井さんが亡くなられたと知ったのは丁度一年前の入院先のことだった。生まれて初めて突然医者から入院を命じられた私は京都東山の山麓にある日赤の病室で退屈な日々を過ごしていた。そんなある夜、着替えを届けに来た妻が妙なことを言って帰った。
さっき塚本先生から「谷○○さんという方が亡くなった」と電話してこられたと。谷の付く名前で存じ上げているのは3人しかいない。しかしどなたも調子が悪いなどとは聞いてもいなかったので、「エッツ?誰?ちゃんと聞いといてくれへんと・・・」と妻をなじったのだった。その「谷○○」さんが谷井さんと判るのにそう時間はかからなかった。
入院してまだ一週間も経たない我が身にはとても応えた。特に直前に私にお会いになりたがっていたと後に聞いたときには残念でならなかった。
谷井さんは私にとっては三重大の1年先輩だ。1997年に富山大から移って来られたと聞いた。見た目も、話すときも温厚な谷井さんと同じ歴史学ということもあって直ぐ親しくなった。教授会ではいつも僕が横に座らせてもらった。昼飯の「パセオ」でもご一緒することが多かった。学生の少なくなる13時前に行って、14時頃までだべるのがとても有意義だった。そんな時何気なく会話に出てくるのが奥様のことだった。
「彼女はね-大作主義なんですよ。きっちりまとめないと気が済まないんですよ。僕なんかは全く逆でね・・・」
勿論谷井さんがとてもきちんと研究されていることは言うまでもないのだが、それに輪をかけて調べ上げて、推敲に推敲を重ねて論文を書かれる奥様ってどんな人だろうと、いつしか尊敬するようになったものだった。それと共に、谷井さんのご家族への篤い思いを知ったのだった。
私が入院する直前、いつものように「パセオ」で会ったのが最後だった。
「山中さん、授業どうですか?」
これが谷井さんと交わした最後の言葉だった。その言葉の奥を察知できなかった僕のうかつさを悔やんでも悔やみきれない。
『三重大史学』読んでみようかなと思ったらよろしくね
僕たちの大事な大事な仲間谷井さんが亡くなって昨日で丁度1年になる。僕が実際にこの事実を知ったのは昨年の今日、京都第1赤十字病院の病室でだった。あまりのショックに自分のことなどどうでもよく悲嘆に暮れた。
もうあれから1年が経つのかと思うと、本当に月日の経つのは早い。
大学の最も親しかった仲間だけで『三重大史学第8号』を追悼号として出すことにした。奥様で同じ時代の研究者でもある谷井陽子さんが谷井さんの残された研究をまとめて巻頭論文として載せて下さった。
『宗国史』の歴史叙述 谷井俊仁・谷井陽子
嗚呼、谷井俊仁さん 廣岡義隆
慰労詔書書式の変遷に関する覚書 山中 章
道中記研究の可能性 塚本明
鈴鹿峠と坂上田村麻呂 山田雄司
私の駄文を除けば、みなさん、心のこもった追悼論文ばかりである。
(ちなみに1冊1000円で〒514-8507 津市栗真町屋町1577 三重大学人文学部 山田雄司研究室 で取り扱っている。)
彼を死へ追いやった病の原因は私には判っている。その追及の手は今は取りあえず封印して、改めて追悼の気持ちをここに捧げておくことにする。本当に悲しく、寂しい。そしてこれだけの逸材を失った三重大学の損失は計り知れない。しかしそのことに気付くこともなく人文学部文化学科は益々骨の髄まで腐敗が進行している。
追悼
拙文が対象とした慰労詔書(制書)のような中国の制度に由来する日本の制度研究には東洋史の素養が欠かせない。1年前までは、こうした時にいつも気軽に谷井俊仁さんに相談することができた。もちろん谷井さんは明清史が専門なのだが、その漢文の素養から文章の読みや意味をご教示頂いたのだった。
そんな谷井さんが亡くなられたと知ったのは丁度一年前の入院先のことだった。生まれて初めて突然医者から入院を命じられた私は京都東山の山麓にある日赤の病室で退屈な日々を過ごしていた。そんなある夜、着替えを届けに来た妻が妙なことを言って帰った。
さっき塚本先生から「谷○○さんという方が亡くなった」と電話してこられたと。谷の付く名前で存じ上げているのは3人しかいない。しかしどなたも調子が悪いなどとは聞いてもいなかったので、「エッツ?誰?ちゃんと聞いといてくれへんと・・・」と妻をなじったのだった。その「谷○○」さんが谷井さんと判るのにそう時間はかからなかった。
入院してまだ一週間も経たない我が身にはとても応えた。特に直前に私にお会いになりたがっていたと後に聞いたときには残念でならなかった。
谷井さんは私にとっては三重大の1年先輩だ。1997年に富山大から移って来られたと聞いた。見た目も、話すときも温厚な谷井さんと同じ歴史学ということもあって直ぐ親しくなった。教授会ではいつも僕が横に座らせてもらった。昼飯の「パセオ」でもご一緒することが多かった。学生の少なくなる13時前に行って、14時頃までだべるのがとても有意義だった。そんな時何気なく会話に出てくるのが奥様のことだった。
「彼女はね-大作主義なんですよ。きっちりまとめないと気が済まないんですよ。僕なんかは全く逆でね・・・」
勿論谷井さんがとてもきちんと研究されていることは言うまでもないのだが、それに輪をかけて調べ上げて、推敲に推敲を重ねて論文を書かれる奥様ってどんな人だろうと、いつしか尊敬するようになったものだった。それと共に、谷井さんのご家族への篤い思いを知ったのだった。
私が入院する直前、いつものように「パセオ」で会ったのが最後だった。
「山中さん、授業どうですか?」
これが谷井さんと交わした最後の言葉だった。その言葉の奥を察知できなかった僕のうかつさを悔やんでも悔やみきれない。
『三重大史学』読んでみようかなと思ったらよろしくね