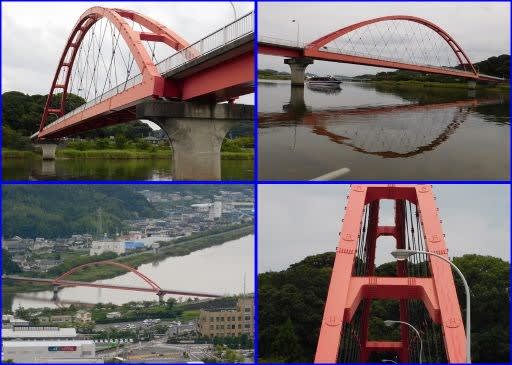ご近所で、色の変化が楽しめる酔芙蓉(」(スイフヨウ)の花が咲いています。
酔芙蓉の花は、朝、白いつぼみから開花し、時間の経過とともにピンク色に、夕方には赤色に染まる1日花です。
酒を飲むと顔色がだんだんと赤みを帯びるのに似ていることからこの名がついたといわれています。
酔芙蓉はフヨウ科の落葉低木です。フヨウ(一重咲き)の園芸品種として八重咲の酔芙蓉が生まれたとのことです。
現産地は中国や日本の南部と言われています。


(朝7時ころの酔芙蓉。純白のすがすがしい色をしています。)


(午後1時ころの酔芙蓉。ちょっとお酒が入ったか、ほろ酔い加減の薄いピンク色に変化。)


(夕刻5時半ごろの酔芙蓉。かなり酔いが回って来ましたね。濃いピンク色に変わりました。)
この後もっと遅い時間(懐中電灯が必要な位)に向かえば、赤色は更に進んだかも。
そして、翌朝の酔芙蓉は、もっと赤く染まりしぼんでしまっています。《かなりお酒をいただいたのかも》それが上の小画像です。《クリックすると拡大します)
酔芙蓉の花は、朝、白いつぼみから開花し、時間の経過とともにピンク色に、夕方には赤色に染まる1日花です。
酒を飲むと顔色がだんだんと赤みを帯びるのに似ていることからこの名がついたといわれています。
酔芙蓉はフヨウ科の落葉低木です。フヨウ(一重咲き)の園芸品種として八重咲の酔芙蓉が生まれたとのことです。
現産地は中国や日本の南部と言われています。


(朝7時ころの酔芙蓉。純白のすがすがしい色をしています。)


(午後1時ころの酔芙蓉。ちょっとお酒が入ったか、ほろ酔い加減の薄いピンク色に変化。)


(夕刻5時半ごろの酔芙蓉。かなり酔いが回って来ましたね。濃いピンク色に変わりました。)
この後もっと遅い時間(懐中電灯が必要な位)に向かえば、赤色は更に進んだかも。
そして、翌朝の酔芙蓉は、もっと赤く染まりしぼんでしまっています。《かなりお酒をいただいたのかも》それが上の小画像です。《クリックすると拡大します)