原作は少し甘いナイーブなところのある小説だけど好きでした。
そもそも、ピアノやバイオリンなどの楽器をめぐる話には、めっぽう弱いし、甘いです。
(「蜜蜂と遠雷」も映画化ならないかなぁと思ってます。
映画化になったら若手アイドル俳優映画にされる危険が高いにしても。)
映画の方は、まあ大体予想通りに普通にイマドキの邦画になってた。
安っぽい、のちょっと手前くらいかなー。
とはいえ、ああ今時のワカイコ向きお子様映画、というほどひどくないのは
恋愛要素がないせいかもしれません。
「恋愛」は素敵だけど、物語を安っぽくすることも多いですからねぇ。
これも、若い人の青春、成長物語ではあるけど、地味な世界の地味な子の話なので
チャラチャラ要素が出てこないのも、安心なところです。
(チャラチャラ要素も、盛大にやってくれてる映画は、わりと好きですけど)
印象的な音に森が見える気がした、みたいなシーンで
急に木の影がわさわさ大きくなったり
音を探して焦っているシーンで森の中を必死で彷徨うイメージがかぶさったり、
そういう、ベタというか安直なところは、演出もカメラもどちらにも多いけど、
キャスティングがかなりイメージ通りなところは、感心しました。
主人公も周りの人たちも、ピアノを弾く姉妹も、小説のイメージを壊すことなく
すんなり納得出来る俳優さんで、見るのが楽だった。
高校で、とある調律師の作る音を耳にして、自分も調律師になることを目指す青年。
北海道で育った彼は東京の専門学校を卒業した後、札幌の楽器店に勤めることになり
高校で出会った尊敬する調律師や先輩たちや様々な顧客の中、
調律を通して成長していく、というお話。
わたしは、目が良ければ修復士になりたかったし、
耳が良ければ調律師になりたかったし
自分の地味な性質には職人が向いてると思うけど、
若い頃にはそういうことがよくわかってなかったなぁ。
わかってても、どうしようもなかったけど。
いや、若い頃から自分が地味な人間なのはわかってたけど、
コツコツしたことができると思ってなかったのよね。
でも今やコツコツしかできないようになってしまった。
コツコツの楽しさもわかってきたけど、わかるのがちょっと遅かったな〜。
そして、映画見てると調律のあとでピアノの持ち主が華麗に何か弾いて、
これで良いと言ったり、音色を変えてと言ったりするのですが、
わたしはいきなり何か弾いたりできないし、
弾けてもソナチネポロンポロンレベルなので、いつもこの時が恥ずかしくて困る。
この映画見た時点で、家のピアノを10年以上ぶりに調律する予定があったのですが
なんか練習しとくべきか、悩みます。笑












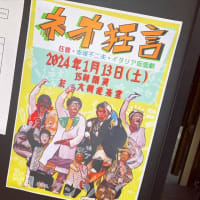





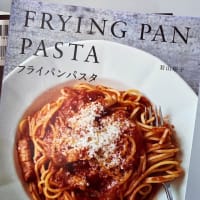

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます