
5回シリーズの講座の最終回。
1年もほったらかしてたんだけど、やっと終わりそうです。
とはいえ、昨日から、また続きの講座を受けているので
それは1年後くらいにまとめるのかも・・・(遅い)。
続きでは、今回の5回シリーズで軽く触れたもの、
ファッション、ドキュメンタリー、ポートレイトなどを
もう少し詳しく見るようです。
ジャンル分けは、一応のもので
現代美術にジェンダーが関わるものも多いし
きっちりした固定的なものではないですが、一応の目安ですね。
とりあえず5回シリーズの最終回は現代美術。
杉本博司(1948~)
明確な哲学のあるコンセプトを、しっかりした技術で
戦略的に作品にする方法で、初期の3部作で認められる。
「ジオラマ」シリーズ
NYで働きながらアートを学んでいたとき
自然史博物館でジオラマを片目で見ると遠近感が消えて
見え方が違い、
カメラでも肉眼よりも写真がかえって本物っぽいと気づき
それでジオラマを撮る。
「シアター(劇場)」シリーズ
映画1本分シャッターあけたままで絞り開放というバルブ撮影。
映画1本分の時間が1枚の写真に蓄積されている。
「シースケープ(海景)」シリーズ
画面を水平線で上下に分けて構成。静かな海の表面と空のモノクロ写真。
「アーキテクチャー(建築)」シリーズ
ピントをぼかした写真で、そのもの本来のイメージをさぐる。
「恐怖の館」シリーズ
マダム・タッソの作る蝋人形の写真
「観念の形」
数理模型と機構モデル群を撮影
「陰影礼賛」
ろうそくの炎だけを大きく写した写真。
「フォトジェニック・ドローイング(光子的素描)」シリーズ
写真発明したタルボットの
日光写真のようなネガであるが、形が写るという驚きと期待に満ちた
初期のネガを買い取ってプリントした。
「放電場」シリーズ
印画紙に通電、光が定着した写真。
などなど、説明だけではどんな写真かわからないと思うので
こちらを参考に→杉本博司サイト
それぞれのシリーズについて、わかりやすくまとめられています。
米田知子
コンセプトは記憶、歴史的記憶。
昔の作家の原稿などを、その作家ゆかりのメガネを通して撮った。
フロイトのメガネでユングの本を、
マーラーのメガネでシンフォニーの楽譜を撮影。
歴史的な事件のあった部屋を撮ったもののシリーズは
ヒトラーの泊まったホテルや
マッカーサーの執務室などを撮ったもの。
渡辺剛
Border、国境をテーマとし、
世界各地にある境界線で隔てられた二つの土地を撮影した
「Border and Sight」シリーズなど。
カトリックとプロテスタントの間の壁など、
人間の作った壁を意識した写真。
鷹野隆大(1963~
男性ヌードのポートレート写真を通して
ジェンダーを問う。
男性器部分は法律により?カットされている。
「ただのポルノじゃないか」と難じられたら、
「その通り」と答えられるようなものにしたいと思っている。」
澤田知子(1977ー
キャノンの若手写真家登竜門である写真新世紀出身。
セルフポートレイト写真で
自分の外見を多様に変身させた写真を撮る。
「ID400」は証明写真の機械で
400人分の変装をした自分自身の写真。
森村泰昌(1951ー
上述の澤田知子と同じくセルフポートレートの手法だけど、
扮するのは世界的に有名な絵画や有名人たち。
似た手法のシンディ・シャーマンは写真家と思ってたのに
なぜか、わたしは彼を写真家ではなく現代美術家と思ってたので
写真家の中に並ぶと不思議な感じがする。
Cindy Sherman(1954ー
コスチュームをつけた自分を撮影するセルフポートレイで
一番有名なのは彼女かもしれません。
1977年から1980年まで室外で制作されたモノクロ写真による
“アンタイトルズ・フィルム・スティール"シリーズは
仮想の映画スティール写真で、50年代のハリウッド映画の ワンシーンを
マリリン・モンローやソフィア・ローレン などに扮して撮影したもので、
まだ10代だったわたしにも、とても強い印象を与えました。
だから80年代半ば過ぎに森村泰昌(上記↑)の作品を見たときは
アメリカ美術のパクリだなぁと思ったのを覚えています。
バブルに乗じて、二番煎じが出てきたなぁと(笑)。
森村さんは今もばりばり活躍されて、
今や日本の現代美術会では大先生かもしれないけど(笑)。
Sandy Skogland
自分で舞台のすべてを構成して撮るメイクフォト。
作り込まれたセットの中に鮮やかに彩色されたマネキンやフィギュア、
人間を配置して撮る鮮烈な写真です。
元々彫刻家で、小道具類にもその影響はあるかも。
やなぎみわ
染色出身の写真家。
エレベーターガールをモチーフにした写真作品や、
若い女性が自らの半世紀後の姿を演じる写真作品、
少女と老女の物語をテーマにした写真と映像のシリーズ
「フェアリーテール」などで知られる。
Loretta Lux (1969ー/ドイツ)
子どものポートレイトのシリーズ
絵画っぽい不思議な遠近感がある写真。
きれいな色使いで、かわいい子どものシンプルなポートレイトなのに
複雑なものが隠されているように見えて、印象的で、
美術館で見たのをよく覚えています。
→作品と、自分のことを語った言葉の動画
Walfgang Tillmansドイツ(1968-/ドイツ)
若者文化をとらえたスナップから出発し
現在では現代アート作家としてみられることが多い。
無造作でとりとめもないスナップのようでいて計算されている写真。
展示の方法、大きさを意図的にバラバラにして
配置によるインスタレーションとして表現も。
Thomas Deman(1964ー/ドイツ)
一見普通のオフィスや室内に見えるが
実はデスクも椅子も壁も窓もライトもすべて紙で作った模型。
という写真で有名。
寺田真由美
がらんとしたシンプルな部屋に
風や光の差し込むモノクロ写真に見えるけど
これも実は、全部ミニチュアで、
ミニチュアを作ってセットして撮っている写真。
静かで美しい写真ですが、どこかに潜んでいる違和感が
奥行きをもたらしている。
横溝静
コンセプチュアルアート手法の写真。
まず、気に入った窓を見つけてその住所に手紙を出す。
そこで、その窓にいついつ10分間立っていて下さいとお願いし
その時間に訪ねて
そこに人がいて了解してもらえたなら写真を撮る、という方法。
Rineke Dijkstra (1957ーオランダ)
海の前にすとんと立った人のポートレートが知られている。
生まれたての赤ちゃんを抱いたポートレートや
闘牛のポートレートは闘牛直後、の血しぶきを浴びたものなど。
(女性写真家の項でもリネケ・ダイクストラとして触れています)
ベッヒャー夫妻
ベルント&ヒラ・ベッヒャーは50年代の終わりからモノクロで、
給水塔、冷却塔、溶鉱炉、鉱山などを撮りはじめた写真家。
大判カメラで正面からの構図、曇りの日にしか撮影しないという写真を
70年に『無名の彫刻-建造技術の類型学(タイポロジー)』としてまとめ、
ミニマリズムやコンセプチュアル・アートの文脈で高い評価を受ける。
ベッヒャー夫妻に影響を受けた写真家も多い。
1年もほったらかしてたんだけど、やっと終わりそうです。
とはいえ、昨日から、また続きの講座を受けているので
それは1年後くらいにまとめるのかも・・・(遅い)。
続きでは、今回の5回シリーズで軽く触れたもの、
ファッション、ドキュメンタリー、ポートレイトなどを
もう少し詳しく見るようです。
ジャンル分けは、一応のもので
現代美術にジェンダーが関わるものも多いし
きっちりした固定的なものではないですが、一応の目安ですね。
とりあえず5回シリーズの最終回は現代美術。
杉本博司(1948~)
明確な哲学のあるコンセプトを、しっかりした技術で
戦略的に作品にする方法で、初期の3部作で認められる。
「ジオラマ」シリーズ
NYで働きながらアートを学んでいたとき
自然史博物館でジオラマを片目で見ると遠近感が消えて
見え方が違い、
カメラでも肉眼よりも写真がかえって本物っぽいと気づき
それでジオラマを撮る。
「シアター(劇場)」シリーズ
映画1本分シャッターあけたままで絞り開放というバルブ撮影。
映画1本分の時間が1枚の写真に蓄積されている。
「シースケープ(海景)」シリーズ
画面を水平線で上下に分けて構成。静かな海の表面と空のモノクロ写真。
「アーキテクチャー(建築)」シリーズ
ピントをぼかした写真で、そのもの本来のイメージをさぐる。
「恐怖の館」シリーズ
マダム・タッソの作る蝋人形の写真
「観念の形」
数理模型と機構モデル群を撮影
「陰影礼賛」
ろうそくの炎だけを大きく写した写真。
「フォトジェニック・ドローイング(光子的素描)」シリーズ
写真発明したタルボットの
日光写真のようなネガであるが、形が写るという驚きと期待に満ちた
初期のネガを買い取ってプリントした。
「放電場」シリーズ
印画紙に通電、光が定着した写真。
などなど、説明だけではどんな写真かわからないと思うので
こちらを参考に→杉本博司サイト
それぞれのシリーズについて、わかりやすくまとめられています。
米田知子
コンセプトは記憶、歴史的記憶。
昔の作家の原稿などを、その作家ゆかりのメガネを通して撮った。
フロイトのメガネでユングの本を、
マーラーのメガネでシンフォニーの楽譜を撮影。
歴史的な事件のあった部屋を撮ったもののシリーズは
ヒトラーの泊まったホテルや
マッカーサーの執務室などを撮ったもの。
渡辺剛
Border、国境をテーマとし、
世界各地にある境界線で隔てられた二つの土地を撮影した
「Border and Sight」シリーズなど。
カトリックとプロテスタントの間の壁など、
人間の作った壁を意識した写真。
鷹野隆大(1963~
男性ヌードのポートレート写真を通して
ジェンダーを問う。
男性器部分は法律により?カットされている。
「ただのポルノじゃないか」と難じられたら、
「その通り」と答えられるようなものにしたいと思っている。」
澤田知子(1977ー
キャノンの若手写真家登竜門である写真新世紀出身。
セルフポートレイト写真で
自分の外見を多様に変身させた写真を撮る。
「ID400」は証明写真の機械で
400人分の変装をした自分自身の写真。
森村泰昌(1951ー
上述の澤田知子と同じくセルフポートレートの手法だけど、
扮するのは世界的に有名な絵画や有名人たち。
似た手法のシンディ・シャーマンは写真家と思ってたのに
なぜか、わたしは彼を写真家ではなく現代美術家と思ってたので
写真家の中に並ぶと不思議な感じがする。
Cindy Sherman(1954ー
コスチュームをつけた自分を撮影するセルフポートレイで
一番有名なのは彼女かもしれません。
1977年から1980年まで室外で制作されたモノクロ写真による
“アンタイトルズ・フィルム・スティール"シリーズは
仮想の映画スティール写真で、50年代のハリウッド映画の ワンシーンを
マリリン・モンローやソフィア・ローレン などに扮して撮影したもので、
まだ10代だったわたしにも、とても強い印象を与えました。
だから80年代半ば過ぎに森村泰昌(上記↑)の作品を見たときは
アメリカ美術のパクリだなぁと思ったのを覚えています。
バブルに乗じて、二番煎じが出てきたなぁと(笑)。
森村さんは今もばりばり活躍されて、
今や日本の現代美術会では大先生かもしれないけど(笑)。
Sandy Skogland
自分で舞台のすべてを構成して撮るメイクフォト。
作り込まれたセットの中に鮮やかに彩色されたマネキンやフィギュア、
人間を配置して撮る鮮烈な写真です。
元々彫刻家で、小道具類にもその影響はあるかも。
やなぎみわ
染色出身の写真家。
エレベーターガールをモチーフにした写真作品や、
若い女性が自らの半世紀後の姿を演じる写真作品、
少女と老女の物語をテーマにした写真と映像のシリーズ
「フェアリーテール」などで知られる。
Loretta Lux (1969ー/ドイツ)
子どものポートレイトのシリーズ
絵画っぽい不思議な遠近感がある写真。
きれいな色使いで、かわいい子どものシンプルなポートレイトなのに
複雑なものが隠されているように見えて、印象的で、
美術館で見たのをよく覚えています。
→作品と、自分のことを語った言葉の動画
Walfgang Tillmansドイツ(1968-/ドイツ)
若者文化をとらえたスナップから出発し
現在では現代アート作家としてみられることが多い。
無造作でとりとめもないスナップのようでいて計算されている写真。
展示の方法、大きさを意図的にバラバラにして
配置によるインスタレーションとして表現も。
Thomas Deman(1964ー/ドイツ)
一見普通のオフィスや室内に見えるが
実はデスクも椅子も壁も窓もライトもすべて紙で作った模型。
という写真で有名。
寺田真由美
がらんとしたシンプルな部屋に
風や光の差し込むモノクロ写真に見えるけど
これも実は、全部ミニチュアで、
ミニチュアを作ってセットして撮っている写真。
静かで美しい写真ですが、どこかに潜んでいる違和感が
奥行きをもたらしている。
横溝静
コンセプチュアルアート手法の写真。
まず、気に入った窓を見つけてその住所に手紙を出す。
そこで、その窓にいついつ10分間立っていて下さいとお願いし
その時間に訪ねて
そこに人がいて了解してもらえたなら写真を撮る、という方法。
Rineke Dijkstra (1957ーオランダ)
海の前にすとんと立った人のポートレートが知られている。
生まれたての赤ちゃんを抱いたポートレートや
闘牛のポートレートは闘牛直後、の血しぶきを浴びたものなど。
(女性写真家の項でもリネケ・ダイクストラとして触れています)
ベッヒャー夫妻
ベルント&ヒラ・ベッヒャーは50年代の終わりからモノクロで、
給水塔、冷却塔、溶鉱炉、鉱山などを撮りはじめた写真家。
大判カメラで正面からの構図、曇りの日にしか撮影しないという写真を
70年に『無名の彫刻-建造技術の類型学(タイポロジー)』としてまとめ、
ミニマリズムやコンセプチュアル・アートの文脈で高い評価を受ける。
ベッヒャー夫妻に影響を受けた写真家も多い。












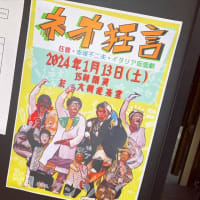





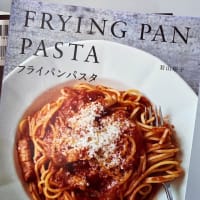

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます