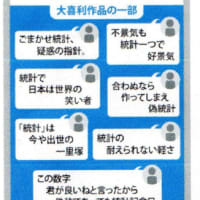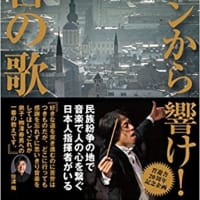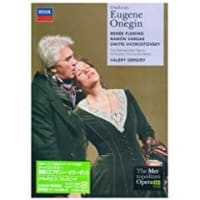3.11の東日本大震災、それによって引き起こされた津波により、多くの人びとが家族を失い、親しい友人、恋人を亡くし、家を失い、仕事を失い、人生そのものを奪われ、希望を失っている。そして、地震と津波によって引き起こされた福島の原子力発電所の事故は、これまで盲信されてきた「安全神話」を崩壊させた。とりわけ、放射能による土壌、大気、海洋の汚染は、地域住民に甚大な健康被害と経済的損失をもたらした。避難することを余儀なくされた人びとは、ふるさとを離れなければならず、その避難生活は長期化すると予測されているが、このことは土地をふくめ生活基盤を根こそぎ奪われ、伝統と文化までも奪いかねない。これまでにない社会問題が提起されている。
まさにチェルノブイリ原子力発電所の事故が起きた1986年、貧困、社会的不平等の研究者として著名な研究者であるU. Beckは 、その著書『危険な社会』(Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986,Suhrkamp Verlag)のなかで次のように新たに登場する生活破壊をもたらす危険社会について指摘している。
「これまで、人間が人間に与えてきた苦悩、困窮、暴力は例外なく『他者』というカテゴリーが存在していたが、しかし、チェルノブイリ以降、実質的にそれは存在しなくなった。二つの大戦、アウシュビッツ、広島・長崎までは敵国と味方とか人種とかという境界があったが、スリーマイルアイランドをはじめとしてチェルノブイリの事故はわれわれの生活を破壊するリスクが、境界を超えるようになったことを示している。」
常にだれもが生活破壊に直面するという「リスク社会」の到来を鋭く説いているが、くわえて、9.11以後の「テロとの闘争」を考えれば、世界のどこにいてもテロにまきこまれることも新たなリスクにくわわったということもいえ、多様なリスクに脅かされている社会に我々は生きていることを再認識せざるを得ないだろう。
Beckのいうまさにリスク社会という生活破壊の可能性を常に秘めた社会のただなかにあって、われわれは何をどのように現代社会をとらえ、なにを問題とし、解決のための具体的方策をたて、実践していくべきなのだろうか。
貧困や生活問題は、戦前戦後を通して、内外を問わず、社会福祉の中心的なテーマであり続けてきた。しかし、市場原理主義、競争と成果主義、効率重視の風潮、価値のなかで、「豊かな社会」の到来がいわれ、我が国の社会福祉において、貧困は、昨今、マイナーなテーマとなっていた。研究的蓄積も必ずしも多いとは言えなくなっていた。市場原理のなかで、成果主義は広く受けいれられ、個人の努力や能力の結果によって富がもたらされるのだから、努力したものがその富の恩恵に浴することは当然であり、格差は仕方のないこと、格差があって何がわるいのか、という言説が広まっていた。その結果、失業や事業の失敗は個人の努力の怠りであり、結果としてもたらされた貧困は、個人の責任に帰属する、という自己責任と貧困原因が緊密にかさなりあったイメージで一般的にとらえられることも多かった。その結果、残念ながら、社会福祉のなかでも貧困は極めて矮小化、限定的なものとなり、問題関心は薄れ、慈恵的、救貧的な対処療法的なスキル偏重なものとなっていたことも否めない。今日の社会福祉そのものの脆弱性を認識せざるを得ない。
3.11以前、大都市を中心に社会的排除や差別、あるいは、精神的荒廃などを含む複合的な原因による解決困難な貧困をどう解決するかが労働経済学などの分野ではすでにかなり議論されてきていた。さらに、東北地方は極度の人口の高齢化と労働人口の減少、地域経済の低迷、すなわち、経済グローバリゼーションの枠から外れた地場産業の低迷等というきわめて深刻な地域的な貧困・生活問題が横たわり苦しんでいた。今回の大震災で被災した人々の生活はさらに困窮化し、生活の問題は深化するだろう。発電所の事故による環境破壊がさらに覆いかぶさるように地場産業や農水産業を破壊していくだろう。今回の大震災とそれにともなう発電所の事故による生活破壊は、そこから自力では生活再建できない、立ち直れない多くの人々を生み出し、貧困の海に投げ出すはずなのだ。すでにあった大都市圏を中心とした複合的な貧困、さらに東北地方の震災によってもたらされる貧困。1945年の敗戦以来、今こそ、社会福祉や社会保障の本来的役割が重要である時代はない。
貧困・生活問題は、ひとり、一つの家族などにとどまることはない。一家族の貧困・生活問題は連鎖し、次の世代に引き継がれていく。それがさらに問題の解決を困難にさせる。われわれはこの貧困の「連鎖」を断ち切るために、何をすべきか。
3.11以前にあった貧困・生活問題を生み出していた社会システムの問題点をまず、明らかにしなければならないだろう。そして「以後」は、「以前」の問題点をふまえ解決しつつ、さらに創出され、この先、深刻化するであろう被災地を中心とした貧困・生活問題の実像を生活レベルからえぐるという作業を繰り返さなければならないだろう。個人の人生における貧困の連鎖を断ち切り、また、家族への貧困波動を食い止め、それらの世代間に継承されるサイクルを分断するためには、斬新な社会的方策を生み出すための社会福祉実践、当事者を含む運動とそれを支える研究が必要である。
日銀は日本経済は今回の大震災の影響で、一時的に落ち込むが、復興景気で、秋ごろから復調するという予想をだしている。しかし、マクロで経済が復調するということと、ひとりひとりの生活が再建するというのは違う。復興景気の恩恵に浴さない層は必ず出る。被災した地域の復興はそこに住む人々の人生、生活が本当の意味で再建できたときと考えると道は遠く険しい。
今回の大震災、津波、とりわけ原子力発電所の事故を通して、環境問題へのアプローチが重要であることは明白である。環境汚染が地域生活の根幹を破壊し健康被害をもたらす。社会福祉はこれまで環境問題にどう取り組んできたのか。少なくとも、1980年代初頭までの社会福祉の枠組みには、公害・環境問題がきちんと入っていた。しかし、いつのまにか消えていった。現在の社会福祉士養成課程のカリキュラムのなかには位置づけられていない。しかし、環境破壊が地域破壊や健康被害、それにともなう生活破壊を引き起こすことは前述のとおりで、社会保障、社会福祉の理論枠組みに環境問題の視点を改めて組み込むことが必要であろう。
3.11「以前」と「以後」との「連続性」と「非連続性」、そのなかから「以後」の新しい社会福祉の枠組みを考える必要を強く感じる。