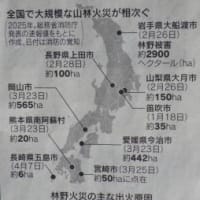今朝はここ数日より幾分涼しめ・・いつもより楽にウオーキングができました~・・。
 今週は週半ばには台風13号が東日本を目指して
今週は週半ばには台風13号が東日本を目指して
やってくるという予報・・そのせいで涼しいの?
台風がやってくるというと・・そろそろ秋冬用の
準備(土作り)です。
まだ早いと思われるでしょうが、季節は少しだけ
進んでいます。 今朝・ウォーキングの際に見た
田んぼ、左の写真のように「稲穂が・・」です。
暑い!暑い!といっているうちに、自然界は着々と次の季節を目指しているようです。
敷物の機能といえば地面や床からの断熱や防湿・防塵、クッション性などが考えられるが
この常識をくつがえす「油団」という面白い?敷物があります。


福井県鯖江市で表具店「紅屋紅陽堂」を営む“牧野さん”の工房が製作工程を見てみた。
上質の和紙を15~20枚も貼り重ね、八畳間ならその大きさに作った敷物で、裏に渋柿
表に荏胡麻(えごま)の油をそれぞれに塗り、仕上げには豆腐の搾り汁でツルツルに磨く。
和紙1枚ごとに硬い刷毛で力強くたたいて毛羽立て、上下の紙の繊維を一体化させる手間
が品質の決め手になる。 八畳の油団で1万回以上も叩き、3~4㍉の厚みに仕上げる。
6月ごろから畳の上に敷いて過ごすもので、手で触れたり、はだしで歩いたりすれば不思
議な「ひんやり感」が味わえるという・・。
材料費も手間もかかり、かなり高価になるので、何代も続く旧家や高級料亭などで使用さ
れるだけのぜいたく品になってしまったそうだ。 巻いて収納する土蔵も必要といえば、
現代離れした品だといわざるを得ないが、70~100年も使用に耐える品質は無視で
きないといわれているという。
なぜ「ひんやり」するのか? その謎を科学者の“武田氏”の研究が挑み、動画サイト
「ガリレオ放談」の第31回でその成果を紹介してるそうです。
当初、そのメカニズムは通常の科学的分析では全く解けなかった。 「気のせいでは」
という意見も出るなか、ある学生が、多くの材料に手のひらを当てたときの状態を
サーモグラフで撮影し、アルミ板と油団が同じように手の熱の痕跡が8分後には消え
ることを確認したという。
油団の熱伝導率はアルミの千倍も悪く、手の熱を吸収・拡散するはずがない。
それで油団が吸収したのは熱ではなく、手の汁(水と油)だと武田氏は気付いたという。
汗を瞬時に吸収することで気化熱が肌を冷たく感じさせる。 これが油団の仕組み?
油団の記録は近世末に遡るが、さらに古くからの蓄積があったに違いない。 幕末に来日
した英国駐日大使“パークス氏”も油団に注目して断片を持ち帰り、ビクトリア・アン
ド・アルバート博物館に保存されている。
地球温暖化が問題にされる今こそ、このような自然素材の伝統的用具の価値に注目して
その技の保存と新しい活用アイデアを模索すべきではないだろうか
 今週は週半ばには台風13号が東日本を目指して
今週は週半ばには台風13号が東日本を目指してやってくるという予報・・そのせいで涼しいの?
台風がやってくるというと・・そろそろ秋冬用の
準備(土作り)です。
まだ早いと思われるでしょうが、季節は少しだけ
進んでいます。 今朝・ウォーキングの際に見た
田んぼ、左の写真のように「稲穂が・・」です。
暑い!暑い!といっているうちに、自然界は着々と次の季節を目指しているようです。
敷物の機能といえば地面や床からの断熱や防湿・防塵、クッション性などが考えられるが
この常識をくつがえす「油団」という面白い?敷物があります。


福井県鯖江市で表具店「紅屋紅陽堂」を営む“牧野さん”の工房が製作工程を見てみた。
上質の和紙を15~20枚も貼り重ね、八畳間ならその大きさに作った敷物で、裏に渋柿
表に荏胡麻(えごま)の油をそれぞれに塗り、仕上げには豆腐の搾り汁でツルツルに磨く。
和紙1枚ごとに硬い刷毛で力強くたたいて毛羽立て、上下の紙の繊維を一体化させる手間
が品質の決め手になる。 八畳の油団で1万回以上も叩き、3~4㍉の厚みに仕上げる。
6月ごろから畳の上に敷いて過ごすもので、手で触れたり、はだしで歩いたりすれば不思
議な「ひんやり感」が味わえるという・・。
材料費も手間もかかり、かなり高価になるので、何代も続く旧家や高級料亭などで使用さ
れるだけのぜいたく品になってしまったそうだ。 巻いて収納する土蔵も必要といえば、
現代離れした品だといわざるを得ないが、70~100年も使用に耐える品質は無視で
きないといわれているという。
なぜ「ひんやり」するのか? その謎を科学者の“武田氏”の研究が挑み、動画サイト
「ガリレオ放談」の第31回でその成果を紹介してるそうです。
当初、そのメカニズムは通常の科学的分析では全く解けなかった。 「気のせいでは」
という意見も出るなか、ある学生が、多くの材料に手のひらを当てたときの状態を
サーモグラフで撮影し、アルミ板と油団が同じように手の熱の痕跡が8分後には消え
ることを確認したという。
油団の熱伝導率はアルミの千倍も悪く、手の熱を吸収・拡散するはずがない。
それで油団が吸収したのは熱ではなく、手の汁(水と油)だと武田氏は気付いたという。
汗を瞬時に吸収することで気化熱が肌を冷たく感じさせる。 これが油団の仕組み?
油団の記録は近世末に遡るが、さらに古くからの蓄積があったに違いない。 幕末に来日
した英国駐日大使“パークス氏”も油団に注目して断片を持ち帰り、ビクトリア・アン
ド・アルバート博物館に保存されている。
地球温暖化が問題にされる今こそ、このような自然素材の伝統的用具の価値に注目して
その技の保存と新しい活用アイデアを模索すべきではないだろうか