小正月も彼方に去り、お正月を感じさせるものはすっかり消えてしまいました。
「今年こそは、出来る?」と思っていた「かるた会」。
しかし、人数が集まらない、来客があってもすぐ帰る、ということで会はまたしても来年へと持ち越され、かるたは出番なく納戸へ静かに戻りました。
我が家の「小倉百人一首かるた」の取り札は木で出来ています。
これは函館地区のみならず、北海道全域で見られます。
(写真をクリックすると拡大できます。)

何故木札なの?由来はこうです。
本道の初期開拓者にとって、紙は高価で貴重な物。
ましてや、かるたには厚い紙が使われますから、一層手が届きません。
遊びの道具ですから形には拘らず、かるたとして使える材質であれば良いという考えが芽生えました。
そこで、代用材とし目をつけたのが建物や船を造るときに出る半端材。
これを、かるた大に切りそろえ使い出しました。
すると「丈夫で長持ち」という評判、道内全域へと広がっていったようです。
木の取り札には、ご覧のとおり「下の句」より書かれていません。
公式競技では、北海道独特の「下の句読み」。ほかに細かい規定があります。
我が家に伝わる方法は、読み手は上の句からの読み。
読み始めたら、下の句を素早く思い出さないと負け。
そして、遠慮なく敵陣まで手を伸ばし突くことが勝利へ結びつきます。
北海道開拓者にとって、寒さ厳しい長い冬の最大の楽しみは「かるた」だったのでしょう。
外は吹雪、赤く燃える囲炉裏の回りで、どてらを着込んだ家族が笑いながらかるたの取り合い。そんな姿が浮かんできます。
「天津風 雲の通い路吹きとぢよ 乙女の姿 暫しとゞめん」
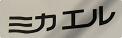




















歌留多を見ると、親父とその中間達を思い出します
親父は生前、函館下の句歌留多会、会長でした
北海道下の句歌留多初代名人位でもありました
よく大会で遠征する時に連れて行ってもらいました
http://hakodate.blog.drecom.jp/archive/496
その息子の私は、まったく出来ません。
にぎやかさ、熱気、迫力にびっくりです。
人気があったんですね。
男性が圧倒的に多いようですが、大会は男女別で開かれたのでしょうか?。
身近に歌留多達人がおられたとは、まったく知りませんでした。
お父さんは、頭脳と反射神経の良さがピカイチだったと思います。ミカエル
2~3日、仮眠をとり勝負してましたね
色々な地域で交代で大会を開いてました
函館湯の川、旭川、札幌、定山渓、登別
けっこうな人が参加しますから
温泉場だったんでしょう
休みが取れる、国鉄職員、郵政の方が多かったようです
毎月、何日かは我が家の二階で練習してました
自分は参加できませんでしたが
気合の入った勝負には、あこがれてました
子供歌留多は大森神社や桟橋にあった景福丸(旅館)でも行われてたようです
遠い昔の情報でした。
やはり想像以上の盛会さだったんですね。
国鉄青函局にはたくさんの人がいましたからね。
桟橋横に係留され営業していた景福。
泊まってみたかったですよ。ミカエル
なるほど、昔は紙は宝物でしたね。
ようこそマイブログへ。
子供の頃の話ですが、確かにどこの家にもありました。薄汚れ、古さが感じられました。
今は、昔言葉で言えば、本家により残っていないようです。
なにしろ、ゲームの時代ですからね。ミカエル