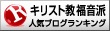「確かに塩は良いものだ。だが、塩も塩気がなくなれば、その塩は何によって味が付けられようか。」
ルカ 14章 34節
喩えを語られているので、聞く耳のある者は聞きなさいと言われています。関心のない人、
求道しない人はこの譬えだけで終わってしまいますが、その意味を解き明かしてほしい、
そして自分に どのように関わるか知りたいと願っている人には知らされる内容です。
キリストの弟子にならなければ、イエス様に付いてきても意味がないということです。
私たちが本気でキリストの弟子になって、イエスに付いてきていないと、
結局、世において役立つ者たちにならないのです。つまり人々に霊的な渇きを起こし、
社会や人々の心にある暗闇、そこに光を当てることができないのです。
十字架を誇ってください、パウロはそう言いました。その生活を歩んでいる時に、
初めて自分ではなく、自分の内に住んでおられるキリストが、周囲の人々に、
また社会に 対して影響力をもたらすことができるのです。
塩は防腐剤の役目があります。調味料として味を付けます。また、青菜に塩というように、
相手を枯らすほどの強烈な性質があります。イエスは、クリスチャンはこの塩味を持って
いなければならないと言われました。つまり、み言葉によって生きていくとき、
その人は世の中の腐敗を清めていく働きをします。そのためにまずクリスチャンであるあなたが清められ、
塩漬けられていなければなりません。このためには信仰による勇気、愛などが必要です。
塩の強烈さは、社会の悪い、サタンの働きに作用しなければなりません。
こうした塩味を持った働きは、クリスチャンの証と奉仕の生活から生まれます。
マルコ 9:49-50
「人は皆、火で塩味を付けられる。塩は良いものである。だが、塩に塩気がなくなれば、
あなたがたは何によって塩に味を付けるのか。自分自身の内に塩を持ちなさい。」