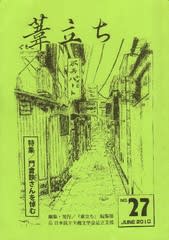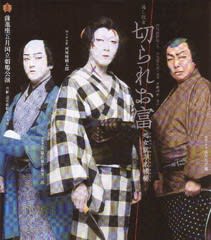クラッシック音楽をこれだけ庶民にわかりやすく、親しみ楽しくさせた映画はそうはないと思います。
昨日、川口アリオのムービックス川口で娘らと3人で「のだめカンタービレ最終楽章後編」を鑑賞して来ました。前編は先月末にテレビ放送したのでビデオに撮っておいて再度、鑑賞して行きました。

今回、後編を鑑賞するにあたって、4月末にテレビ放映された前編をみてから行きました。幸い今回の映画で演奏されるCDをのだめオーケストラが演奏し、CD4枚組みで販売するというのですが、家にあるCDをMP3プレイヤーに落として聞いています。

曲目はこんなところです。DISC1 千秋篇 (オーケストラ)
1.ベートーヴェン:交響曲第7番イ長調作品92より 第1楽章
2.ベートーヴェン:交響曲第7番イ長調作品92より 第4楽章
3.デュカス:交響詩「魔法使いの弟子」
4. ラヴェル:「ボレロ」
5.J.S.バッハ:ピアノ協奏曲第1番ニ短調BWV1052より 第1楽章
6.J.S.バッハ:ピアノ協奏曲第1番ニ短調BWV1052より 第3楽章
7.チャイコフスキー:序曲「1812年」

DISC2 のだめ篇 (ピアノ)
1.モーツァルト:ピアノソナタ第11番イ長調K.331より 第3楽章「トルコ行進曲」
2.ショパン:ピアノソナタ第3番ロ短調作品58より 第1楽章
3.ドビュッシー:「映像」第1集より 「水に映る影」
4.ベートーヴェン:ピアノソナタ第31番変イ長調作品110より 第1楽章
5.ベートーヴェン:ピアノソナタ第31番変イ長調作品110より 第3楽章から
6.ラヴェル:ピアノ協奏曲ト長調 より 第1楽章
7.ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調作品11 より 第1楽章
8.ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調作品11 より 第3楽章から
9.ベートーヴェン:ピアノソナタ第8番ハ短調作品13「悲愴」より 第2楽章 Adagio cantabile
10.モーツァルト: 2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448/375a より 第1楽章
11.大島ミチル/松谷卓編:「もじゃもじゃ組曲」より第1曲「もじゃもじゃの森」から “のだめとヤドヴィ” ヴァージョン
12.フランス民謡:「アヴィニヨンの橋の上で」

DISC3 マルレオケと仲間たち篇 (室内楽、オーケストラ BGM楽曲)
1.モーツァルト:オーボエ協奏曲ハ長調 K.314/285dより 第1楽章 ピアノ伴奏版
2.サラサーテ:「ツィゴイネルワイゼン」 ピアノ伴奏版
3.ドヴォルザーク:チェロ協奏曲ロ短調 作品104/B.191より 第1楽章から ピアノ伴奏版
4.ジョリヴェ:バソン協奏曲より 第1楽章 ピアノ伴奏版
5.ブラームス:ヴァイオリン協奏曲ニ長調作品77より 第3楽章
6.ベートーヴェン:交響曲第5番ハ短調作品67「運命」より 第4楽章
7.ベートーヴェン:交響曲第9番ニ短調作品125「合唱付き」より 第4楽章から
8.エルガー:「エニグマ」変奏曲より 第9変奏「ニムロッド」
9.マーラー:交響曲第5番嬰ハ短調 より 第4楽章(
10.チャイコフスキー:交響曲第6番ロ短調作品74「悲愴」より 第4楽章から
11.ガーシュイン:ラプソディ・イン・ブルーより

このMP3を作成した後、全のだめファン待望の「のだめカンタービレ コンプリート ベスト 100」の発売が決まりました。
これなら営業妨害にならないでしょう。